
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.02.23


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
人口が爆発的に増加している東南アジアは世界の中でも高い経済成長率を誇ります。日本企業が東南アジアに進出した理由やメリットはどのようなものがあるでしょうか。
本記事では、日本企業の進出率が高い国や東南アジア各国へ進出した際のメリットなどについて、解説します。
今後、東南アジアへの進出を検討している企業の担当者の方はぜひご覧ください。

外務省が毎年実施している「海外進出日系企業拠点数調査(2023年調査結果)」によると、東南アジア諸国に進出している日本企業の数は15,807社です。特に、ASEANに加盟している国への進出率が増加傾向にあります。
ASEANは2015年に共同体となって以降、高い経済成長を見せてきました。そのため、世界から「開かれた成長センター」として注目されています。
日本企業の多くも東南アジア諸国に注目しており、最も進出数が多いのがタイで5,856社です。次にベトナムが2,394社、インドネシアが2,182社と続きます。
業種別では、製造業が最も多く、次に卸売業です。進出が多い製造業は海外の生産拠点としてや、有力なマーケットに地理的に近いなどの理由から進出しているケースが多いと言えます。

前述のとおり、東南アジアにおいて最も日本企業の進出増加率が高いのはタイです。後に続くベトナムやインドネシアの2倍以上の進出数を誇ります。
日本企業の進出が多い東南アジア諸国の多くでは、外資企業に対しての優遇制度や経済特区といった地域が設けられています。東南アジア諸国への進出の際は、自社の製品やサービスが現地にマッチするかという観点以外に、外資企業に対してどのような規制や優遇制度があるのかも事前に調査することが重要です。
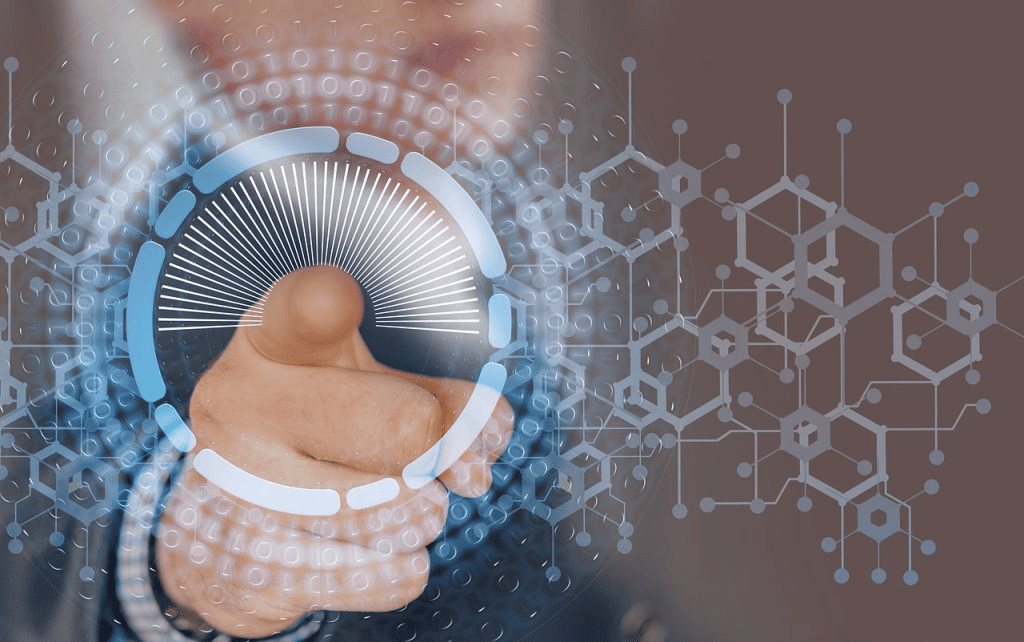
東南アジア諸国における日本企業の進出は年々増加しています。日本が東南アジアに進出した理由としては、東南アジア諸国は日本と比較して物価が安く、豊富な労働力や市場があります。また、国によっては、進出した企業へ投資の優遇制度もあるため、ビジネスチャンスと立ち上げのしやすさがあるでしょう。
その他にも多くの日本企業が東南アジア諸国へ進出する理由があります。次の3つも大きな要因です。
それぞれの要因が企業の進出とどのような関連があるのか、1つずつ解説します。
第二次世界大戦後の東南アジア諸国における人口は、1950年に約1億6,500万人でした。その後、経済成長に伴い人口増加も続き、2020年には4倍以上の約6億6,700万人に達しました。東南アジアにおける人口増加は2050年から2060年頃まで続くと見込まれています。
この人口増加は消費市場の拡大と豊富な労働力の源泉となり、企業が東南アジアに進出する際、注目すべき点と言えるでしょう。
人口増加が続く東南アジアでは日本より出生率が高い国も多いため、高齢者より若年層の人口が多い傾向にあります。若年層の多さは労働力の多さに直結するため、企業が進出して拠点をつくるときに現地での労働力調達のしやすさに関係します。
このように人口増加とそれに伴う若年層人口の厚みは、東南アジアにおける経済成長や市場拡大に期待につながるでしょう。
2024年における東南アジアの経済成長率は平均4%前後です。これは世界経済の成長率3%程度を上回る成長率であり、今後の市場拡大も期待されています。経済成長率の高さの背景には、人口増加による都市化率の上昇や所得水準が高まることで都市部における消費活動が拡大することにあります。
東南アジアの中で最も経済成長率が高いのはフィリピンです。国内のインフレ抑制や金融緩和を背景とした内需の活発化により6.1%の成長が見込まれていました。2番目に高いカンボジアは6.0%の成長が見込まれ、製造業における輸出増加や観光業の回復が成長を牽引すると予測されていました。
高い経済成長率を維持する東南アジア諸国ですが、2025年においては、人口や消費が膨大な中国市場を上回る経済成長が予想されています。2025年の中国の経済成長率は4.5%と予測されています。一方で、東南アジアの経済成長率の平均は4.7%と中国を0.2ポイント上回る見通しです。
このように東南アジアの高い経済成長率は日本企業が東南アジアに進出した理由の1つとして欠かせないと言えます。
ASEAN諸国は、経済発展を加速させるために外国企業の投資を積極的に受け入れています。そのため、多くの国で外資に対する優遇措置や規制緩和が導入されています。
具体的には、法人税の減免や一定期間の免税措置、輸入関税の軽減、土地利用に関する特例などが挙げられます。さらに、経済特区や工業団地が整備され、投資手続きが簡素化されるケースも増えています。
電子部品や自動車関連、IT、再生可能エネルギーといった分野では、外資企業にとって参入しやすい環境が整備されています。実際に、ASEAN地域への外国直接投資額は年々増加しており、日本企業も多く進出を果たしています。
各国政府が雇用や技術移転を重視し、外資を成長のエンジンとして捉えているからこそだと言えますが、優遇制度には業種や地域ごとに条件や法規制が設けられている場合があり、すべての事業が対象になるわけではない点には注意が必要です。
ASEAN諸国は日本にとって地理的に近く、輸送や通信の面で大きな利点があります。飛行機で数時間、海運ルートも短距離で結ばれているため、物流コストを抑えつつスピーディーな供給体制を構築できるのが特徴です。
自動車部品や電子機器など、部材のやり取りが頻繁に発生する産業では、この距離的優位性が競争力を高める要因となる他、日本と時差が小さいために経営判断や顧客対応においても効率的に連携を取ることが可能です。
さらに、日本とASEAN各国との外交関係は比較的安定しており、長年にわたり経済・文化交流が築かれてきました。日本政府は開発援助やインフラ整備の支援を通じてASEANとの協力を強化しており、現地での日本企業のプレゼンスを高めています。
加えて、ASEAN域内では自由貿易協定や地域包括的経済連携(RCEP)といった枠組みが広がり、貿易や投資を促進する仕組みが整いつつあります。域内関税の撤廃や非関税障壁の縮小が進み、日本企業にとってはサプライチェーンの最適化を図りやすい環境になっています。
ASEAN(東南アジア諸国連合)は東南アジアの経済発展やさまざまな面での交流や問題解決を促進することなどを目的として、1967年の「バンコク宣言」によって設立された組織です。そして、ASEAN経済共同体(AEC)はASEANに加盟する10か国を一つの経済圏とする経済統合を指します。
AECはASEAN地域全体の経済発展を目的とし、経済統合を推進するために2015年12月に発足されました。AECが立ち上げられたことで、ASEAN地域における関税が撤廃され、モノやサービスの流通や投資の自由化が促進されます。
このように経済の活性化を推進しているAECの国々へ日本企業が進出することは市場拡大や人材確保の面から、企業の成長に欠かせない要素と言えます。

人口分布や高い経済成長率などの面から、日本企業が東南アジアに進出するビジネスチャンスやメリットは多くあります。東南アジアの中でも日本企業の進出が多い国とそうでない国があります。
ここでは、それぞれの国ごとの特徴や進出するメリット・デメリットを解説します。
タイの人口は約7,000万人であり、日本の人口と比較すると半分程度です。また、出生率の低下が影響し人口は減少傾向にあるものの、人口分布では20代から50代が日本よりも多く労働人口が豊富にいます。
日本企業がタイに進出するメリットは次のようなものがあります。
タイの人件費は日本と比較すると安価であり、企業は販売管理コストを抑えることができます。次に、タイ国投資委員会(BOI)による投資優遇制度も日本企業が多くタイに進出するメリットです。BOI許可を得ることで法人税や輸入関税の免除、または優遇がされます。その他、就労ビザ取得の円滑化や事業用の土地所有も認められます。
3つ目としては、タイ政府が推進する東部経済回廊(EEC)における税制上の優遇制度です。タイ政府は国内における投資重点地域を定めています。この地域へ企業が進出すると最大8年間の法人税免除と、その後5年間の法人税50%免除という税制上の優遇措置が受けられます。
最後はタイが親日国であることです。そのため、日本製のモノやサービスへの関心も高く、それによる需要拡大が日本企業の進出の一員でもあります。また、日タイにおける友好的な関係から、企業がタイ進出時に現地での労働力確保も難しくないと言えます。
一方で課題となるのが、政情の不安定さです。タイは過去にクーデターや政治的混乱を経験しており、政権交代や政策変更によって経済活動に影響が及ぶリスクがあります。とくに外国企業に対する投資優遇策や規制が政権によって変動する可能性は無視できません。
そのほか、人件費の上昇も課題です。タイは以前は「安価な労働力」が大きな魅力でしたが、近年は経済成長とともに最低賃金が上昇しており、労務コストの負担が増しています。文化や商習慣の違いも軽視できず、意思決定のスピードが日本に比べて遅いことがあります。
タイは市場規模や製造拠点としての強みを持つ一方、政情不安やコスト上昇、インフラ格差などの課題も併せ持つ国と言えます。進出を検討する際には、リスクを十分に認識し、現地パートナーや専門家との連携を通じて対応策を講じることが求められるでしょう。
ベトナムの人口は約9,900万人です。ベトナムの出生率は1960年代と比較すると約3分の1まで低下しましたが、現在の労働人口は豊富にあります。特に25歳から40歳までの働き盛りの労働人口が豊富にある市場です。
日本企業がベトナムに進出するメリットは次のようなものです。
人口増加に伴う都市化の進展や若年層による旺盛な消費意欲が今後の消費市場の成長性や拡大を示唆しています。また、東南アジアの中でも人件費や物価が安価であることは世界の企業が注目している点です。
ベトナムの国民性は勤勉で真面目、性格は温厚な人が多いと言われています。勤勉で真面目な面から生まれる優秀で質の高い人材は、企業が現地に進出するメリットと言えるでしょう。
日本とベトナムは2009年10月に2国間で日本・ベトナム経済連携協定(EPA)を締結しました。これにより、モノやサービスの自由化と投資の円滑化などさまざまな面で連携が強化されています。EPAを締結することで、両国は相互に最恵国待遇とない国民待遇を供与します。また、日本企業がベトナムに投資しやすい環境の整備や知的財産権保護に関する協議規定も盛り込まれています。
対して課題となるのはインフラ整備の遅れです。ハノイやホーチミンといった主要都市では道路や港湾の整備が進んでいる一方で、地方部はまだ発展途上であり、物流の効率性に課題があります。
ビジネスリスクとして、法制度や規制の複雑さも挙げられます。ベトナムは外資誘致を積極的に進めていますが、法改正や規制の変更が頻繁に行われる傾向があります。行政手続きが煩雑で透明性に欠ける場面もあり、許認可の取得に時間がかかることも少なくありません。
人材に関しても課題があり、労働力は豊富で賃金も比較的低いですが、管理職や技術職といった中堅層の人材は不足しており、人材育成に時間とコストをかける必要があります。
マレーシアの人口は約3,400万人です。人口は日本の4分の1ほどですが、急速に人口が増加しています。人口分布では20代から40代が多く、労働人口が豊富な市場です。
日本企業がマレーシアに進出するメリットは次のようなものです。
マレーシアの公用語はマレー語です。しかし、ビジネスシーンにおいては、世界から企業が集まっていることから英語の使用頻度は高く現地の言葉を習得していなくても困らないでしょう。
マレーシア政府は積極的な外資企業の誘致活動を行っています。マレーシアに進出する企業が受けられる恩恵は、特定産業における税金の免除や輸入関税の減免があります。その他、研究開発にあたっての補助金を受け取ることが可能です。
主なものとしては、マレーシア投資開発庁が提供する優先セクターへの投資奨励に関するインセンティブがあります。また、イスカンダル・マレーシア地域に進出する企業は特定の産業セクターに限られますが、所得税の免除を受けられます。その他、日本はマレーシアともEPAを締結しており、モノやサービスの自由化と投資の円滑化などさまざまな面で連携が強化されています。
人口増加傾向が続くマレーシアでは20代から40代の若年層が多く、消費行動も旺盛なため今後、消費市場の拡大が見込まれます。
課題としては、人件費の上昇が挙げられます。かつては低コストの労働力が進出の大きな理由でしたが、経済成長に伴い人件費が高騰しています。そのため、単純労働を目的としたコスト削減型の進出には不向きとなりつつあります。
次に、多民族国家ならではの文化的な課題があります。マレーシアはマレー系、華人系、インド系など多様な民族で構成されており、それぞれに文化や宗教的価値観が異なります。
加えて、外資規制も課題です。特定の業種では外資比率に制限があり、現地パートナーとの合弁が求められる場合があります。この点は日本企業にとって意思決定の自由度を制約する要因となり得ます。
フィリピンの人口は約1億1,700万人と日本と同じぐらいの人口規模です。若年層の人口率が高く世界でも有数の労働力輸出国です。
日本企業がフィリピンに進出するメリットは次のようなものがあります。
フィリピンにおける人口増加は1960年代から続いており、1960年は約2,800万人だったのが、現在は4倍以上に増えています。この傾向は2050年頃まで続くと見込まれており、フィリピンは東南アジアの中でも有力な巨大マーケットと言えます。
次にフィリピン経済特区長が管轄している外資企業を優遇する経済特区がある点です。優遇措置を受けるためには、輸出企業であること、生産品の70%以上を輸出していることが条件として挙げられています。
これらの条件を満たすと4年から最長8年間、法人免税所得税(インカム・タックス・ホリデー)が適用されます。なお、最長8年間の免税適用を受けるためには、いくつかの条件を満たしパイオニア企業と認められることが条件です。
フィリピンは英語を公用語としていることから、世界88か国の英語力ランキングでは14位と上位に位置しています。東南アジアにおいてはシンガポールに次ぐ2位であり、日本企業が進出する上で、英語が使えれば言葉の障壁があまり高くないでしょう。
大きな課題はインフラの不十分さが挙げられます。首都マニラを中心に道路渋滞や公共交通機関の整備不足が深刻であり、物流や従業員の移動に大きな影響を与えています。
さらに、自然災害リスクも気になるところです。フィリピンは台風の常襲地帯であり、洪水や土砂災害も頻発しています。企業の拠点が被害を受けると事業活動が一時的に停滞するリスクが高いため、災害リスクを織り込んだ事業継続計画(BCP)の策定が欠かせません。
治安や法制度の不透明さも課題です。フィリピンは都市部では治安改善が進んでいるものの、一部地域では犯罪やテロのリスクが残っています。さらに、行政手続きの複雑さや汚職の問題もビジネスの円滑な運営を妨げる要因となりやすいでしょう。
シンガポールの人口は約600万人とあまり多くはありません。しかし、シンガポール政府による企業支援、規制や手続きが明瞭でデジタル化している部分などは進出企業がビジネスをしやすい点でしょう。
日本企業がシンガポールに進出するメリットは次のようなものがあります。
シンガポールの法人税は最高17%と低く設定されており、スタートアップ企業や中小企業に対しての税制上の優遇措置が充実しています。また、日本とは異なるさまざまな軽減税率制度があり、これらの制度を活用することで創業し始めたばかりの企業でもビジネスがしやすいでしょう。
また、現地法人を設立するにあたり、手続きが簡素で比較的設立がしやすいのも日本企業の進出が多い要因の1つです。法人設立の手続きは容易ですが、政府がシンガポール国民の雇用強化を推進しているためビザの取得や現地での口座開設の難易度は高くなりつつあります。
地理的優位性としては、シンガポールは東南アジアの中心に位置していることです。アジア全体へのアクセスがしやすく、国際的な貿易や物流のハブとしての機能を持っています。物理的な優位性を活かして中継貿易の拡大に成功し、外資企業を積極的に誘致することで経済成長を遂げています。
対して課題といえるのは、コストの高さです。法人税率は比較的低水準に抑えられていますが、オフィス賃料、生活費、人件費はASEAN諸国の中でも突出して高額です。特に都市部での不動産コストは企業の固定費を圧迫する要因となるでしょう。
シンガポールの国内市場の規模が小さい点もデメリットです。人口が約600万人と限られているため、消費市場としての成長余地は限定的です。多くの企業はシンガポールを「ASEAN市場への拠点」として位置づけていますが、あくまでハブとしての機能が中心であり、現地の販売市場としては拡大が見込みにくいのが実情です。
外資企業が集中しているため競争が激しいこともビジネスリスクと言えます。シンガポールは国際ビジネスの中心であり、多国籍企業が拠点を構えているため、日本企業が差別化を図るのは容易ではありません。
インドネシアの人口は約2億7,750万人です。東南アジア諸国の中で最も人口が多い国です。世界の中でも第4位の人口の多さから、その巨大な市場に対して、経済成長が期待されています。
日本企業がインドネシアに進出するメリットは次のようなものがあります。
インドネシアは経済成長に伴い中間層も増加しました。それにより、個人消費が促進されています。また、天然資源が豊富にあり、石炭や天然ガスなどの天然資源を日本より低価格で利用可能です。
その他、外資企業に対しての優遇税制が導入されています。一定の条件を満たせば、さまざまな優遇処置を受けられます。優遇措置の一例として、タックスホリデー制度があります。これは投資優先先事業分野に指定されたパイオニア産業に対して、5年から最長20年間にわたり、投資額に応じて法人税の50%もしくは100%が減額されるものです。
その他に保税区内の優遇措置や各種税制措置、自由貿易地域および自由貿易港、経済統合開発地域(KAPET)にある企業への優遇措置などがあります。
半面、法制度や行政手続きの複雑さが大きな課題です。インドネシアでは規制の変更が頻繁に行われるうえ、制度の運用が不透明な場合が多いため、外国企業にとって予期せぬ負担が発生するリスクがあります。
次に、インフラ整備の遅れも挙げられます。首都ジャカルタや主要都市では道路や港湾整備が進んでいるものの、地方部では物流インフラが十分に整っていませんし、電力や通信インフラの不安定さも事業運営に影響を与える可能性があります。
インドネシアは人材面でも課題があり、人口は多いものの、産業の高度化に対応できる熟練労働者や管理職層は不足しています。そのため、人材育成や教育に時間とコストを投資しなければなりません。

国別リスクを把握することは重要ですが、ASEAN 全体で共通して押さえておくべき注意点もあります。進出先を選定・戦略設計・ビジネスリスク管理をする際の基盤となるでしょう。
以下では「言語・文化」「インフラ・法制度」「政情・治安」「自然災害」をテーマに、最新情報を交えて解説していきます。
ASEANは10カ国から成り立ち、それぞれに異なる言語や文化的背景を持っています。その多様性は魅力である一方、日本企業にとってはビジネス展開上の大きなハードルにもなります。
まず言語の違いですが、英語が通じやすい国(シンガポール、フィリピン、マレーシアなど)もある一方で、タイ語やベトナム語、インドネシア語といった現地言語を理解できなければ、従業員や取引先との円滑な意思疎通が難しい国も少なくありません。
英語を社内公用語としている企業も多いですが、現地スタッフ全員が十分な英語力を持つわけではないため、誤解や業務効率の低下につながるリスクがあります。
文化面でも、日本との違いは大きな影響を及ぼします。例えばタイやインドネシアでは上下関係を重視する文化が根付いており、現場での意見交換や提案が表に出にくい傾向があります。
また、宗教的価値観も日常業務に影響を与えます。イスラム教徒が多い国では礼拝時間への配慮や断食月(ラマダン)中の勤務対応が必要ですし、祝祭日や勤務スタイルも宗教によって変わるため、日本の慣習そのままでは業務が円滑に進まない可能性があります。
ASEAN諸国の多くは経済成長が著しい一方で、インフラや法制度の整備が十分に追いついていません。この遅れは、日本企業の事業運営に直接的な影響を与える要因となっています。
インフラ面では、都市部では道路や港湾の整備が進んでいる国もありますが、地方部では物流網が脆弱で、製品の輸送に時間やコストがかかるケースが多く見られます。電力や通信のインフラも不安定で、停電やインターネット接続の不具合が業務効率を下げるリスクを抱えています。
法制度に関しても課題があります。ASEAN諸国では外資を歓迎する一方、投資規制や外資比率の制限を設けるケースが多く、国ごとに条件が異なります。法規制や法改正が頻繁に行われる傾向もあるため、その運用が必ずしも透明ではない場合もあります。
結果として、日本企業はインフラや法制度の不確実性を前提に、現地パートナーや専門家と協力しながら柔軟に対応する体制を整えておく必要があります。長期的な視点でのリスク管理が求められる領域といえるでしょう。
ASEAN諸国は経済成長を続けていますが、政治の安定度や治安の状況には国ごとの差があります。これらのリスクは日本企業の事業運営に直結するため、注意が必要です。
まず政情不安についてです。タイは過去にクーデターや政権交代を繰り返しており、現在も政治的な対立が社会不安につながるリスクを抱えています。
ミャンマーでは2021年のクーデター以降、国際社会との関係が不安定で、投資リスクが非常に高い状況が続いています。インドネシアやフィリピンは比較的安定していますが、選挙のたびに政策変更の可能性があり、外資に影響を与えるケースもあります。
治安面では、国ごとに状況が大きく異なります。フィリピンでは首都マニラを含む都市部で犯罪件数が減少傾向にあるものの、一部の地方では依然として反政府武装勢力やテロリスクが残っています。インドネシアも観光地でのテロ事件が過去に発生しており、現在も警戒が必要です。
日本企業にとって重要なのは、治安リスクを前提にした対策を講じることです。現地駐在員や従業員の安全を守るために、最新の治安情報を収集し、危険地域への立ち入り制限や緊急時の避難計画を策定することが欠かせません。
ASEAN地域は自然災害のリスクが高いエリアとしても知られています。日本企業が進出する際には、この点を十分に考慮する必要があります。
まず、台風の影響を強く受けるのがフィリピンです。毎年数十回規模の台風が発生し、そのうち数回は大規模な被害をもたらします。洪水や停電が発生すれば事業活動は一時的に停止し、物流やサプライチェーンにも影響が及びます。
インドネシアやフィリピンは「環太平洋火山帯」に位置しており、地震や火山噴火のリスクが高い国です。実際に過去には大規模な地震や津波によって甚大な被害が発生し、企業活動に深刻な影響を与えた事例があります。
洪水もASEAN諸国では頻発する自然災害のひとつです。特にタイでは雨季の集中豪雨によって大規模な洪水が発生し、工業団地や製造拠点が浸水して操業停止に追い込まれる事例がありました。
こうした自然災害リスクに備えるには、立地選定の段階から災害リスクを織り込むことが重要です。さらに、被災時に備えた事業継続計画(BCP)の策定や、複数拠点での分散生産体制を構築しておくことも有効です。

日本企業が東南アジア諸国に進出し、ビジネスを成功させるためにはさまざまな準備が必要です。
・現地調査と戦略
・現地ニーズとトレンドを把握する
・現地に精通した人材の確保
・積極的なコミュニケーション
・他社との差別化
東南アジアは経済成長が目覚ましくビジネスチャンスや市場の成長も拡大傾向にありますが、現地ニーズやトレンドの把握を理解した上で戦略を立てなければせっかくの立ち上げ機会も活かせません。
ここでは、それぞれの重要性について確認し、日本企業がビジネスリスクを抑えながら、東南アジアへの進出を成功させるためのポイントをおさえましょう。
はじめにターゲット先の言語や文化、慣習を把握する必要があります。その他、ビジネス環境における規制や企業が受けられる優遇制度なども事前に調査しておくことが重要です。
東南アジア諸国は同じASEANでもそれぞれの国において、ビジネス環境や消費市場ニーズは異なります。それぞれの地域特性を意識した進出戦略やマーケティング戦略を立てなければなりません。
市場調査における現地ニーズと最新トレンドの把握は自社製品やサービスがその国で受け入れられるかを判断するポイントです。さまざまな情報やデータを収集し分析したり、現地に赴いて市場調査したりすることは現地でのビジネス拡大成功のためのカギの1つです。
複雑な市場動向や潜在ニーズの調査、市場の持つポテンシャルに基づいた戦略策定に課題を持っている企業の担当者の方は、こちらをご覧ください。
東南アジアに進出するにあたりビジネス成功のカギの1つは、現地に精通した人材を確保することです。日本企業が東南アジアに進出する際、現地法人を統括する人材が必要です。
現地法人を統括する人材に必要なスキルは、現地の言語や文化、商習慣に精通している、現地スタッフをまとめられるリーダーシップ能力です。また、現地法人は本社との調整や交渉なども多くあります。そのため、本社の方針を理解し、現地スタッフに共有して実行に移せる、本社と現地双方の利害を調整できる交渉力も必要な能力です。
同じアジア地域でも日本とは言葉も文化も商慣習も異なります。現地法人を設立し、現地での雇用をする場合は、コミュニケーションを積極的に取ることが重要です。
日本では言葉の行間を読んだり空気を読んだりするということもビジネス上で往々にしてあります。しかし、海外では空気を読むことは通じません。
言葉にしたものがその通りに実現されるよう、スタッフは動きます。そのため、こまめなコミュニケーションを取ることを意識しましょう。
国内市場においても同じことをマーケティングでしますが、自社の強みや弱みを明確化するのが重要です。競合他社とは異なる自社独自の価値を市場でアピールし、顧客に提供することで、市場優位性を確立できます。
差別化戦略は、市場におけるポジションの確立と高い利益率とシェアの確保につながります。

日本企業が東南アジアに進出した理由や進出することのメリットを説明してきました。ここでは、東南アジア進出を成功した日本企業の事例をご紹介します。
〈東南アジア進出に成功した日本企業3社〉
・ヤクルト
・CoCo壱番屋
・株式会社ギフティ
ヤクルトはインドネシアや台湾など東南アジアに進出して成功しています。同社は1964年に台湾で初めて海外に進出、その後、1991年にインドネシアへ進出しました。インドネシアでの販売ルートは卸業者や問屋を介して販売することが一般的です。
一方でヤクルトは日本でも行っている「ヤクルトレディ」を現地で採用し、独自の訪問販売による消費者との信頼関係構築を進めていくことで、初年度は1日あたり7万本だった販売数量が、30年間で100倍の700万本以上を1日に販売するまでにビジネスが成長しました。
同社は現地生産、現地販売を基本とした「現地主義」を貫きながら、ヤクルトブランドのグローバル化を推進しています。
CoCo壱番屋はタイをはじめシンガポールやフィリピンなど東南アジアの複数国に進出しています。その中でも2008年8月に進出したタイでは、店舗数を順調に増やしていき成功を収めています。
日本での同社のイメージは手軽で安くオリジナルカレーが食べられるというものでしょう。日本におけるカレーライスは家庭の味を代表する1つです。一方でタイ進出にあたっては、カレーになじみのないタイ人に興味関心を持たれるよう「高級な日本式カレー」と打ち、ブランド戦略を始めました。
また、タイでの展開において、現地の大手外食チェーンであるフジ・グルメクリエーションとパートナーとして組んだことも成功要因の1つです。フジ・グルメクリーエションはタイにおいて100店舗以上を展開してます。
現地の消費者ニーズや販売やマーケティングに関するノウハウを持ち、タイ国内での展開に成功している企業と手を組むことで、市場への浸透を図りました。
ギフティはデジタルギフトの取り扱いをしています。2018年9月に、東南アジアにおける本格的な事業展開を目的として、マレーシアに現地法人を設立しました。同社がマレーシアに進出したのは東南アジアの中でもスマートフォンの普及率が高く、キャッシュレス決済なども浸透しているためでした。
同社の商材はデジタルギフトという観点からスマートフォンの普及率やキャッシュレス決済の浸透、デジタルギフトに対しての抵抗感がない程度の経済的豊かな国であることが進出先の要素としてあります。同社では東南アジアへの進出において、これらの要素の市場調査を行い今後もASEAN地域への展開を図る計画です。

日本企業が東南アジアに進出した理由やメリットはそれぞれあります。ただし、同じアジア、同じASEANでも国によって文化やビジネス環境は異なります。
現在は、東南アジア諸国はどこも人口が多く、その中でも若年層の人口が多くあります。そのため消費市場は拡大傾向にあり、日本企業が進出してビジネスを拡大する機会はたくさんあるでしょう。
しかし、現地の顕在化したニーズやトレンド、さらには潜在ニーズまで把握するためには市場調査は不可欠です。

AXIA Marketingは市場調査におけるプロ集団です。日本企業が東南アジアに進出するための市場調査から進出時の戦略策定サポートまで一気通貫でサービスを提供できます。自社の製品やサービスが現地にマッチするかどうか、東南アジアに進出するメリットがあるのかなどもアクシアの市場調査にお任せください。
またアクシアでは、海外市場への参入を検討している企業に向けて、市場分析や法規制の理解、現地でのビジネス展開戦略の策定といった幅広い範囲でのサポートが可能です。多角的な側面から、海外市場に効果的に進出するためのコンサルティングを提供します。
サービスの詳細については、こちらをご覧ください。
1時間の無料オンライン相談も承っております
お見積りなどもお気軽にお問い合わせください
関連記事
・シンガポール進出支援・タイ進出支援・中国進出支援・インド進出支援・韓国進出支援
参考文献
・東南アジアへ進出する日本企業数の推移と進出するメリットについて-TOMAコンサルタンツグループ
・東南アジアの経済成長、2024年は4.6%前後の見通し-ジェトロ
・東南アジア(ASEAN)における日本企業の進出ーその実態と理由とは-フカガワ
・タイに進出する有名企業は?進出先にタイが人気の理由も解説-IDG
・マレーシア進出のメリット・デメリット|日本企業の拠点数・最新進出動向-Digima〜出島〜
・海外進出に伴う社内体制の整備:必要な人材と育成方法-One Step Beyond
・日本企業がインドネシアに進出して成功した事例 一覧|成功した理由と成果-INDONESIA WORKS
Copy Link





