
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.10.29


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
近年、世界的なEC市場の拡大と円安の追い風を受け、日本企業による越境ECへの注目が急速に高まっています。国内市場が成熟し需要が頭打ちになる一方で、海外では日本製品への信頼と人気が根強く、MADE IN JAPANブランドは高い競争力を持っています。オンライン上で世界中の顧客とつながる越境ECは、中小企業や個人事業主にとっても新たな販路拡大のチャンスです。
本記事では、越境ECの基本から始め方、構築方法、成功のポイントまでを徹底解説し、初めての方でもスムーズに海外販売をスタートできるよう実践的に紹介します。

越境ECとは、インターネットを通じて海外の消費者に商品を販売する仕組みのことです。つまり、日本国内の事業者が海外向けにオンライン販売を行うビジネスモデルであり、国境を越えた電子商取引を指します。
従来の輸出と異なり、現地に店舗や代理店を設ける必要がなく、ECサイトや海外モールを活用することで、個人や中小企業でも海外市場へ直接アクセスできるのが特徴です。近年は、スマートフォンの普及や物流ネットワークの発達、そして円安による価格競争力の向上を背景に、越境EC市場が急拡大しています。
さらに、SNSを通じた情報発信やレビュー文化の広がりにより、海外の消費者が日本ブランドを直接購入するケースも増加。これにより、国内にいながらにして世界中の顧客を相手に販売できる時代が到来しました。越境ECは、中小企業にとってもグローバル市場への新たな成長機会を生む有力な手段と言えるでしょう。

日本国内では少子高齢化が進み、国内消費市場の成長が鈍化する一方で、海外では中間層の拡大やデジタル化の進展により購買力が高まっています。こうした背景の中、越境ECは新たな販路拡大の手段として企業の注目を集めています。
円安による価格競争力の上昇や、日本製品への根強い人気も追い風となり、今や大手企業だけでなく中小企業や個人事業主にとっても現実的な海外進出手段となっています。
日本では人口減少と高齢化により、国内消費市場が年々縮小傾向にあります。地方では購買層の減少が顕著で、新たな成長機会を国内だけで見出すことが難しくなっています。一方で、アジアをはじめとする新興国では経済発展が著しく、中間層の拡大に伴い消費意欲が高まっています。中国や東南アジアではスマートフォンやECプラットフォームの普及が進み、オンラインショッピングの利用が日常化しています。
このような市場環境の変化により、日本企業にとって海外市場は大きな成長余地を持つ魅力的なフィールドとなっています。越境ECは、現地に店舗を構えることなく販路を拡大できるため、初期投資を抑えつつ海外の顧客と直接取引が可能です。国内需要の減退をカバーし、新しい収益源を確保する手段として、越境ECへの関心は今後さらに高まっていくでしょう。
為替レートの変動、特に円安は越境EC事業者にとって大きなチャンスです。円安が進むと、日本の商品価格が海外の消費者から見て割安になり、購買意欲が高まります。例えば、1ドル=150円のような為替環境では、海外から見ると日本製品を安く購入できる状態が続きます。
この価格競争力の向上が、海外からの越境EC需要を押し上げているのです。さらに、品質の高い日本製品をお得に入手できるという点は、海外のバイヤーや消費者にとって強い魅力となっています。実際、円安期には越境ECサイトへのアクセス数や注文数が大幅に増加する傾向があります。
日本側にとっても、為替差益を活かして海外売上を拡大できるタイミングと言えるでしょう。越境ECは、為替変動を追い風にできる柔軟な販売チャネルとして、多くの企業が新規参入を検討する要因になっています。
MADE IN JAPANは、今なお世界中で高い評価を受けています。特にアジア圏では日本製品に対して「高品質」「信頼性」「デザイン性の高さ」といったブランドイメージが強く、家電、コスメ、食品、アパレルなど幅広い分野で需要があります。
欧米諸国でも、日本の文化やライフスタイルに根差した商品はプレミアムブランドとして受け入れられているのです。また、アニメ・漫画・ゲームなどのクールジャパンコンテンツの影響もあり、日本製品への関心が若年層を中心に広がっています。
SNSや動画プラットフォームを通じて日本ブランドが自然に拡散され、海外消費者が自ら越境ECサイトを利用して購入するケースも増加。こうした文化発信と購買行動の一体化が、日本企業の海外販売に新たな追い風をもたらしています。越境ECは、このグローバルな日本ブランド需要を的確にキャッチできる最前線の販売チャネルと言えるでしょう。

越境ECを成功させるためには、勢いだけで始めるのではなく、入念な準備と計画が不可欠です。販売国の選定から商品戦略、法律や物流の確認、決済手段の整備に至るまで、一つひとつのステップを丁寧に進めることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな事業展開が可能になります。
外取引では、商習慣・通貨・文化などが大きく異なるため、国内ECの延長線では通用しません。ここでは、越境ECを始める前に押さえておくべき6つの準備ステップを解説します。
越境ECを始める際、最初に決めるべきは「どの国で」「何を売るか」です。販売国を選ぶ際には、市場の成長性、競合状況、購買力、文化的な嗜好などを総合的に判断する必要があります。
例えば、日本製のコスメや健康食品は東南アジアで人気が高く、アニメ関連グッズは欧米の若年層に需要があります。このように、国ごとの需要特性を理解した上で商品を選定することが重要です。
また、商品の選定では海外配送に適しているかもポイントとなります。壊れやすい商品やサイズが大きい商品は、物流コストや破損リスクが高くなるため注意が必要です。
さらに、現地の規制によって輸出が制限される品目もあるため、販売候補リストを作成して商材ごとに適合性を確認することが成功の第一歩です。
販売国を決定したら、次に行うべきは市場調査です。現地消費者の購買行動、人気ブランド、価格帯、販売チャネルなどを分析することで、自社商品のポジショニングを明確にできます。オンライン調査ツールやSNSのトレンド分析、ECモールのランキングデータを活用すれば、低コストで有益な情報を収集できます。
また、現地語での検索キーワード分析を行うことで、消費者がどのような言葉で商品を探しているかを把握でき、SEOや広告施策にも役立ちます。さらに、JETROや商工会議所、現地コンサルティング会社のレポートも有効な情報源です。感覚的な判断ではなく、データに基づいた市場分析を行うことで、需要のある国・カテゴリに焦点を当てた戦略的な展開が可能になります。
海外販売を行う際は、現地の法律や規制の把握が欠かせません。輸出入に関する法規制、税関手続き、製品認証、商標登録、消費者保護法など、国ごとに異なるルールが存在します。例えば、EUでは化粧品や食品に対して厳格な安全基準が設けられており、アメリカではFDA認証が必要なケースもあります。
違反すると罰金や販売停止などのリスクがあるため、事前に確認し、必要に応じて専門家やコンサルティング会社のサポートを受けることが重要です。
また、販売契約や返品ポリシーなどの商取引ルールも現地基準に合わせる必要があります。BtoC取引では、消費者保護の観点から返金ルールや表記義務が厳しいため、現地法令に準拠した運営体制を整備することが信頼構築につながります。
越境ECでは、現地の顧客が安心して支払いできる決済手段を導入することが不可欠です。国や地域によって主流の決済方法は異なり、クレジットカードが一般的な国もあれば、デビットカード、電子ウォレット、銀行振込が主流な国もあります。
日本国内向けの決済手段だけでは海外顧客を取りこぼす可能性があるため、ターゲット国に合わせた多通貨・多決済対応を整えることがポイントです。
さらに、為替レートの変動リスクを考慮し、決済代行サービスを利用して安定した決済処理を行う企業も増えています。安全性と利便性のバランスを取りながら、現地消費者の決済行動に最も適した手段を選択することで、購入完了率(CVR)の向上が期待できます。
物流・配送は越境ECの成否を左右する重要な要素です。配送スピード、コスト、追跡性、関税対応などを考慮し、最適な配送方法を選択する必要があります。主な手段としては、「国際郵便(EMS)」「民間宅配業者」「越境EC物流代行サービス」があります。
小規模事業者の場合、まずはEMSなどの郵便ベースの配送からスタートし、販売量が増えた段階で物流代行サービスに切り替える方法が現実的です。また、配送遅延や関税トラブルを防ぐため、現地の配送事情を把握しておくことも重要です。顧客に対しては、配送日数や送料、返品条件などを明確に表示することで、信頼性の高い販売体験を提供できます。
最後に、越境ECを継続的に運営していくための事業計画と予算設計を行いましょう。初期費用に加え、運営費用を含めた収支シミュレーションを作成することが重要です。また、為替変動や関税コスト、返品リスクといった変動要素も考慮しておく必要があります。広告費やプロモーションコストは想定以上にかかることが多く、リスクヘッジとして補助金制度の活用も検討しましょう。
さらに、3〜6か月単位でKPIを設定し、定期的に成果を検証することが成功の鍵です。計画的な資金管理と目標設定が、越境ECの持続的な成長を支える基盤となります。

越境ECを始める際には、自社でECサイトを構築するか海外のECモールに出店するかという2つの大きな選択肢があります。どちらにも明確な特徴があり、自社の販売戦略・リソース・目標に合わせた選定が重要です。
自社サイトはブランドコントロールに優れる一方、集客にコストがかかります。一方、モール出店は集客力が高い反面、手数料や販売ルールの制約があります。それぞれの特性を理解し、最適な販売チャネルを選ぶことが、越境EC成功への第一歩です。
自社ECサイト型の越境ECは、自社ドメイン上にオンラインストアを構築し、海外向けに販売を行う方法です。Shopifyやfutureshop、Magentoなどの多言語・多通貨対応カートを利用すれば、専門知識がなくても比較的容易に構築できます。
自社ブランドの世界観を自由に表現でき、販売データや顧客情報を自社で保有できるのが大きな特徴です。自社でSEO・広告・SNSを活用して集客する必要はありますが、顧客との直接的な関係を築けるため、長期的なファンづくりやブランド育成に向いています。
自社ECサイトの最大のメリットは、ブランドイメージを自由に設計・発信できる点にあります。モールではデザインや販売ルールに制約がありますが、自社サイトならビジュアルやストーリーテリングを通じて世界観を統一し、顧客に強い印象を与えることが可能です。
また、顧客データを自社で管理できるため、CRMを活かしたリピーター戦略を構築しやすい点も魅力です。さらに、モール手数料が不要なため、一定の売上規模に達すれば利益率が高くなり、独自キャンペーンや価格設定の自由度も高まります。中長期的にブランド力を高めたい企業には、自社EC型が最適です。
一方で、自社ECサイトには集客の難しさという大きな課題があります。モールのような既存トラフィックがないため、SEO対策やSNS広告、インフルエンサーマーケティングなど、継続的なプロモーション施策が必要です。
海外向けの場合は、多言語対応や通貨・決済システムの整備、配送コストの設定など、初期構築・運用のハードルも高くなります。また、顧客対応も自社で行う必要があり、多言語カスタマーサポート体制の構築が求められます。短期的な販売を目的とする場合には、初期コストと運用負担がネックになる可能性があります。
海外ECモール出店型は、Amazon、eBay、Tmall Global、Shopee、Lazadaなど、既に集客力を持つプラットフォームに出店して販売する方法です。
モールは世界中の消費者が利用しており、販売開始直後から一定のアクセスが見込めるのが強みです。越境EC初心者でも比較的スムーズにスタートでき、モール側が決済・配送の仕組みを整備しているため、手間を軽減しながら販売を行えます。
コスト面やブランド戦略の自由度に制約はありますが、短期間で成果を出したい企業に適した選択肢です。
海外モールに出店する最大のメリットは、圧倒的な集客力と販売のスピード感です。特にAmazonやShopee、Lazadaなどは現地での認知度が高く、すでに多くの顧客が利用しているため、出店直後から一定の売上を見込めます。
また、モール側が決済・配送・サポート体制を整備している場合が多く、事業者は商品登録と販売に集中できます。初期費用やリスクを抑えつつ海外展開を始められる点が魅力で、まずは海外市場の反応をテストしたい企業や、現地パートナーを見つけたい事業者に最適な手法です。
海外モールでは、販売手数料や出店料が発生し、利益率が下がる傾向があります。さらに、同一モール内で多数の競合と価格競争が起こりやすく、ブランド価値を訴求しにくいのが課題です。
モール側の規約変更やアルゴリズムの影響で、販売順位が下がるリスクもあります。また、顧客データがモール運営側に管理されるため、自社でリピーター戦略を構築しにくい点もデメリットです。
中長期的なブランド育成や利益最大化を目指す場合は、自社サイトとの併用を検討するのが理想的です。

越境ECを始める際には、販売スタイルや事業規模に合った構築サービスを選ぶことが成功の鍵です。自社サイトを立ち上げてブランドを確立したいのか、海外モールでスピーディーに販売を開始したいのかによって、最適なプラットフォームは異なります。ここでは、自社で構築できるECカート型と、既存の海外モールに出店するモール型に分け、それぞれの代表的なサービスを紹介します。
どのサービスも多言語対応や多通貨決済など、越境ECに必要な機能を備えていますが、特徴や強みを理解したうえで選ぶことが重要です。
自社ECサイト型の越境EC構築サービスは、ブランド独自の世界観を発信したい企業に最適です。多言語対応・多通貨決済・海外配送設定など、グローバル販売に必要な機能をワンストップで実装できる点が魅力です。
ここでは、導入実績が豊富でサポート体制にも優れた4つの代表的なプラットフォームを紹介します。

Shopifyは、世界175か国以上で利用されているグローバルECプラットフォームです。直感的な操作でサイト構築ができるうえ、豊富なアプリを組み合わせることで、自社のビジネスモデルに合った拡張が可能です。越境ECに特化した多言語翻訳機能や150以上の通貨に対応した決済システム、主要な物流サービスとの連携など、海外販売を強力にサポートする仕組みが整っています。
また、Shopify Marketsを利用すれば、国や地域ごとに価格設定・言語・税率を自動で最適化でき、現地消費者に合わせた販売が可能です。SNSとの連携も強く、InstagramやTikTok、Facebookなどからの直接販売にも対応。デザイン性と拡張性を両立したShopifyは、初期投資を抑えながらグローバル展開を加速したい企業に最適なプラットフォームです。
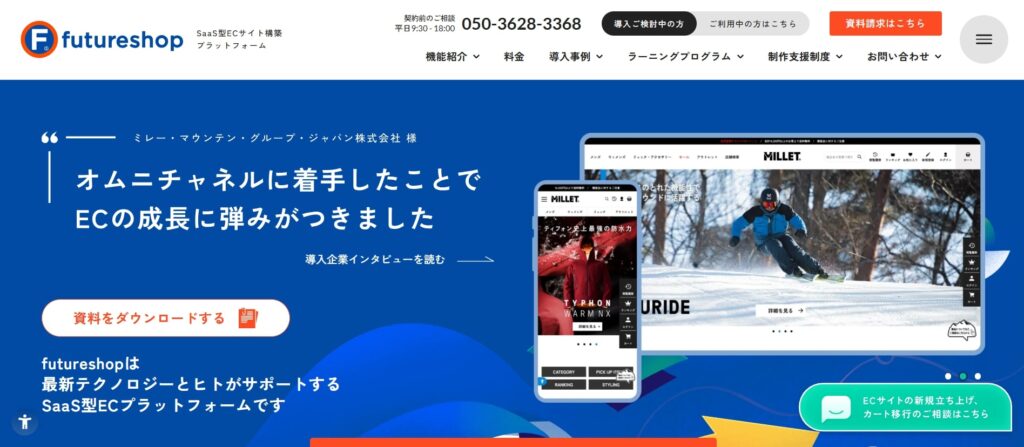
futureshop(フューチャーショップ)は、日本国内で高いシェアを誇るEC構築サービスで、海外販売にも対応できる柔軟な機能が特徴です。特に、越境EC機能「futureshop CROSS BORDER」を活用することで、多言語・多通貨設定や海外配送を簡単に設定できます。日本語管理画面の操作性が高く、英語・中国語・韓国語など主要言語への翻訳サポートも充実しています。
また、国内外のマーケティング支援に強く、広告連携・SEO最適化・顧客分析機能が標準搭載されている点も魅力です。サポート体制が整っており、EC初心者でも安心して運用を開始できます。さらに、越境ECに特化した物流・決済サービスとの連携もスムーズで、日本企業が海外進出を段階的に進めるうえで理想的な選択肢となっています。

Cafe24は、アジア市場を中心に高いシェアを持つEC構築プラットフォームで、韓国・台湾・東南アジアなどでの販売に強みがあります。無料で始められるプランがあり、初期コストを抑えて越境ECを立ち上げたい企業にも最適です。多言語・多通貨に完全対応しており、主要な決済手段を標準搭載。海外モールとの連携機能もあり、複数チャネルでの販売展開が容易です。
また、デザインテンプレートが豊富で、コーディング不要でプロフェッショナルなECサイトを構築できます。さらに、越境EC向けの物流支援・翻訳代行・マーケティングサポートなどの周辺サービスも充実。Cafe24は、アジア圏を中心にブランドを広げたい企業にとって、コストパフォーマンスとスピードを両立できるプラットフォームといえます。
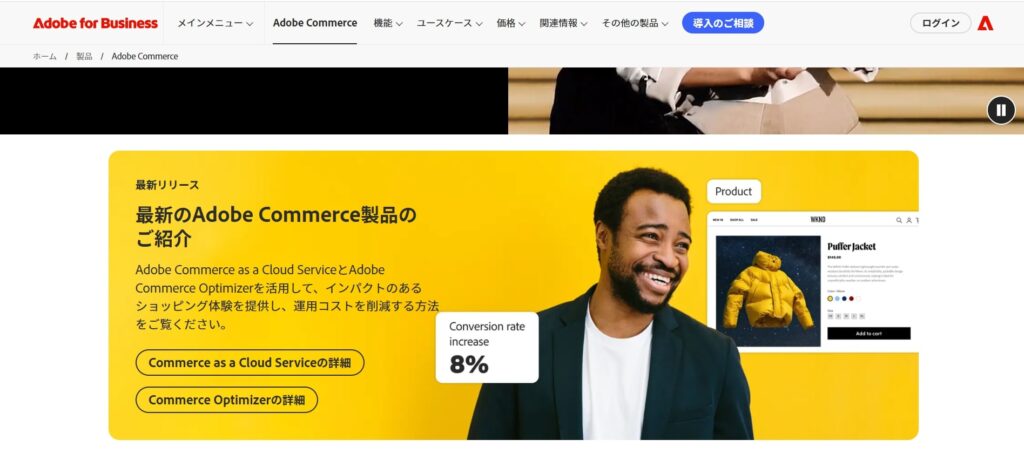
Magentoは、Adobeが提供する高機能なオープンソース型ECプラットフォームで、大規模な越境EC事業を展開したい企業に適しています。高度なカスタマイズ性とスケーラビリティを備えており、複数店舗・複数言語・複数通貨を一元管理できる点が特徴です。BtoB・BtoCの両方に対応しており、企業向けの販売や卸売にも強いシステム設計となっています。
また、SEO対策やマーケティング自動化機能、詳細なデータ分析ツールを備えており、グローバル戦略を重視する企業に最適です。ただし、導入・運用には専門的な知識や開発リソースが必要で、開発会社との連携が前提となります。
高機能ゆえに初期投資は高めですが、長期的なブランド戦略を重視する企業にとっては、最も柔軟で強力な越境EC基盤を構築できる選択肢です。
海外ECモール型は、すでに集客力のあるプラットフォームを活用し、スピーディーに海外販売を始めたい企業におすすめの手法です。出店により、モールが持つ信頼性・流通インフラ・決済機能をそのまま活用でき、初期投資を抑えながら販路を拡大できます。
AmazonやeBayなどのグローバルモールから、ShopeeやLazadaなどアジア特化型モール、さらには急成長中のTikTok Shopまで、多様なプラットフォームが存在します。ここでは、それぞれの特徴と強みを詳しく紹介します。
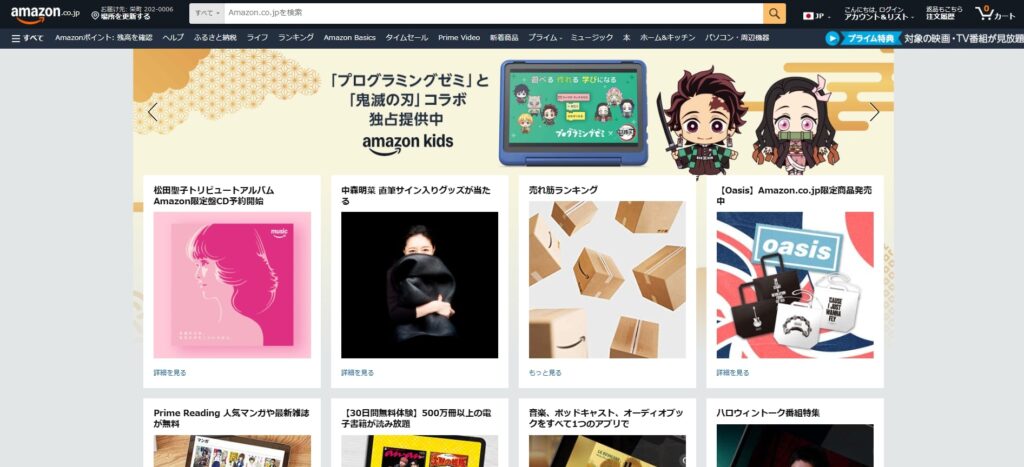
Amazonは、越境ECの代名詞ともいえる世界最大級のオンラインモールです。200以上の国と地域に販売網を持ち、「Fulfillment by Amazon(FBA)」を利用すれば、商品の保管・梱包・発送までを一括で代行できます。
これにより、在庫管理や国際配送の負担を大幅に軽減でき、海外顧客への迅速なサービス提供が可能になります。また、Amazon Global Sellingを通じて、米国・欧州・アジアなど複数のマーケットプレイスに同時出品できる点も大きな魅力です。
さらに、レビュー機能やSEO最適化が整備されているため、ブランド認知度を高めながら販売拡大が期待できます。初期費用を抑えてグローバル展開を始めたい中小企業にとって、最も安定性の高い越境ECモールと言えるでしょう。

eBayは、世界190か国以上で利用されている老舗のオンラインマーケットプレイスです。オークション形式だけでなく固定価格販売も可能で、家電・アパレル・コレクターズアイテムなど、幅広いジャンルの商品が取引されています。
特に、レア商品や中古品、日本限定商品を販売する事業者に人気があります。越境ECにおける最大の特徴は出品のしやすさとグローバルバイヤーへの直接アクセスです。英語対応の出品システムが整っており、物流パートナーeBay国際配送を利用すれば、発送や関税処理を自動化できます。
さらに、Payoneerなどの海外決済対応もスムーズ。個人事業主やスモールビジネスでも参入しやすく、試験的に海外販売を始めたい場合に最適なプラットフォームです。

Tmall Global(天猫国際)は、中国最大のEC企業アリババグループが運営する越境ECモールで、主に中国国内の富裕層・中間層向けに海外ブランド商品を販売できるプラットフォームです。日本製の化粧品・食品・ベビー用品・健康商品は特に人気が高く、日本ブランド=高品質という認識が広く浸透しています。
Tmall Globalの強みは、アリババグループが提供する物流・決済・マーケティング支援を一体化して利用できる点です。Alipayによる決済サポートや、広告配信ツール「Alimama」を活用した販促施策も可能で、ブランドの成長を長期的に支援します。
一方で、出店審査が厳しく初期費用も比較的高いため、中堅〜大手企業やブランド戦略を重視するメーカーに向いているモールです。

Shopeeは、東南アジアおよび台湾を中心に急成長しているECモールです。インドネシア・タイ・マレーシア・フィリピンなどの新興国市場で強い影響力を持ち、スマートフォンアプリを中心としたモバイルECに強みがあります。日本企業にとっては、アジア市場への越境ECを始める第一歩として最適です。
Shopeeの特徴は、出店のしやすさと手厚いサポート体制にあります。日本語対応の「Shopee Japanチーム」が存在し、商品登録や配送サポートを受けながら運用を開始できます。さらに、現地倉庫への出荷で配送を効率化する「Shopee Logistics Service」も利用可能。コストを抑えてアジア市場に参入したい企業にとって、低リスクかつ実践的なプラットフォームと言えるでしょう。

Lazada(ラザダ)は、東南アジア6か国(シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナム、インドネシア)に展開するアリババグループ傘下の大型ECモールです。高い集客力と安定した物流・決済インフラを備えており、越境ECの入口としても人気があります。
Lazadaの強みは、AIによる商品レコメンドや、現地マーケティングツール「Lazada Sponsored Discovery」を活用できる点です。これにより、ターゲット層に合わせたプロモーションを自動で最適化できます。また、「Lazada Global Shipping」を利用することで、海外配送・通関・関税対応をワンストップで実施可能。現地消費者へのリーチと物流効率を両立したい企業にとって、非常に実用的な選択肢です。

TikTok Shopは、動画プラットフォームTikTok上で直接商品を販売できる新しい形のECサービスです。エンタメ要素と購買体験を融合させたショート動画×ライブコマースにより、短期間で爆発的な拡散力を発揮します。特に若年層ユーザーへの訴求力が強く、ブランドストーリーや使用シーンを動画で伝えることで購買意欲を高められます。
また、TikTok内で完結する購入フローにより、ユーザーは離脱することなくスムーズに商品を購入可能。クリエイターやインフルエンサーとのコラボレーションを通じて、自然な形で商品の魅力を発信できるのも特徴です。まだ新興サービスながら、アジア圏を中心に利用が拡大しており、今後の越境EC戦略において注目すべきプラットフォームといえるでしょう。
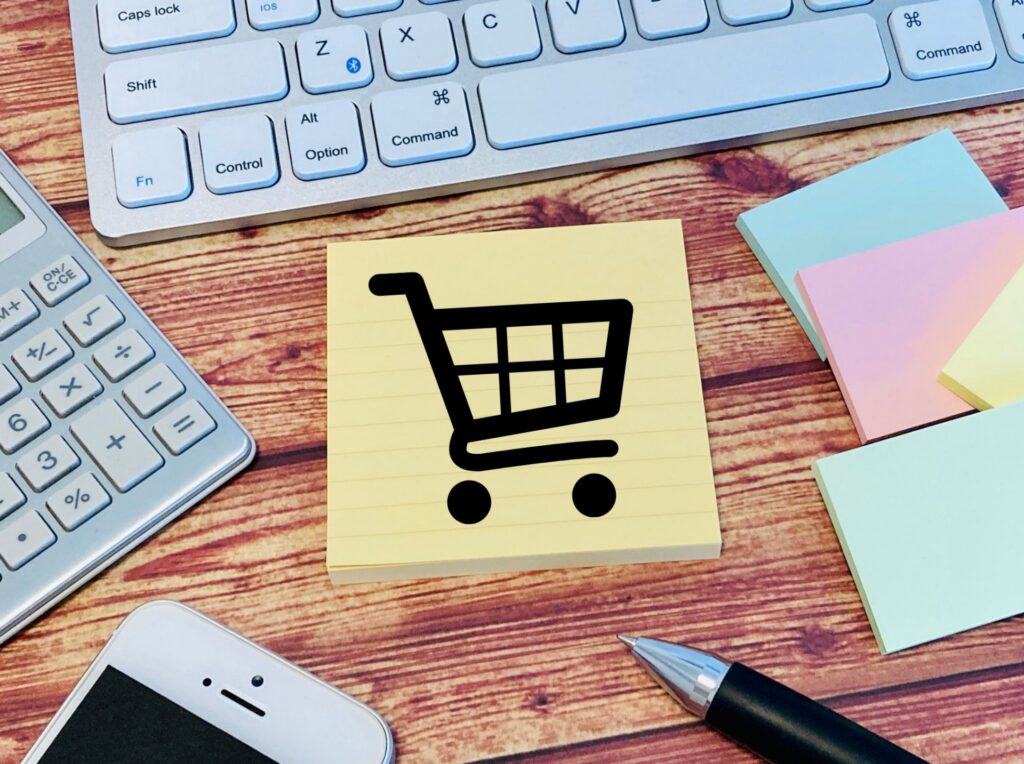
越境ECは、世界中の顧客と取引できる大きなビジネスチャンスである一方、国内ECとは異なる多くの課題も伴います。特に、言語や文化の違い、決済方法の多様性、国ごとの物流事情、そして複雑な法規制や税制への対応は、運営を左右する重要なポイントです。
これらを正しく理解し、事前に準備を整えることで、トラブルのリスクを最小限に抑え、信頼される越境ECサイトを構築できます。以下では、越境EC運営時に注意すべき4つのポイントを詳しく解説します。
越境ECにおいて、言語と文化の壁は最初に直面する大きな課題です。単に商品ページを英語に翻訳するだけでは、現地顧客に訴求することはできません。例えば、同じ英語圏でもアメリカとイギリスでは表現や単語が異なり、さらにアジア圏では消費者心理や購買動機にも文化的な違いがあります。そのため、現地の言語表現や文化的背景を踏まえたローカライズ(現地最適化)が不可欠です。また、文化の違いがマーケティング施策にも影響します。
日本では品質や安心感が重視される一方、欧米では利便性やデザイン性、アジアではステータス性や限定感が購買動機になりやすい傾向があります。SNS投稿や広告コピーも、それぞれの価値観に合わせて調整する必要があります。現地パートナーや翻訳専門家と連携し、単なる翻訳ではなく伝わる表現を目指すことが、越境EC成功の第一歩となるでしょう。
越境ECでは、国や地域ごとに異なる決済文化への対応が欠かせません。日本ではクレジットカードが主流ですが、アジアでは電子ウォレット、欧州ではデビットカードや銀行振込、アメリカではPayPalやApple Payなどが一般的です。
対応する決済手段が限られていると、購入を検討していた顧客が離脱してしまうケースも少なくありません。そのため、ターゲット国の主要決済手段を調査し、複数の決済方法を導入することが重要です。また、通貨換算や為替手数料の扱いも明確にしておく必要があります。
さらに、海外取引では不正利用リスクも高まるため、セキュリティ対策を強化した決済代行サービスの利用がおすすめです。ユーザーが安心して支払える環境を整えることで、購入率の向上やリピーター獲得につながります。越境ECの決済は多様性と信頼性が鍵となる要素です。
越境ECでは、物流と配送の最適化が顧客満足度を左右します。海外配送には、国際郵便や民間物流会社、または越境EC専門の物流代行サービスを利用する方法があります。コスト、配送スピード、追跡可否、関税処理などを考慮して選択する必要があります。
特に、配送にかかる日数や送料の高さは購入意欲に直結します。顧客に対しては、配送期間・関税・返品ポリシーを明確に提示し、トラブルを防ぐことが大切です。また、複数国で販売する場合は、現地倉庫を活用して在庫を分散管理すると、配送コスト削減とスピード改善が可能です。
さらに、梱包品質や破損対策も重要です。日本製品は品質への期待が高い分、商品到着時の印象がブランド評価に直結します。スムーズで安全な配送を実現するためには、信頼できる物流パートナーとの連携が不可欠です。
越境ECを行う際には、国や地域ごとに異なる法規制や税制への対応が必要です。特に注意すべきは、輸入関税、消費税、製品安全基準、商標・知的財産権、個人情報保護法といった分野です。これらを正しく理解せずに販売を進めると、罰金・販売停止・返品などのトラブルに発展するリスクがあります。
例えば、EUではCEマークやREACH規制など、製品の安全性や化学物質に関する認証が求められる場合があります。また、アメリカではFDAの認可が必要な商品カテゴリも存在します。さらに、越境ECで発生する売上に対して課税される輸入消費税や源泉税などの申告義務にも注意が必要です。
法務・税務の知識を自社でカバーするのが難しい場合は、専門のコンサルティング会社や税理士と連携し、法令遵守体制を整えることが安全な運営への近道です。信頼性のある運営は、長期的な海外展開の基盤を支えます。

越境ECを軌道に乗せるためには、単に商品を海外へ出品するだけでは不十分です。現地の消費者心理や購買行動を理解し、最適な販売戦略を構築することが求められます。また、決済や物流、カスタマーサポートなどの運用面も、現地の事情に合わせて整える必要があります。
ここでは、越境ECを長期的に成功へ導くための5つのポイントを紹介します。これらを意識することで、海外市場での信頼獲得とリピーターの増加を実現できます。
越境EC成功の基本は、現地の消費者ニーズを的確に捉えることです。日本で人気の商品でも、海外では文化や嗜好の違いから受け入れられない場合があります。例えば、サイズ・色味・パッケージデザイン・使用方法など、各国の価値観や生活習慣に合わせた調整が重要です。
また、マーケティング戦略も現地化が鍵です。SNS広告やレビューサイト、インフルエンサーなど、現地で主流のメディアを活用して認知を広げることが効果的です。例えば、アジア圏ではInstagramやTikTokが強く、欧米ではFacebook広告やYouTubeが効果を発揮します。単に翻訳した広告を配信するのではなく、現地ユーザーが共感するストーリーや価値を訴求することが、購買意欲の向上につながります。
越境ECでは、国や地域によって一般的な決済手段が異なるため、複数の支払い方法に対応することが欠かせません。例えば、中国ではAlipayやWeChat Pay、東南アジアではGrabPayやShopee Pay、欧米ではPayPalやApple Payが主流です。
これらを導入することで、顧客が安心して購入できる環境を整えられます。また、通貨や税金計算の自動換算機能を備えた決済システムを採用することで、顧客の不安を軽減し、離脱率を下げることができます。さらに、チャージバックなどのトラブルに備え、セキュリティ認証が高い決済代行サービスを選ぶことも重要です。
多様な決済手段を整えることは、越境ECのコンバージョン率向上に直結します。
SNSは、越境ECにおいて現地の顧客との接点を生む最も効果的なツールです。Instagram、TikTok、Facebook、YouTubeなどのプラットフォームを活用することで、低コストでブランドの認知を広げることができます。特に、動画コンテンツやライブ配信は商品の魅力をリアルに伝えられるため、購入への心理的ハードルを下げる効果があります。
また、現地のインフルエンサーとのコラボレーションも有効です。信頼性の高い第三者が商品を紹介することで、ローカルユーザーの購買意欲を刺激できます。さらに、口コミやレビューを促進する施策を取り入れることで、自然なブランド拡散が可能です。SNSマーケティングを通じて共感や信頼を築くことが、越境ECでリピーターを増やす鍵となります。
海外販売では、購入後のサポート体制がブランド評価に直結します。問い合わせ対応が遅れたり、言語が通じなかったりすると、トラブルやクレームに発展しかねません。そのため、多言語対応のカスタマーサポートを整備することが非常に重要です。
英語・中国語・スペイン語など、主要ターゲット地域の言語に対応したチャットやメールサポートを導入し、迅速かつ丁寧に対応できる仕組みを作りましょう。AIチャットボットを活用することで、24時間対応も可能になります。
また、FAQや返品ポリシーを明確に提示することも、トラブル防止につながります。顧客に安心感を与えるサポート体制を整えることで、信頼関係を構築し、リピート購入や高評価レビューの獲得につながります。
越境ECの運営には、物流・決済・マーケティング・法務など、多岐にわたる専門知識が必要です。すべてを自社で対応するのは難しいため、信頼できる外部パートナーを見つけることが成功の近道です。例えば、海外販売支援に強いコンサル会社、現地物流代行業者、翻訳・マーケティング専門企業などと連携することで、効率的に事業を拡大できます。
パートナー選定の際は、過去の支援実績や対応国、サポート体制を確認し、自社の課題に合う企業を選ぶことが重要です。単なる委託関係ではなく、共に成長を目指せる協業関係を築くことで、越境ECの長期的な成功につながります。信頼できるパートナーとの連携は、海外展開のリスクを最小化し、安定した運営を実現するための基盤です。

越境ECは、日本にいながら世界中の顧客に商品を届けられる大きなチャンスです。しかし、成功のためには、入念な準備と現地市場への深い理解が欠かせません。言語・文化・決済・物流などの課題を一つずつクリアし、現地ニーズに合った商品やマーケティングを展開することが鍵です。
信頼できるパートナーと連携し、長期的な視点で取り組むことで、安定した海外売上を築けるでしょう。海外進出支援やEC構築の相談なら、AXIA Marketingがトータルにサポートします。
参考文献
Copy Link





