
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.10.29


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
グローバル市場の拡大や国内需要の減少を背景に、海外展開を目指す日本企業が増加しています。しかし、現地の商習慣や法制度、販路構築、人材確保など、海外進出には多くのハードルが存在します。そこで注目されているのが、海外展開を専門的にサポートする支援サービスです。
戦略立案から現地法人設立、マーケティングや補助金活用まで、各フェーズに応じた支援を受けることで、リスクを最小限に抑えながら海外進出を実現できます。本記事では、コンサル・公的機関・補助金などを網羅的に紹介し、自社に最適な支援先を見つけるためのポイントを徹底解説します。

海外展開支援とは、企業が海外市場への進出や事業拡大を行う際に専門的な知見や実務サポートを提供するサービスのことです。現地調査や戦略立案、パートナー企業の選定、法人設立、販路開拓、マーケティング、資金調達など、支援内容は多岐にわたります。
特に中小企業の場合、言語・法制度・商習慣の違いが大きな壁となるため、外部の専門機関やコンサルタントのサポートが欠かせません。また、国や自治体、JETROなどの公的機関も補助金や助成金の交付、専門家派遣、マッチング支援といった形で企業の海外展開を後押ししています。
自社の目的や課題に応じて、こうした支援サービスを活用することで、リスクを抑えながら効率的に海外進出を進めることが可能になります。

海外進出を成功させるためには、企業の成長段階や目的に合わせて最適な支援を選ぶことが重要です。海外展開支援サービスは大きく分けて、「民間企業によるコンサルティング型の支援」「JETROや中小機構などの公的機関による支援」「補助金・助成金など資金面での支援」の3つに分類されます。
それぞれ支援範囲や得意分野が異なるため、自社の課題に合わせて活用することがポイントです。以下では、それぞれの特徴とメリットを詳しく解説します。
民間企業による海外展開支援は、コンサルティング会社やマーケティング企業、貿易・物流の専門業者などが提供するサービスです。主な支援内容は、市場調査、進出戦略の立案、現地パートナーの紹介、法人設立代行、デジタルマーケティング支援など多岐にわたります。
特に、近年は現地のSNS広告運用やECサイト構築など、デジタル領域に強みを持つ支援企業が増えています。民間コンサルの最大のメリットは、実務に直結する具体的なサポートを受けられる点です。
現地文化や商慣習を熟知した担当者が伴走することで、スピーディかつ実践的な海外進出が可能になります。一方で、費用は数十万円〜数百万円規模になるケースも多いため、支援内容の範囲と費用対効果を明確に確認しておくことが重要です。
公的機関による海外展開支援は、費用負担を抑えつつ、信頼性の高いサポートを受けられる点が特徴です。代表的な機関には、日本貿易振興機構(JETRO)、中小企業基盤整備機構(中小機構)、地方自治体、商工会議所などがあります。これらの機関は、現地市場に関するデータ提供、現地ビジネスマッチング、展示会・商談会の開催、専門家による個別相談などを実施しています。
JETROは、世界70か国以上に海外事務所を持ち、現地の最新情報を提供するほか、進出後のフォローアップ支援も行っています。公的支援のメリットは信頼性とコストパフォーマンスの高さですが、申請書類や審査に時間がかかる点には注意が必要です。海外展開の初期段階や情報収集フェーズでは、公的支援を積極的に活用するのが効果的です。
海外展開を行う際にネックとなるのが、初期投資やマーケティング費用などの資金負担です。こうした課題を解決するために、国や自治体は多様な補助金・助成金制度を設けています。
代表的なものとして、「ものづくり補助金<グローバル展開枠>」「中小企業等海外展開支援事業費補助金(特許庁)」「東京都市場開拓助成事業」などがあります。これらの制度では、海外見本市出展費用、現地法人設立費、翻訳・広告制作費、知的財産の海外出願費用などが補助対象です。
補助率は1/2〜2/3程度が一般的で、採択されれば数百万円規模の支援を受けられることもあります。ただし、申請には事業計画書の作成や報告義務が伴うため、コンサルタントや行政書士のサポートを受けると安心です。資金面の支援を上手に活用することで、海外進出のリスクを大幅に軽減できます。

海外展開支援サービスは数多く存在しますが、どの支援先を選ぶかによって成果は大きく変わります。特に、初めて海外進出を検討する企業にとっては、戦略の方向性やコストバランス、担当者の対応力が成功の鍵となります。最適な支援先を見つけるには、単に費用や知名度で判断するのではなく、「自社の目的・課題」と「支援内容・実績・体制」の整合性を重視することが重要です。
ここでは、海外展開支援サービスを選ぶ際に押さえておくべき5つのポイントを解説します。
最初に明確にすべきなのは、「なぜ海外進出をするのか」「自社のどんな課題を解決したいのか」という目的です。例えば、販路拡大を目的とするのか、生産拠点の分散化を狙うのかによって、求める支援内容は大きく異なります。
目的が曖昧なまま進めてしまうと、コンサルタントや支援機関との方向性がずれ、効果的なサポートを受けられないリスクがあります。そのため、進出目的に加えて「現地調査が不足している」「販路開拓のノウハウがない」「補助金の申請が難しい」など、自社の課題を整理することが重要です。目的と課題を明確化することで、最適な支援タイプ(民間・公的・資金支援など)を選択しやすくなります。
海外展開支援と一口にいっても、提供範囲は企業によってさまざまです。市場調査や戦略立案までを行う会社もあれば、法人設立・税務・人材採用などの実務支援を得意とするコンサルもあります。依頼前には、どの工程まで対応してもらえるのかを明確に確認することが大切です。
また、専門性の高さも重要な判断基準です。例えば、製造業の海外進出支援に強い企業、デジタルマーケティング支援に特化した企業など、自社の業種や業態に合った専門知識を持つ支援先を選ぶことで、実行力の高いサポートが受けられます。
表面的な提案だけでなく、現地ネットワークや実績に裏づけされた専門性を持つかどうかを見極めましょう。
海外展開支援サービスの費用は、内容や支援範囲によって大きく異なります。例えば、市場調査や戦略立案のみであれば数十万円程度、法人設立やマーケティング支援を含む総合支援となると100万円以上かかることもあります。費用が高ければ良い結果が得られるとは限らず、コストパフォーマンスを重視することが大切です。
契約前には、初期費用・月額費用・成果報酬の有無など、料金体系を明確に確認しましょう。また、補助金・助成金を活用できる場合は、費用負担を抑えつつ高品質な支援を受けることも可能です。自社の予算と支援内容を照らし合わせ、投資対効果の高い支援先を選ぶことが成功への近道です。
海外展開の成否は、支援先の経験値に大きく左右されます。支援実績が豊富な企業は、過去の成功事例や失敗事例から得たノウハウをもとに、より精度の高い提案を行えます。また、支援実績がある国・地域を確認することも重要です。
東南アジアに強い企業もあれば、欧米や中東市場に特化した支援会社もあります。さらに、現地の法制度や商習慣を熟知しているかどうかもチェックポイントです。具体的な実績として「進出企業の数」「支援後の成果」「顧客の業種」などを確認し、自社の業態や展開先にマッチする支援会社を選びましょう。
信頼性の高い支援先を選ぶことで、現地でのトラブルを防ぎ、スムーズな展開が可能になります。
海外展開は短期的に完結するプロジェクトではなく、長期的なパートナーシップが求められる取り組みです。そのため、支援先のサポート体制や担当者との相性は極めて重要です。対応のスピード、コミュニケーションの取りやすさ、課題解決への姿勢などをチェックしましょう。
特に、海外とのやり取りでは時差や文化の違いから意思疎通に課題が生じやすいため、丁寧かつ柔軟な対応ができる担当者が理想です。また、契約後のアフターサポートや進捗報告の頻度なども確認しておくと安心です。単なる委託先ではなく、自社の成長を共に目指せるパートナーとして信頼できるかどうかを見極めることが、海外展開成功の鍵となります。

海外進出を成功させるには、現地の市場特性を理解し、法制度や商習慣に対応した戦略的な支援が欠かせません。ここでは、民間コンサルティング企業・公的機関・補助金制度の3カテゴリーに分けて、信頼性の高い海外展開支援サービスを厳選して紹介します。
企業規模や目的、進出国によって最適な支援先は異なります。自社の課題に合わせて、戦略立案から実務サポート、資金支援まで一貫して利用できるサービスを選ぶことで、海外事業を確実に成功へ導けます。
民間のコンサルティング企業による支援は、海外展開の初期段階から実行フェーズまでを一貫してサポートできる点が魅力です。市場調査、現地法人設立、デジタルマーケティング、EC構築、現地採用など、企業の目的に応じたオーダーメイド型の支援が受けられます。
特に海外進出ではスピード感と実行力が求められるため、現地ネットワークを持ち、リアルタイムで市場変化に対応できるコンサルの存在は重要です。ここでは、グローバル戦略に強い実績を持つ7社を紹介します。
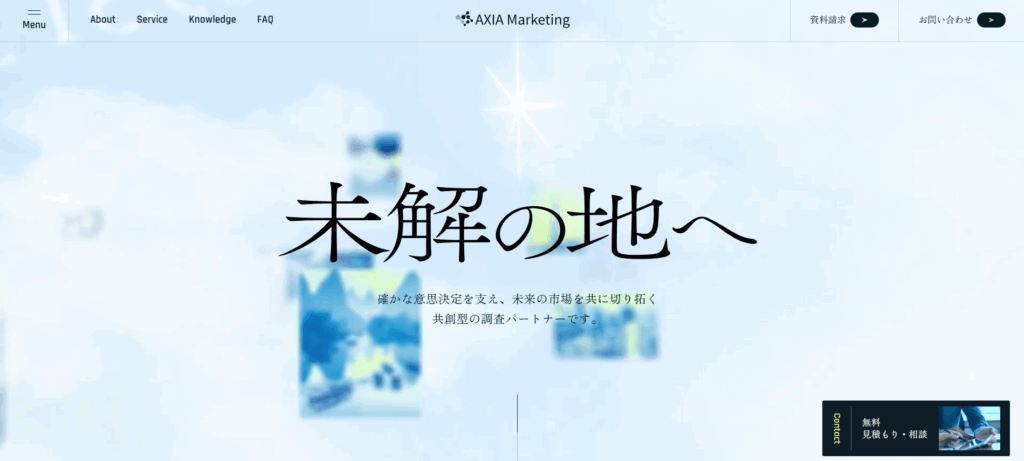
AXIA Marketingは、海外進出を目指す企業に対し、戦略設計から現地展開・集客までをワンストップで支援するコンサルティング会社です。ASEAN地域(タイ・ベトナム・マレーシアなど)への進出支援に強みを持ち、市場調査から会社設立、現地マーケティング施策まで一気通貫でサポートします。
AXIA Marketingの特長は、単なるコンサルにとどまらず、デジタル広告やSNS戦略など実務に直結するマーケティング支援も提供している点です。さらに、現地企業との連携や補助金申請サポートにも対応しており、中小企業でもリスクを抑えて海外進出を実現可能です。成功率の高い戦略設計力と実行支援が、AXIA Marketingの最大の強みです。

山田コンサルティンググループは、国内外に拠点を持つ総合コンサルティングファームで、海外進出の戦略立案から現地法人運営まで総合支援を行っています。財務・法務・人事・M&Aなど、企業経営に関わる幅広い分野をワンストップで対応可能です。
山田コンサルティンググループはアジア、欧州、北米など主要国に現地拠点を展開しており、現地の法制度やビジネス慣習に精通した専門家が実務レベルでサポート。進出前のリスク分析から撤退戦略の立案まで、中長期的な海外経営戦略のパートナーとして企業を支援します。
海外M&Aや事業承継を見据えた進出支援において、同社の実績と信頼性は業界でも高く評価されています。

インフォキュービック・ジャパンは、海外向けデジタルマーケティングの専門企業として知られ、Web広告・SEO・SNS運用などを通じて現地でのブランド浸透を支援しています。グローバルに展開する多言語チームが在籍し、各国の文化や検索トレンドを踏まえた戦略設計が可能です。
特にGoogle・Meta・LinkedInなどの広告運用に強みを持ち、BtoB・BtoC問わず幅広い業界の企業を支援。日本企業の海外展開において、現地ニーズを的確に捉えたデータドリブンなマーケティング戦略を提供しています。
また、海外向けサイト制作やコンテンツ翻訳まで一貫対応できる点も魅力です。デジタル施策で海外販路を拡大したい企業に最適なパートナーです。

クリスクは、グローバルBtoBマーケティングとブランディング支援に強みを持つコンサルティング会社です。企業の海外市場進出において、ブランド戦略の構築からリード獲得まで、マーケティング全体を包括的に支援します。
特に製造業やIT業界など、専門性の高い企業の支援実績が豊富で、海外展示会やWebマーケティングの戦略立案にも対応。海外顧客との関係構築を重視し、「戦略×クリエイティブ×テクノロジー」を融合させたアプローチで成果を上げています。
単なる広告運用ではなく、事業戦略全体を見据えたグローバル展開を実現したい企業に最適な支援企業です。

カーツメディアワークスは、広報・PRの視点から海外展開を支援するコンサルティング会社です。海外市場でのブランド認知向上、メディア露出、SNS発信を得意としています。カーツメディアワークスの強みは、国内外での豊富なメディアネットワークを活かした戦略的PR支援です。
日本企業が海外市場で信頼を獲得するためには、単なる広告ではなくブランドストーリーの発信が不可欠。カーツメディアワークスは、現地メディアとのリレーション構築やプレスイベント企画を通じ、自然な形でブランド浸透を実現します。
海外でのブランド立ち上げやリブランディングを目指す企業におすすめです。
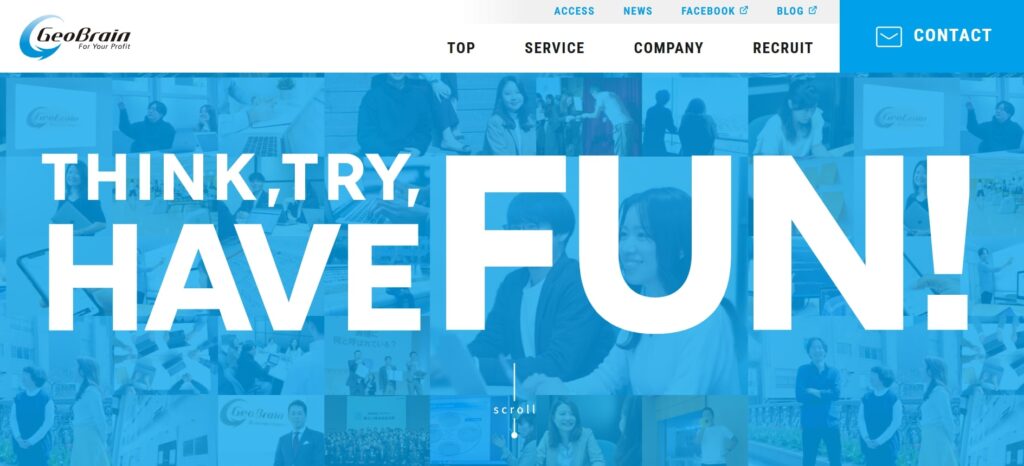
ジオプレインは、データ分析とAIを活用した海外マーケティング支援を提供する企業です。独自のデータプラットフォームを用いて、現地市場の消費者行動や競合動向を可視化し、最適な戦略立案を行います。
また、SNS広告や検索広告の運用だけでなく、EC市場のデータ収集や商品リサーチにも対応しており、精度の高い海外販路開拓を実現。特にアジア・欧米市場に強みを持ち、現地消費者のデータをもとにROIを最大化する提案が可能です。
マーケティングに科学的アプローチを求める企業や、海外EC展開を本格化させたい企業に最適なパートナーです。
海外進出を検討する企業にとって、公的機関の支援は費用を抑えつつ信頼性の高い情報や専門アドバイスを得られる点が大きな魅力です。各機関は、進出前の市場調査やパートナー紹介、現地展開後の販路開拓支援など、幅広いサポートを行っています。初めて海外展開に挑戦する中小企業にとっては、制度面・資金面・情報面で心強い味方となる存在です。
ここでは、代表的な4つの公的支援機関を紹介します。どの機関も無料または低コストで利用できるため、まずは相談先として検討する価値があります。

JETRO(ジェトロ)は、経済産業省所管の公的機関で、日本企業の海外展開を総合的に支援する代表的な組織です。世界約70か国・200以上の都市に事務所を持ち、現地の経済動向や法制度、商習慣に関する一次情報を提供しています。
主な支援内容は、現地市場調査、ビジネスマッチング、展示会・商談会の開催、輸出入関連セミナーの実施など。さらに、現地企業とのパートナーシップ構築や販路開拓のサポートも行っています。中小企業向けの無料相談や、海外進出に関するオンライン支援サービス「J-messe」「TTPP」なども充実しており、海外展開を初めて検討する企業にとって最初の相談先として最適です。
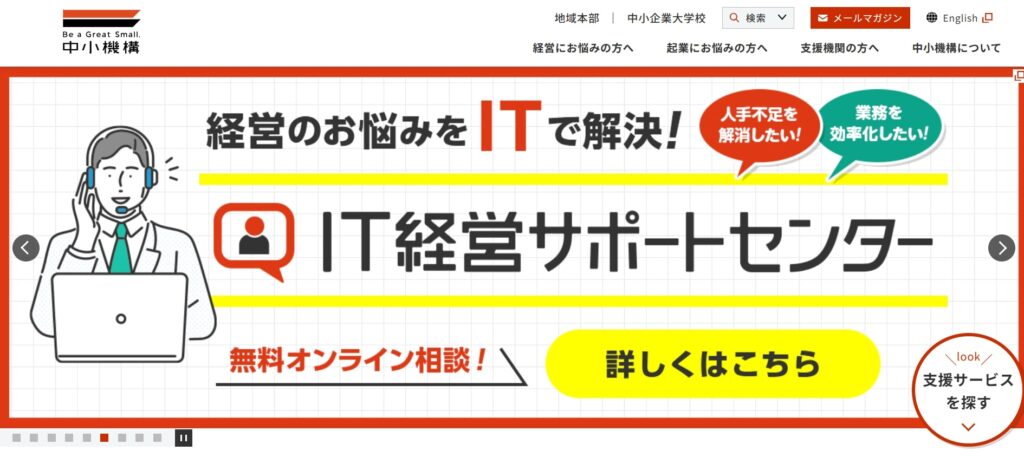
中小機構は、中小企業の経営支援を目的とした独立行政法人で、中小企業の海外展開を中長期的に支援する体制を整えています。海外展開に関する課題解決を目的に、専門家による個別相談や海外ビジネスに関するオンライン講座、セミナーなどを実施しています。
また、JETROと連携して現地市場調査やマッチング支援も行っており、補助金や助成金など資金面でのサポートも提供。さらに、海外ビジネス経験のある中小企業診断士や貿易実務の専門家を派遣し、実務レベルでの課題解決をサポートしています。
公的機関の中でも中小企業に特化している点が特徴で、進出準備から現地展開・撤退戦略まで一貫して伴走する姿勢が評価されています。

JICA(ジャイカ)は、政府開発援助を通じて発展途上国の支援を行う公的機関ですが、民間企業の海外展開支援にも力を入れています。特に、開発途上国での社会課題解決型ビジネスを推進する日本企業に対し、調査費用や実証事業の資金支援を行っています。
「中小企業・SDGsビジネス支援事業」では、事業化可能性調査(FS)や実証事業にかかる費用の一部を補助。さらに、現地政府・企業との調整支援や、JICA現地事務所を通じたネットワーク構築もサポートします。単なるビジネス進出ではなく、社会的インパクトを伴う国際展開を目指す企業にとって、JICAは強力な支援機関と言えます。

商工会議所は、全国各地の地域企業を支援する団体として、地域から海外へ挑戦する中小企業を後押しする役割を担っています。地域ごとの経済特性を踏まえ、海外展開に関する個別相談や専門セミナー、輸出実務講習会などを実施。特に、初めて海外取引を行う企業に向けて、貿易実務や契約書の作成支援など、実務的なサポートが充実しています。
さらに、JETROや中小機構、自治体と連携した海外展示会・商談会の参加支援も行っており、地元企業の国際化を包括的にサポート。会員であれば低コストで利用できる制度が多く、地域密着型の海外展開支援を受けたい企業に最適な窓口です。地元ネットワークと公的支援を融合した地域発のグローバル展開を目指す企業におすすめです。
海外展開には、現地調査や法人設立、マーケティング、物流、人材確保など多くの費用が発生します。そのため、補助金や助成金を活用して初期投資の負担を軽減することが成功の鍵となります。日本では、国・自治体・公的機関が海外展開を支援する複数の資金制度を設けており、申請次第で数百万円規模の補助を受けることも可能です。
ここでは、全国レベルから東京都の地域支援まで、代表的な4つの補助制度を紹介します。上手に活用することで、限られた資金でも海外進出を現実的に進められます。

全国中小企業団体中央会が運営する「ものづくり補助金<グローバル枠>」は、海外展開を目的とした設備投資や新製品開発を支援する制度です。特に、海外市場向け製品の開発や海外拠点での生産体制構築を行う中小企業が対象となります。補助上限額は1,000万円程度(※年度により変動あり)で、試作・開発・現地調査・設備導入費用などが対象経費に含まれます。
通常のものづくり補助金に比べて、輸出促進や海外販路開拓に特化している点が特徴です。また、申請時には事業計画書の提出が求められるため、経営戦略を明確化する良い機会にもなります。技術力を海外市場に展開したい製造業に最適な支援制度です。

東京都の海外展開支援事業は、都内中小企業の海外進出を支援するための包括的な助成制度です。海外展示会への出展費用、現地調査、通訳費、プロモーション活動費など、実務的な経費が幅広く対象になります。助成上限額は原則300万円(助成率1/2以内)で、海外ビジネスの初期段階におけるリスク軽減を目的としています。
また、対象となる企業は東京都内に本社を置く中小企業で、申請には事業計画書や経営基盤の証明が必要です。さらに、専門家による個別相談やマッチング支援も併用でき、中小企業が一歩を踏み出しやすい実践的な制度として高い評価を得ています。海外での販路開拓や新市場調査を検討している企業におすすめです。

東京都中小企業振興公社が実施する市場開拓助成事業は、海外展示会・商談会への出展支援や現地販売促進活動を助成する制度です。BtoB企業や製造業、スタートアップ企業の利用が多く、海外バイヤーとの商談を通じて販路を拡大する支援を行っています。
助成金額は上限150万円(助成率1/2以内)が目安で、渡航費・展示会出展料・翻訳・通訳費・広告宣伝費などが対象。選定企業には公社職員が伴走支援を行い、現地での成果報告までフォローしてくれます。初めて海外展示会に出たい企業や海外販路を試験的に拡大したい中小企業に最適です。東京発で世界市場に挑戦する企業を後押しする、実用性の高い助成制度と言えるでしょう。

特許庁が実施する中小企業等海外展開支援事業費補助金は、海外での知的財産保護を目的とした支援制度です。海外展開を進める中で、模倣品被害や商標トラブルを防ぐための知財戦略を強化することを目的としています。
補助対象となるのは、商標・特許・意匠などの海外出願費用や調査費用で、補助率は2/3以内、上限額は原則300万円程度。特許庁が認定した支援機関を通じて申請・報告を行う仕組みとなっています。中小企業等海外展開支援事業費補助金を活用することで、知財リスクを抑えながら安全に海外展開を進めることが可能です。
特に、ブランドを海外に展開する企業や製品技術を守りたいメーカーにとって不可欠な制度と言えます。

海外展開支援サービスや補助金を活用しても、企業側の取り組み姿勢によって成果は大きく変わります。支援先の専門家や機関はあくまで伴走者であり、実際に成功をつかむためには企業自身の主体性と中長期的な視点が欠かせません。
支援を最大限に活かすには、単に任せるのではなく、自社の戦略を明確にし、社内体制を整備しながら継続的に改善を重ねることが重要です。ここでは、海外展開を成功に導くために意識すべき3つのポイントを紹介します。
海外展開支援を受ける際、多くの企業が陥りがちなのが支援先への丸投げです。確かに、コンサルティング会社や公的機関は豊富なノウハウを持っていますが、最終的に成果を出すのは自社の戦略と意思決定です。支援先の提案を受け身で受け取るだけでは、自社に最適化された施策にはつながりにくいでしょう。
重要なのは、支援先との関係を委託ではなくパートナーシップと捉えることです。自社が持つ強み・課題・現場の情報を積極的に共有し、意見交換を重ねることで、より効果的な施策を共創できます。
また、定期的な進捗確認や成果の検証を行い、改善サイクルを自ら主導する姿勢が成果を左右します。支援を活用する側の主体性が、海外展開成功の最大の鍵です。
どれほど優れた支援を受けても、社内に海外展開を推進できる体制がなければ、プロジェクトは長続きしません。海外事業は部門をまたぐ取り組みであり、営業・経理・人事・マーケティングなど各部署の協力が欠かせません。
そのため、専任チームの設置や、海外担当責任者を明確にすることが重要です。さらに、社内で情報共有が円滑に行われる仕組みを整えることで、現地の課題や進捗をタイムリーに把握できます。言語や時差の壁を越えるために、オンラインツールの活用や定例ミーティングの導入も有効です。
また、グローバル人材の育成も長期的な投資として考える必要があります。支援先に頼るだけでなく、自社内にノウハウを蓄積することが、継続的な成長の土台となります。
海外展開は短期間で成果が出るものではなく、3〜5年単位の中長期的な視点で取り組む必要があります。特に現地市場では、文化・商習慣・景気動向の違いによって、想定通りに事業が進まないことも多いため、柔軟な戦略修正と継続的な投資が欠かせません。
短期的な売上だけを追うのではなく、ブランド浸透・人材育成・現地パートナーシップなど、将来の安定基盤を築くことを重視すべきです。
そのためには、支援制度を活用しつつ、成果を段階的に検証しながらPDCAを回すことが大切です。また、為替変動や政治リスクへの備えも含め、リスクマネジメントを計画に組み込む必要があります。海外展開は“マラソン”であり、短距離走ではないという認識が成功の第一歩です。

海外進出を成功させるには、明確な戦略と信頼できるパートナーの存在が欠かせません。AXIA Marketingは、市場調査から現地法人設立、デジタルマーケティングまでを一貫支援する海外展開コンサルティング企業です。
ASEANを中心に豊富な実績を持ち、現地の商習慣や規制にも精通しているため、初めての海外進出でも安心して任せられます。補助金活用や販路拡大の相談にも柔軟に対応し、企業ごとの課題に最適なソリューションを提供。中小企業から大手まで、海外展開を成功に導く実行支援力がAXIA Marketingの最大の強みです。海外進出を検討している企業は、まず無料相談から一歩を踏み出してみましょう。
参考文献
Copy Link





