
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.10.29


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
インドは人口14億人を超える世界最大の市場の一つであり、経済成長率も高水準を維持していることから、日本企業にとって有望な投資先として注目を集めています。製造業・IT・インフラなど幅広い分野で外資導入が進む一方で、会社設立に際しては独自の制度や行政手続きへの理解が欠かせません。
本記事では、インドで会社を設立するための基本的な流れを10ステップに分けてわかりやすく解説します。手続きのポイントや必要書類、費用相場、成功のための注意点まで、インド進出を検討する企業必見の内容です。

インドは人口14億超、経済成長を続ける巨大市場であり、デジタル化・産業高度化政策が追い風となっています。インフラ整備や製造拠点誘致政策が進むなか、日本企業にとって製造と内需の両面を狙える拠点としての魅力が強まっています。
また、既に多くの日本企業が進出しており、現地でのネットワーク・ノウハウ蓄積が進んでいる点も安心材料。ここでは、インドで会社を設立するメリットと、近年の日本企業動向を見ていきましょう。
インドで会社を設立する最大の魅力は、巨大な人材資源と成長する消費市場を同時に取り込める点です。インドは若年人口が多く、英語に通じた技術力のある人材が豊富であり、IT・エンジニアリング・BPO分野などで世界的に競争力を持っています。
こうした人材を活用することで、コストを抑えつつ高度な開発・運営体制を構築できます。さらに、政府が推進する「Make in India」「Digital India」などの政策や、特別経済区(SEZ)への優遇措置、税制インセンティブ、インフラ整備強化なども外国企業にとって追い風となっています。
これらの政策により、物流コストや許認可手続きの負荷軽減などが進んでおり、ビジネス環境自体が年々改善されてきています。また、インドは地理的にもアジア・中東・アフリカ市場へのハブとして戦略的な位置にあり、インドを起点に広域展開を仕掛けやすい強みを持っているのです。こうした「人的資源」「制度的支援」「戦略立地」の三つが揃う点が、インド設立の大きなメリットと言えます。
日本企業のインド進出は着実に広がっており、JETROおよび在インド日本大使館のデータによれば、日本企業の現地登録数は2022年時点で1,400社ほどとされています。製造業がその半数を占め、残りは卸売、小売、サービス業など多様な業種に展開しています。
近年では、製造業だけでなく、デジタル分野・R&D拠点・グローバルサービス拠点としての利用も増えています。インドの技術力・コスト優位性に注目し、日本企業がソフトウェア開発やデータセンター、バックオフィス機能を現地化するケースも多く見られます。
一方で、日本企業が進出する際には、許認可の遅延、土地取得問題、税制・労働規制の複雑性といった課題も報告されており、制度理解と現地パートナーネットワークの有無が成功を左右する要因となっています。こうした実情を踏まえつつ、日本企業はインドを次の成長拠点として積極的に活用しつつある段階と言えるでしょう。

インドで事業を展開する際には、事業目的や投資規模、活動範囲に応じて最適な設立形態を選ぶことが重要です。主な形態としては、現地法人(子会社)・駐在員事務所・支店・プロジェクト・オフィスの4種類があります。それぞれに設立要件や活動範囲、税務上の扱いが異なるため、事前に十分な比較・検討が必要です。
特に外資規制が適用される業種では、許認可の有無や出資比率制限が影響することもあるため、進出目的に応じた最適なスキーム設計が成功の鍵となります。ここでは、インドでの会社設立4つの形態について解説します。
インドで最も一般的な設立形態が現地法人です。独立した法人格を持ち、インド国内外で自由に事業活動を行うことが可能です。外資系企業が設立する場合は、外資持株会社として扱われ、最低2名の取締役と株主が必要とされます。そのうち1名はインド居住者でなければなりません。
外資規制のない業種であれば、100%外資による出資も認められます。設立手続きは電子化が進んでおり、デジタル署名証明書(DSC)や取締役識別番号(DIN)を取得した上で、会社法に基づき登記申請を行います。現地法人のメリットは、契約・資産保有・雇用などの活動を自社名義で行える点で、長期的な事業拠点として信頼性が高いことです。
一方で、税務・会計・監査義務などのコンプライアンスが厳格であるため、設立後の管理コストが発生します。とはいえ、政府のMake in India政策や法人税の引き下げ施策により、海外企業にとって魅力的な設立形態といえるでしょう。
駐在員事務所は、現地法人を持たずにインド市場の調査や情報収集を行うための拠点です。営業活動や収益を得る行為は禁じられており、本社からの経費送金で運営される非営利拠点として位置付けられています。主な業務内容は、市場調査、製品情報の提供、インド企業との連絡調整、技術協力支援などに限定されます。
設立にはインド準備銀行の事前承認が必要であり、金融・保険など一部業種では追加審査が行われることもあります。駐在員事務所は所得税の対象外となりますが、年度末には活動報告書を提出する義務があります。
駐在員事務所の最大の利点は、低コストでインド市場に進出できる点です。初期段階で市場性を見極めたい企業や、将来的な現地法人設立を検討している企業にとって、リスクを抑えつつ足掛かりを築ける有効な手段といえます。ただし、営業行為が一切できない点を理解しておく必要があります。
支店は、インド国外の親会社が直接インド国内で営業活動を行うための拠点です。現地法人とは異なり独立した法人格を持たず、本社の延長線上で事業を行う形式となります。営業・販売・技術提供・アフターサービスなど、商業活動を通じて収益を上げることが認められているのが特徴です。
支店設立には、駐在員事務所と同様にインド準備銀行の承認が必要です。許可後は会社法および所得税法の規定に基づき、現地登記と定期報告を行います。支店で得た利益には法人税および支店利益送金税(約40%前後)が課されるため、税務上の負担が大きい点には注意が必要です。
一方、インド国内で直接契約・販売活動を行えるため、スピーディに収益化を図りたい企業には適しています。特に製造業やサービス業で、本社ブランドを活かして短期的に事業展開したい場合に有効です。ただし、支店は本社が法的責任を負うため、コンプライアンス管理の徹底が求められます。
プロジェクト・オフィスは、特定の契約またはプロジェクトの遂行を目的として設立される一時的な拠点です。インフラ建設、エンジニアリング、技術提供などの分野で、インド企業と契約を締結した外国企業が設置するケースが多く見られます。
設立条件として、インド国内企業との正式なプロジェクト契約を有していることが必須です。また、事前承認なしで設立できる場合もありますが、業種や契約内容によってはインド準備銀行または商工省の承認が必要となります。プロジェクト・オフィスはその契約期間に限定して活動でき、事業完了後には清算・閉鎖手続きを行う必要があります。
税務上は支店と同様に課税対象となり、所得申告や監査が義務付けられているのです。一方で、短期間での事業展開に適しており、大規模インフラ事業や建設案件を受注した日本企業にとって有効な設立形態です。柔軟性とスピードを兼ね備えた形態として、単発契約型ビジネスに適しています。
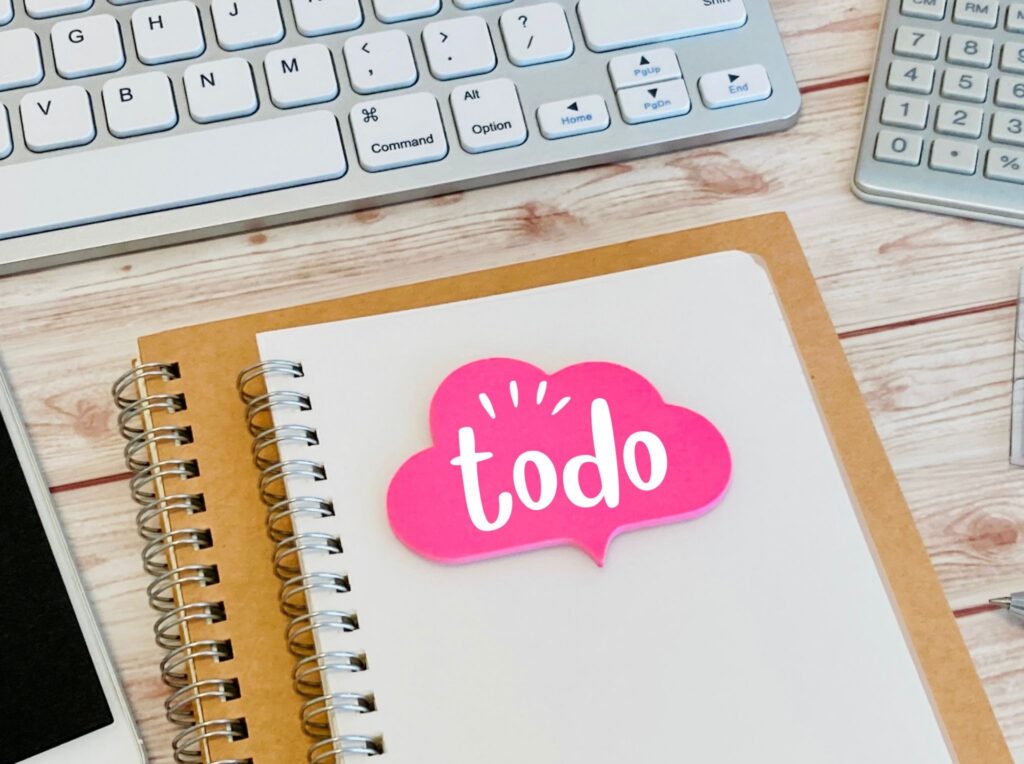
インドで会社を設立するには、複数の行政機関を経由する必要があり、手続きの正確性と順序の把握が非常に重要です。特に外資系企業の場合、インド企業省や税務当局への申請が複雑で、デジタル署名証明書や取締役識別番号など、独自の認証制度に対応する必要があります。
ここでは、会社設立までの流れを10ステップに分けてわかりやすく解説します。各工程で求められる書類や注意点を理解しておくことで、設立までの時間とコストを大幅に削減することが可能です。
最初のステップは、インドで事業を行う上で適用される外資規制・業種規制・税制優遇制度などの事前調査です。インドでは業種によって外資持株比率が制限される場合があり、自動承認ルートと政府承認ルートに区分されています。
例えば、製造業やITサービスなどは比較的自由ですが、防衛産業やメディアなどは政府の許可が必要です。また、設立予定地の州ごとに商業登記の手続きや税制優遇措置が異なるため、州政府レベルの規制確認も欠かせません。
あわせて、環境許可・労働許可・土地使用許可など、関連するローカル法規も事前に洗い出すことが求められます。これらの調査を怠ると、設立後に事業制限や行政処分を受けるリスクがあるため、JETROや現地の法律事務所を通じて最新情報を確認するのが賢明です。
インドでの事業展開を円滑に進めるには、事業内容と会社形態を適切に設計することが欠かせません。会社形態には、現地法人・駐在員事務所・支店・プロジェクトオフィスなどがあり、事業規模や活動内容に応じて最適な形式を選択します。
例えば、長期的な事業展開を想定するなら現地法人が望ましく、一方で市場調査や販売支援のみを目的とする場合は駐在員事務所が適しています。事業目的が製造・販売・サービス提供など多岐にわたる場合には、複数の許認可を並行して取得するケースも。
また、会社形態によって税率・会計監査義務・資本金要件が異なるため、インド商業省や外資投資庁のガイドラインに基づいて慎重に検討することが必要です。設立初期の段階で法的・税務的リスクを最小化することが、後の経営安定につながります。
インドの会社設立手続きでは、すべての申請を電子的に行うため、DSCが必須です。これは、日本でいう電子認証システムのようなもので、MCAのオンライン手続きにおける署名や承認に使用されます。取締役や申請担当者ごとに発行が必要で、政府認定の発行機関を通じて取得。
申請には、パスポート・住所証明書・写真などが必要で、本人確認手続きがオンラインで行われます。発行までには通常2〜3営業日を要します。DSCがなければMCAポータル上での社名申請や設立登記申請を進められせん。
そのため、会社設立をスムーズに進めるためには、最初期段階でDSCの取得を完了しておくことが重要です。特に外国人取締役がいる場合は、パスポートの認証翻訳や公証手続きが必要になるため、余裕をもった準備が求められます。
DINとは、インドで会社の取締役となる人物に発行される固有の識別番号です。会社設立申請時には、最低1名の取締役にDINが付与されている必要があります。
この番号は、MCAによる取締役の管理や不正防止を目的とした制度で、取締役としての登録や将来の登記変更にも使用されます。DINの申請は、フォームDIR-3を通じてMCAポータルで行い、DSCによる署名と本人確認書類を添付。申請が承認されると、即日〜2営業日でDINが発行されます。
なお、すでに他社でDINを保有している人物は再申請の必要はありません。外国籍取締役の場合は、提出書類の認証や翻訳に時間を要するため、国内取締役とのバランスを考慮して進めるとスムーズです。DINは今後の役員変更や登記修正時にも必要となるため、厳重な管理が求められます。
次のステップは、インド企業省の公式ポータルサイトを通じた会社名の予約申請です。名称は他社と重複していないこと、商標法に抵触していないことが条件で、審査を通過すると20日間の有効期間が与えられます。申請はフォームRUNまたはSPICe+を使用し、希望名称と事業内容を入力します。
類似名の有無を事前に検索できるため、商号トラブルを防ぐためにも確認を徹底することが重要です。なお、宗教的・政治的な表現や、政府機関と誤認される名称は原則として認められません。社名が承認されると、会社登記申請時に使用できるようになります。
ネーミングは企業ブランドの印象を左右する重要要素であり、現地文化や発音も考慮した選定が望まれます。
会社名の承認後は、定款および付属定款を作成します。これらは会社の基本ルールを定める重要な書類であり、会社法に基づいて構成。
MOAには会社の目的・所在地・資本金・株主構成などを、AOAには取締役会の運営方法や議決手続きなど内部統治の詳細を記載します。インドでは、定款の電子署名にDSCを使用するため、全株主および取締役が署名を行う必要があります。
さらに、定款はSPICe+フォームに添付して提出されるため、形式や内容に不備があると設立手続き全体が遅延することも。外国企業の場合は、現地法務専門家やコンサルティング会社の監修を受けて作成することが推奨されます。
特に外資比率が高い場合や合弁会社の場合は、資本構成と議決権割合を明確化しておくことが後のトラブル防止につながります。
インドの会社設立手続きでは、すべての申請をSPICe+フォームでオンライン一括提出できます。SPICe+は、会社登記、PAN/TAN申請、税務登録、労働保険登録などをまとめて行える統合申請システムです。フォームでは、定款や取締役情報、資本金、株式配分、事業目的などを入力し、必要書類を添付します。
すべての取締役がDSCで電子署名を行い、MCAの審査を経て承認されます。申請後は、会社識別番号(CIN)が発行され、法的に会社が認められる段階へと進みます。このプロセスは従来より大幅に簡略化され、ペーパーレス化が進んでいますが、入力ミスや書類不備があると却下されることも多いため、専門家による事前確認やドラフトチェックを行うことが重要です。
外資系企業の場合は、資本構成証明書や親会社の登記証明など、追加書類が求められる点にも注意が必要です。
申請が承認されると、会社設立証明書が発行されます。これは会社の正式な設立を証明するもので、会社識別番号(CIN)や発行日が記載されます。この証明書をもって、インドで法人としての法的地位を取得したことになるのです。
証明書の発行後は、定款・登記情報・取締役情報がインド企業省のデータベースに登録され、誰でも閲覧可能となります。また、この段階で同時にPANとTANの申請も自動的に行われます。これにより、税務関連の取引や給与支払いをスムーズに開始できるようになります。
設立証明書の取得には通常3〜7営業日かかりますが、外資系企業の場合は審査が長引くケースも多いです。証明書を受領した後は、次の段階として銀行口座開設・営業許可・税務登録などの手続きを順次進める必要があります。
証明書はビジネス契約・ライセンス申請時にも必須書類となるため、電子・紙双方で大切に保管しておきましょう。
インドでは、法人の税務管理においてPANとTANの取得が義務付けられています。PANは法人の納税者番号として、法人税の申告や銀行口座の開設に使用されます。一方、TANは従業員の給与や業務委託費などの源泉徴収(TDS)を行う際に必要な番号です。
SPICe+の申請段階で同時取得が可能ですが、MCA審査後にインド所得税局から正式なカードが発行されます。これらの番号を取得して初めて、企業は税務上の手続きを行えるようになります。特にTANを取得しないまま給与支払いを行うと、罰金や追徴課税の対象となるため注意が必要です。
また、GST登録が必要な業種では、PANの登録完了後にオンラインでGSTINを申請する流れとなります。税務関連番号は設立後すぐに必要となるため、証明書受領後すぐに確認しておくことが重要です。
最後のステップは、法人銀行口座の開設です。設立証明書、PAN、定款、取締役の身分証明書などを提出し、銀行による審査を経て開設されます。多くの外資系企業は、日系銀行や現地大手銀行を利用しています。
銀行口座開設後は、資本金の払い込みや取引先からの入金、税金支払いなど、すべての商取引をこの口座を通じて行うことになるのです。また、外貨送金を行う場合は、外国為替管理法の規定に従い、RBIへの報告が必要です。
インドでは、KYCプロセスが厳格化しており、外国人取締役や親会社の情報確認に時間を要する場合もあります。そのため、設立証明書を受領した直後から早めに準備を進めておくことが重要です。銀行口座の開設完了により、会社設立手続きは正式に完了し、インドでの本格的な事業活動をスタートできます。
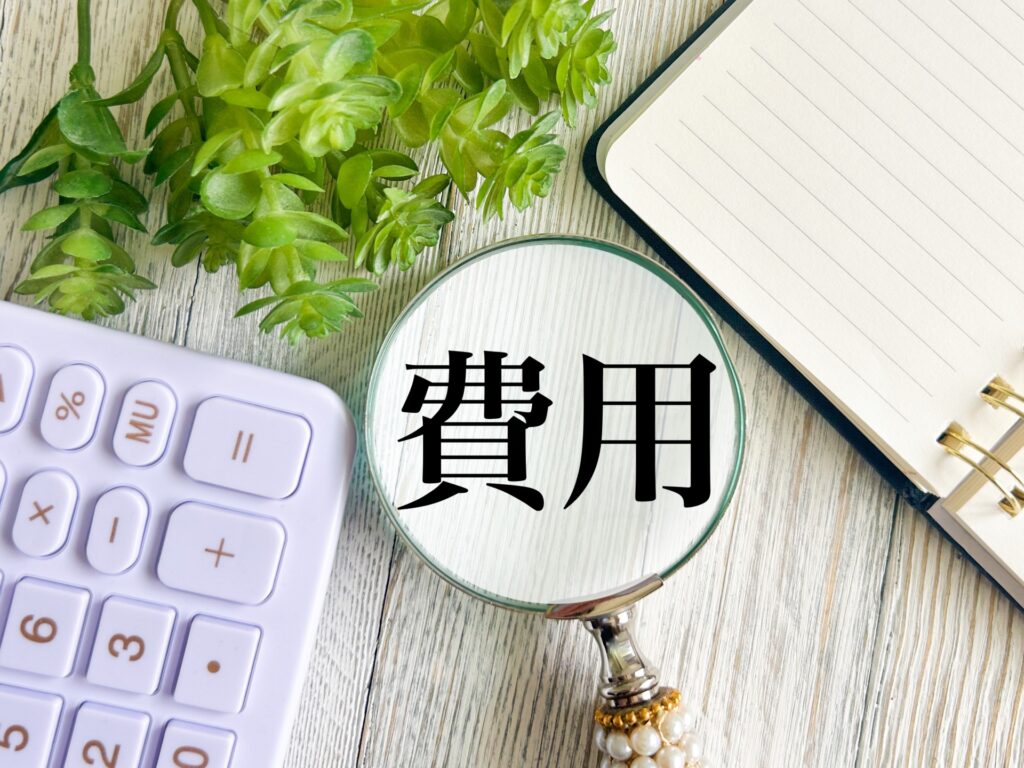
インドで会社を設立する際に必要な費用は、設立形態や資本金、業種によって異なりますが、一般的には総額で20万〜50万インドルピー(約40万〜100万円前後)が目安とされています。
主な内訳としては、登記申請料や公証手数料、定款作成費、デジタル署名証明書および取締役識別番号の取得費用などが挙げられます。また、外資系企業の場合は、書類の認証翻訳や法務代理人への手数料が追加で発生。さらに、インドでは登録資本金に応じた登記料や印紙税が課される仕組みとなっており、資本金が大きいほど設立費用も増加します。
現地コンサルティング会社を活用する場合は、サポート費用として10万〜20万ルピー程度を見込む必要があります。これらに加えて、設立後の会計監査・税務登録・銀行口座開設などにも一定のコストがかかるため、トータルで100万円前後の初期費用を準備しておくのが安全です。

インドで会社を設立する際には、会社形態に関わらず多くの法的書類を準備する必要があります。まず必須となるのが、定款と付属定款で、会社の目的や組織運営の基本方針を明文化したものです。これに加え、取締役および株主の身分証明書や住所証明書、写真が求められます。
外国人取締役を含む場合は、書類を英語に翻訳し、公証およびアポスティーユ認証を受けることが義務付けられています。また、事業所在地の証明、資本金払い込みの証明書、インド国内の連絡先情報も必要です。これらの書類を基に、DSCやDINの取得手続きが進められます。
書類の不備や認証漏れは設立申請の遅延につながるため、事前にMCAのフォーマットに沿って整備しておくことが重要です。外資企業の場合、現地法務専門家のサポートを受けながら準備を進めるとスムーズです。

インド市場での事業成功には、単に会社を設立するだけでなく、現地の商習慣・法制度・人材環境を正確に理解し、長期的な経営戦略を構築することが欠かせません。巨大な人口と経済成長が魅力である一方、州ごとに異なる法律や文化、複雑な税制など、進出後に直面する課題も多く存在します。
ここでは、インド進出を円滑に進めるための3つの重要ポイントとして、「市場ニーズの把握」「法令遵守」「現地人材の活用」を解説します。これらを意識することで、リスクを抑えながら持続的な成長を実現できるでしょう。
インドは多民族・多言語・多宗教の国であり、地域によって購買行動や嗜好が大きく異なります。そのため、進出前に徹底した市場ニーズ調査を行うことが不可欠です。特に、ターゲット層の所得水準、消費傾向、競合他社の動向、流通インフラの整備状況などを把握し、自社の製品・サービスがどの層に最も受け入れられるかを分析する必要があります。
加えて、インドでは価格競争力が成功の鍵を握るため、コスト構造を考慮した現地生産・ローカルサプライチェーンの確立が重要です。単なる市場参入ではなく、どの都市・州から展開するか、どの業界と提携するかを明確にする戦略立案が求められます。政府の政策と整合性を持たせることで、税制優遇や補助金などの恩恵を受けられる場合もあります。
リサーチと戦略を一体化させることで、競合優位性を確立できるでしょう。
インドでは、外国企業による投資は「外国為替管理法」および「外国直接投資政策」に基づいて管理されています。政府は外資を原則自由化しており、多くの業種で自動承認ルートによる100%外資が認められていますが、防衛、通信、保険、メディアなど戦略分野では出資比率が制限され、事前承認が必要です。
これらの制限業種は、いわばインド版ネガティブリストとして「FDI禁止・制限リスト」に明示されています。また、不動産取引や農地取得は外資に原則禁止されており、事業用リース契約のみが認められます。近年は「Make in India」政策のもと製造業や再エネ分野への外資誘致が進みつつあり、規制も段階的に緩和されています。進出前には、最新のFDIポリシーを確認し、業種別の出資上限と承認要件を正確に把握することが不可欠です。
インドの外資規制は「2020年統合版FDI政策」に集約され、宝くじ・賭博・不動産取引などの禁止分野と、業種別の出資上限や条件が定められた条件付き分野に区分されます。認可は、事前承認不要の自動認可ルートと、当局の個別承認が要る政府認可ルートの二本立て。所管はDPIIT(政策)とRBI(FEMA・NDI/DI規則)で、国境接する国からの投資は政府承認が必須です。
さらに2024年改正で、一定要件下での国際取引所への直接上場も可能に。進出前には、対象業種の上限比率・必要ライセンス・適用ルートを最新規程で確認し、手続き・届出期限まで逆算したコンプライアンス計画を用意しましょう。
インド進出を成功させる上で欠かせないのが、現地人材の採用とマネジメント戦略です。インドは若年層人口が多く、英語力・ITスキルに優れた人材が豊富です。
特にエンジニアやマーケティング分野では高度な専門性を持つ人材が多数存在し、現地採用を進めることでコストを抑えつつ事業を拡大できます。ただし、インドでは職業意識や労働文化が日本とは異なり、ジョブホッピングが一般的です。
そのため、給与や福利厚生だけでなく、キャリア形成や企業理念の共有を重視するマネジメントが必要です。また、現地マネージャー層の登用や日本人駐在員との協働体制の構築が、円滑な意思決定とチームの安定につながります。
さらに、州ごとに賃金水準や労働法規が異なるため、採用戦略を地域特性に合わせて最適化することも重要です。現地人材を信頼し、権限委譲を進めることで、企業としての競争力と柔軟性を高められます。

インドは世界有数の成長市場であり、日本企業にとって大きなビジネスチャンスが広がっています。しかし、会社設立や各種許認可の取得には複雑な手続きと現地法規への理解が求められます。
AXIA Marketingでは、インド市場に精通した専門チームが、設立前の市場調査から登記・税務・人材採用支援までワンストップでサポート。初めての海外進出でも安心して事業を立ち上げられるよう、戦略立案から実行まで伴走します。
インド進出を成功させたい企業は、ぜひAXIA Marketingにご相談ください。
参考文献
Copy Link





