
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.10.29


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
近年、ASEAN経済の中心地として存在感を高めるタイは、日本企業の海外進出先として高い注目を集めています。安定した政治基盤や充実したインフラ、BOI(タイ投資委員会)による優遇制度など、ビジネス展開に有利な環境が整っていることが大きな魅力です。
一方で、外資規制(FBA)や複雑な登記手続きなど、事前準備を怠ると設立後にトラブルが生じるリスクもあります。本記事では、タイで会社を設立するために必要な手続き・費用・書類・注意点を網羅的に解説。現地法人や駐在員事務所などの設立形態の違いから、成功に導くための戦略的ポイントまで、実務に直結する情報をわかりやすく紹介します。

東南アジアの経済拠点として成長を続けるタイは、製造業・サービス業・IT産業など多様な分野で日本企業の進出が加速しています。政治的な安定性やASEAN諸国へのアクセスの良さ、BOIによる投資優遇措置など、海外展開を目指す企業にとって魅力的な条件が揃っています。
また、現地には日本人駐在員が多く、日本語対応の専門機関や商工会議所も充実。こうした環境が、初めて海外進出する企業にとっても安心感を与えています。ここでは、タイ進出の主なメリットと日本企業の動向について詳しく見ていきましょう。
タイで会社を設立する最大の魅力は、ASEAN経済共同体(AEC)の中心に位置する地理的優位性にあります。タイは陸・海・空いずれの交通インフラも整備が進み、周辺国への物流ネットワークが発達しているため、ASEAN市場へのハブ拠点として最適です。
特に東部経済回廊(EEC)では、先端製造業や次世代自動車産業の誘致が進み、外資系企業への優遇措置も拡大しています。また、人件費の安さと質の高い労働力も大きな利点です。タイは教育水準が比較的高く、英語・日本語を話す人材も豊富なため、製造業だけでなくサービス業・IT業にも適しています。
さらにBOI(タイ投資委員会)の投資奨励制度を活用すれば、法人税免除や外国人労働許可の簡略化といった恩恵を受けられます。このように、コスト競争力・市場アクセス・制度的支援の三拍子が揃うタイは、海外事業の拡大やリスク分散を目指す日本企業にとって極めて魅力的な進出先と言えるでしょう。
タイは長年にわたり「日本企業に最も選ばれるASEAN進出先」としての地位を確立しています。外務省の海外進出日系企業拠点数調査によると、2020年における日本企業の東南アジアへの進出数は約15000社、そのうちの3分の1である約5,900社がタイへと進出しています。
近年は、ITサービスやスタートアップとの連携を目的とした新規進出も増加傾向にあります。背景には、サプライチェーンの多角化ニーズがあります。中国依存を減らし、生産・販売拠点をASEANに分散する動きが強まる中、地理的に安定したタイは「第二の製造拠点」として再注目されています。また、現地の消費市場も拡大しており、中間所得層をターゲットにした小売・飲食・美容関連ビジネスも活況を呈しています。さらに、タイ政府が進める「Thailand 4.0」政策により、AI・ロボティクス・スマートシティなどの分野で外資系企業の参入が推奨されている点も追い風です。日本企業にとって、タイは単なる生産拠点ではなく、“イノベーションと市場開拓の舞台”として進化を遂げているのです。

タイで事業を始める際には、進出目的や業務範囲に応じて最適な設立形態を選択することが重要です。タイでは主に「現地法人」「駐在員事務所」「支店」「地域統括事務所(IHQ)」の4つの形態があり、それぞれ活動範囲・責任範囲・税務上の扱いが異なります。たとえば、現地で営業活動を行いたい場合と、市場調査や情報収集のみを行いたい場合では、適した形態がまったく異なります。本章では、それぞれの特徴や設立要件、活用シーンについて詳しく解説します。
現地法人は、タイ国内で独立した法人格を持ち、現地企業として営業活動を行う形態です。一般的には「有限会社(Private Limited Company)」として設立されるケースが多く、外国人が出資する場合は外国人事業法(FBA)の規制対象となります。原則として外国人出資比率は49%までとされていますが、BOI(投資委員会)からの認可を受けることで100%外資出資も可能です。
現地法人のメリットは、タイ市場での信頼性が高く、取引先や金融機関からの評価を得やすい点にあります。また、営業・販売・製造など幅広い事業を展開できるため、長期的なビジネス展開を目指す企業に適しています。設立には株主3名以上、取締役1名以上、最低資本金200万バーツ以上が必要です。一方で、法人税(20%)やVAT登録などの税務義務が発生し、会計監査も毎年必要になるため、設立・運営には一定のコストと管理体制が求められます。
それでも、本格的な現地進出を検討する企業にとっては最も汎用的で安定した形態と言えるでしょう。
駐在員事務所は、親会社の連絡・調査・管理を目的とする拠点であり、営利活動(販売・請求・契約締結など)は一切禁止されています。主な業務は、市場調査・製品情報の収集・品質管理・顧客との連絡窓口などに限定されます。駐在員事務所のメリットは、低コストかつ迅速に設立できる点です。
初期投資を抑えながら、現地市場の動向を把握したり、将来的な法人設立の準備段階として活用できます。税務面では、売上や利益が発生しないため法人税の課税対象外となりますが、スタッフ給与や事務所費用などの経費は親会社が負担します。設立には商務省への登録が必要で、所長1名を含む最低2名のタイ人スタッフを雇用するのが一般的です。
また、駐在員には労働許可証とビザが必要です。タイ市場への足がかりとして最適な形態であり、短期的な情報収集や進出前のリスクヘッジに有効です。
支店は、外国企業がタイ国内で直接営業活動を行うための拠点です。現地法人とは異なり独立した法人格を持たず、本社がすべての責任を負うという特徴があります。そのため、資金面や法的リスクがすべて本社に帰属します。
支店のメリットは、本社のブランド・技術力をそのまま活かして営業活動ができる点にあります。現地での売上や契約、請求業務が可能なため、駐在員事務所よりも広範な事業展開が可能です。ただし、外資規制の対象となるため、事業内容によっては商務省の特別許可(Foreign Business License)が必要となります。
また、支店の収益はタイ国内で法人税の課税対象となり、VAT登録や会計監査も義務付けられます。設立には最低資本金(300万バーツ以上)をタイ国内で3年間に分けて払い込み、タイ人スタッフを一定数雇用する必要があります。親会社がリスクを引き受けつつも営業展開を早期に実現したい場合に適した形態です。
地域統括事務所および地域統括会社(International Headquarters:IHQ)は、アジア・ASEAN地域全体の統括拠点として機能する法人形態です。主に、グループ企業の経営管理・財務・人事・マーケティング・研究開発などを統合的に支援する役割を担います。
最大の特徴は、BOIによる税制優遇措置を受けられる点です。IHQとして認定されると、タイ国外の関連会社から得られるサービス収入に対して法人税が免除されるほか、外国人専門職の所得税軽減や関税優遇などの恩恵を受けられます。
これにより、タイはシンガポールやマレーシアと並ぶ「地域統括拠点の誘致国」として注目されています。設立には最低資本金1,000万バーツ以上が必要で、BOIへの申請が前提です。ASEAN全体を見据えた中長期戦略を描く企業に最適な形態であり、生産・販売・研究・財務管理を一元化することで、グループ全体の効率化と税務メリットを同時に実現可できます。

タイで会社を設立するには、日本と同様に複数の行政手続きを順を追って行う必要があります。登記や税務登録だけでなく、外資規制(FBA)やBOI認可など、外国企業特有の要件も多く存在します。特に、事業内容や出資比率によって求められる許可や登記書類が異なるため、最初の段階で制度理解と計画立案をしっかり行うことが成功の鍵です。
ここでは、会社設立の全体像を9つのステップに分け、各段階で押さえるべきポイントを具体的に解説します。
タイでの会社設立を検討する際、最初に行うべきは外国人事業法(Foreign Business Act:FBA)や業種別規制の確認です。FBAでは、外国資本が49%を超える企業について、タイ政府が指定する業種(小売・サービス業など)では原則として外資参入を制限しています。
そのため、進出予定の事業が規制対象かどうかを早期に確認し、必要に応じてBOI(投資委員会)認可や特別許可を取得する準備が必要です。 また、金融・不動産・医療などの一部業種では、別途ライセンスや省庁承認が求められる場合もあります。
これらの規制を理解せずに事業を始めると、営業停止や罰金といった重大なリスクに直結する恐れがあります。さらに、外国人雇用や土地所有に関する法律もあわせて調査しておくと安心です。事業計画を立てる前に法規制を網羅的に確認することが、スムーズな設立プロセスの第一歩となります。
次に行うべきは、進出目的に合わせて事業内容と会社形態を明確にすることです。タイでは、営業活動を行う場合は現地法人や支店の設立が必要となりますが、市場調査や情報収集を目的とする場合は駐在員事務所が適しています。
ASEAN全体を統括する場合は、BOI認可を受けた地域統括会社(IHQ)という選択肢もあります。事業内容を定義する際には、タイ商務省への定款登記で記載する事業目的を明確にする必要があるのです。
事業範囲が曖昧だと、後の許認可申請や税務処理に支障をきたす場合があるため、事前に専門家の確認を受けるのが望ましいです。また、外国人出資比率や資本金額もこの段階で確定します。
BOI認可を受ける場合は、認可業種・投資額・雇用計画などを含めた詳細なビジネスプランを提出する必要があります。
事業形態が決まったら、次は会社名の予約(Company Name Reservation)を行います。これは商務省(Department of Business Development:DBD)が所管しており、会社設立における最初の正式手続きです。希望する会社名をオンラインで申請し、承認を受けることで登記に使用可能となります。
申請時には、第1〜第3希望までの候補名を提出し、既存企業との重複や紛らわしい表現がないかを審査されます。申請が承認されると、通常3日以内に結果が通知され、承認後30日間有効です。この期間内に定款登記を完了させる必要があるため、スケジュール管理が重要です。
会社名は、英語またはタイ語で登録可能ですが、王室関連用語や国家機関と誤解される言葉の使用は禁止されています。また、外資系企業の場合は「Thailand」などの地名を使用する際にも制限があるため注意が必要です。
会社名の予約は一見シンプルに見えて、登記全体の進行を左右する基礎手続きであり、事前の下調べと慎重な候補選定が不可欠です。
会社名の予約が完了したら、次に行うのが基本定款(Memorandum of Association:MOA)の登記です。基本定款は、会社の法的枠組みを定める重要書類であり、タイ商務省(DBD)への提出が義務付けられています。
定款には、会社名・所在地・事業目的・資本金・株式の種類・発行株数・株主構成・発起人情報などを詳細に記載。登記時には、少なくとも3名の発起人(Promoters)が必要で、全員が署名した定款を提出することになります。これらの発起人は、会社設立時に最低1株以上を保有している必要があります。
また、会社の所在地を証明するための賃貸契約書やオーナー承諾書(Letter of Consent)なども添付書類として求められます。定款の内容は将来的な事業変更にも影響するため、曖昧な表現を避け、事業目的を正確かつ広めに設定しておくことがポイントです。
事業内容を限定的に記載しすぎると、新規プロジェクト開始時に追加手続きが必要になるケースもあります。基本定款は、会社の設立憲章といえる重要文書であり、この段階での慎重な作成が後のトラブル防止につながります。
定款の登記が完了すると、次は設立時株主総会(Statutory Meeting)の開催です。この総会では、会社の基本的な運営方針や役員体制、資本金の払い込み方法などを正式に決定します。主な議題は以下の通りです。
設立時株主総会では、発起人全員および出資者の過半数が出席する必要があります。決議事項は議事録に記録し、全員の署名をもって正式な証拠とします。総会の議事録や取締役リスト、株主名簿はその後の法人登記時に提出する必須書類です。
また、資本金の払い込みは通常、取締役名義で一時的に銀行口座に預け入れ、登記完了後に法人名義口座へ移行します。この段階での不備は法人登記に直結するため、法的形式を正確に守ることが極めて重要です。信頼できる会計士や弁護士に同席を依頼する企業も多く、登記準備の最終確認ステップと言えるでしょう。
設立時株主総会を経て、すべての必要書類が揃ったら、商務省(DBD)への会社設立登記(Registration of Company)を行います。これにより、会社が正式な法人格を取得し、事業活動を開始できるようになるのです。
提出書類には、定款、議事録、取締役リスト、株主名簿、会社所在地証明書、資本金の払込証明書などが含まれます。登録手数料は、資本金額に応じて変動し、一般的には資本金100万バーツあたり5,000バーツ前後が目安です。審査期間はおおよそ5〜10営業日程度ですが、書類の不備があると遅延するため、事前のダブルチェックが欠かせません。
法人登記が完了すると、会社は正式に「株式会社(Limited Company)」として認定され、税務登録や銀行口座開設など次のステップに進むことが可能になります。また、登記証明書(Certificate of Incorporation)が発行されるため、今後の各種契約やライセンス申請に使用します。
この登記をもって初めてタイにおける法人としての法的存在が確立するため、全体の設立プロセスにおける最も重要なフェーズと言えるでしょう。
法人登記が完了したら、次のステップは法人名義での銀行口座開設です。これは資本金の正式な払い込みや、日々の経理処理、給与支払い、取引先への入金管理などに不可欠な手続きです。タイではバンコク銀行(Bangkok Bank)、カシコン銀行(Kasikorn Bank)、サイアム商業銀行(SCB)などが一般的で、外資系企業向けのサポートも充実しています。
口座開設には、商務省で発行された登記証明書(Certificate of Incorporation)、会社定款の写し、取締役会議事録(銀行口座開設の承認)、取締役のパスポート・在留証明書などの提出が求められます。銀行によっては、取締役本人の現地出席を必須とする場合もあるため注意が必要です。
また、外貨取引を行う企業は、外貨口座(Foreign Currency Account)の開設も検討すると良いでしょう。資本金の送金ルートや海外送金履歴を明確にしておくことで、将来の税務監査やBOI申請時にスムーズな対応が可能になります。法人銀行口座は経理の基盤であり、設立後の資金運用を円滑に進めるための重要なステップです。
会社設立後、売上が一定額を超える場合は付加価値税(Value Added Tax:VAT)の登録が必要です。タイでは、年間売上額が180万バーツ以上に達した事業者は、Revenue Department(歳入局)へのVAT登録が義務付けられています。
登録が完了すると、VAT登録番号(Tax ID)が付与され、請求書や領収書に記載することが求められます。登録手続きでは、会社登記証明書、取締役の身分証明書、会社所在地の賃貸契約書、事業所の写真、事業内容の説明資料などを提出します。
審査は通常1〜2週間で完了し、登録後は毎月のVAT申告(Form P.P.30)が必要です。VAT登録のメリットとして、仕入れ時に支払ったVATを控除できる仕入税額控除制度が挙げられます。一方で、帳簿や領収書の管理義務が厳格化するため、会計体制の整備が不可欠です。
早めのVAT登録と専門会計士のサポート導入が、税務リスクを防ぐ鍵となります。
従業員を雇用する企業は、社会保険(Social Security)への登録を行う必要があります。これは、タイ社会保険法に基づく義務であり、会社設立後30日以内に社会保険事務所(Social Security Office)へ申請を行わなければなりません。
登録対象は、常勤従業員1名以上を雇用するすべての企業です。会社側の手続きとしては、まず事業所登録(Form SSO 1-01)を提出し、事業者番号を取得。その後、各従業員ごとに被保険者登録(Form SSO 1-03)を提出します。これにより、医療・年金・失業・労災・出産などの社会保障制度が適用されます。保険料は、給与額の5%を上限として企業・従業員がそれぞれ負担し、毎月の給与支払い時に源泉徴収します。支払いは翌月15日までに行うのが原則です。
社会保険登録を怠ると罰金や行政処分の対象となるため、登記完了後できるだけ早く対応することが重要です。この手続きを完了することで、企業としての雇用責任を果たし、従業員の安心と信頼を確保できます。

タイで会社を設立する際の費用は、会社形態や資本金、業種、外資比率によって大きく異なります。一般的な現地法人(有限会社)を設立する場合、登記関連費用としておおよそ5万〜10万バーツ(約20〜40万円)が目安です。
これには、会社名予約、定款登記、法人登記の登録料などが含まれます。さらに、弁護士や会計士などの専門家サポート費用が10万バーツ前後発生するケースも多いです。資本金については、外資比率49%以下のローカル企業では最低資本金の法的要件はないものの、外資100%出資の場合や外国人労働許可を申請する場合は200万バーツ以上が必要です。
また、オフィス賃貸契約、銀行口座開設、印紙代などの諸経費も加味すると、初期費用全体で30万〜50万バーツ(約120〜200万円)が一般的な目安です。このほか、設立後には会計監査・税務申告・社会保険登録などの維持コストが年間で10万バーツ前後かかります。進出前にこれらの費用を正確に試算し、現地専門家と連携して予算計画を立てることが重要です。
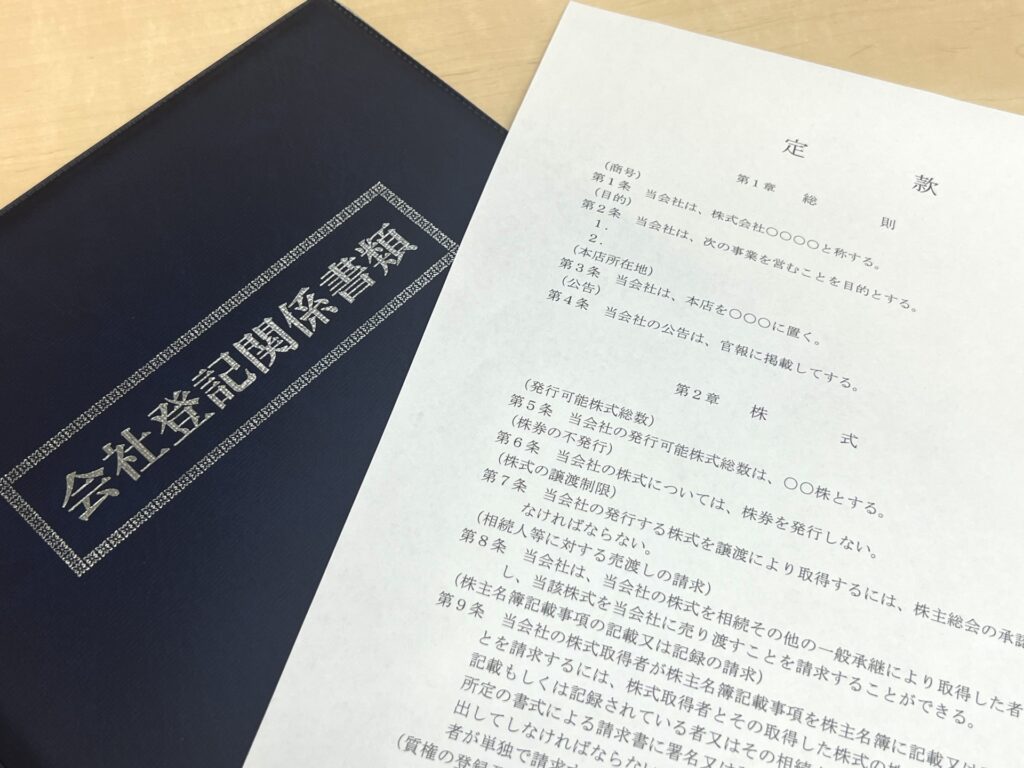
タイで会社を設立する際には、登記や税務登録などの各段階で多数の書類を準備する必要があります。
会社設立で必要となる書類は以下の通りです。
主な提出書類は、会社定款(Memorandum of Association)、株主リスト(List of Shareholders)、取締役名簿(List of Directors)、会社設立登記申請書などです。また、会社の所在地を証明するために賃貸契約書とオーナーの承諾書(Letter of Consent)が求められるほか、代表者や株主のパスポートコピー・署名証明書も必要になります。
外国人が取締役を務める場合は、ワークパーミット(労働許可証)申請のために、学歴証明書や職務経歴書の準備も求められます。さらに、税務関連ではVAT登録申請書類(P.P.20)、社会保険登録に必要な従業員情報リストの提出が必要です。書類の多くは英語またはタイ語で作成し、公証や翻訳証明が求められる場合があります。
特に外国企業の場合、書類の不備や翻訳ミスによって手続きが遅延することが多いため、現地の会計士や弁護士と連携し、正確な書類準備を行うことがスムーズな設立の鍵となります。

タイ進出を成功させるためには、単に会社を設立するだけでなく、現地のビジネス環境や文化的背景を正しく理解した上で、長期的な戦略を描くことが不可欠です。とくに、事前の市場調査やパートナー選定、法令遵守、BOI制度の活用、現地人材の採用戦略などは、進出後の成果を大きく左右する重要な要素です。日本企業の中には、手続きや税制の違いを軽視した結果、想定外のコストや運営上のトラブルに直面するケースも少なくありません。
ここでは、タイ進出を成功へ導くための4つの実践的ポイントと注意点を解説します。
タイ市場はASEANの中でも購買力が高く、製造業・小売業・ITなど多様な産業が発展していますが、市場特性や消費者行動を十分に把握せずに進出すると失敗リスクが高まります。まず重要なのは、業界構造・競合環境・消費トレンドを徹底的に分析することです。例えば、製造業であればEEC(東部経済回廊)での産業集積、IT・小売業であればバンコク中心部や地方都市の購買データをもとに市場規模を予測します。
また、タイでは価格志向の一方でブランドへの信頼性も重視されるため、「高品質×コストパフォーマンス」戦略が鍵となります。日本企業は高品質な製品や丁寧なサービスで高い評価を得ていますが、現地企業との競争を考慮し、ローカルニーズに適した商品設計や販売戦略を立てる必要があります。
さらに、進出初期はターゲットを明確に絞り込み、BtoB向け・BtoC向けいずれにおいても、現地の販路・パートナーとの提携を視野に入れた段階的成長モデルを描くことが成功への近道です。
タイで事業を行う際、最も重要な法規制の一つが「外国人事業法」です。FBAは、外国資本が特定の業種を不当に支配したり、実質的な投資を行わずに利益を得ることを防ぎ、タイ国民の経済的利益と雇用を保護する目的で制定されています。この法律の根幹にあるのが、「資本金」と「最低資本金」という2つの概念です。
資本金は企業の外国法人としての地位を判断する基準であり、最低資本金は外国人がタイで事業を行う際に必要とされる最低限の資本額を意味します。一般的に、外国企業がタイで新規事業を始める場合、最低資本金は200万バーツ以上が求められます。さらに、FBAでは外国人が参入できる業種を3つのリストに分類しており、それぞれ異なる規制レベルが設けられています。
一方で、例外規定も存在します。例えば、製造業や輸出業など、タイ経済への貢献が大きいと判断される分野は外資規制の対象外です。製造工場の設立や製品輸出は雇用創出や外貨獲得につながるため、政府支援を受けやすい傾向にあります。また、タイ投資委員会の投資奨励制度を受けた企業は、外国人事業ライセンスの取得が免除されるケースもあります。
近年では、デジタル産業・Eコマース・IT関連サービスなど新興分野に対してもFBAの適用が検討されており、外資参入の可否が流動的に変化しています。そのため、事業計画の初期段階から現地の法律事務所や進出支援コンサルティング企業と連携し、業種ごとの制限やライセンス要件を正確に確認することが欠かせません。
外国人事業法(Foreign Business Act:FBA)は、外国資本によるタイ国内事業を規制する主要法律であり、日本企業が進出する際に必ず確認すべき制度です。外国人事業法では、外国人が出資比率の50%以上を保有する企業を外国企業と定義し、特定業種での事業活動を制限しています。
例えば、小売業やサービス業、不動産仲介などは外国人単独での経営が原則禁止されています。しかし、BOI(投資委員会)認可を取得した場合や、特別経済区・EEC(東部経済回廊)における優遇事業では、100%外資出資も可能です。また、FBA第17条に基づく「外国事業ライセンス(Foreign Business License)」を取得すれば、例外的に規制対象業種での活動が認められる場合もあります。
FBAを無視して設立を進めた場合、登記後に営業停止命令や罰金が科されることもあるため、事前に事業内容と出資構成を精査し、必要な許可を取得することが絶対条件です。複数の業種を扱う企業は、どの業務がFBAの規制対象にあたるかを専門家に確認することが望まれます。
タイ進出を検討する日本企業にとって、BOI(Board of Investment:タイ投資委員会)の制度を活用することは非常に有効です。BOIは外国企業の投資を促進するために設けられた国家機関で、認可を受けた企業には法人税の免除(最大8年)や関税優遇、外資出資制限の緩和といった恩恵が与えられます。
例えば、先端製造業、電気電子産業、IT、再生エネルギー分野などは優遇対象業種に指定されており、これらの分野で事業を行う企業はBOI申請を行うことで、100%外資出資や外国人専門職の雇用も容易になります。
また、BOI認可企業はワークパーミットやビザ申請の迅速化が可能で、行政手続きの負担を大幅に軽減可能です。ただし、BOIの申請には詳細な事業計画書、投資額、雇用計画、技術移転方針などの明確な提出が求められます。申請が通れば大きなメリットを享受できますが、認可条件を満たさない場合や、認可後の報告義務を怠ると特典が無効になることもあるため、慎重な対応が必要です。
BOI制度を「税制優遇+戦略支援」の両面で活用することが、タイでの長期的な事業成功につながります。
タイ進出後の事業を安定的に成長させるためには、現地人材の活用と育成戦略が欠かせません。タイは労働力人口が豊富で、製造・販売・バックオフィスなど幅広い分野で優秀な人材が確保できます。特に英語教育が進んでおり、グローバル企業とのコミュニケーションにも対応できる人材が多いのが特徴です。
一方で、タイでは日本のような終身雇用の文化が根付いておらず、成果主義・柔軟な働き方を重視する傾向があります。そのため、給与や福利厚生だけでなく、キャリアアップ支援や教育制度を充実させることが人材定着の鍵です。
また、日本式のマネジメントを一方的に押し付けるのではなく、現地の価値観や労働慣習を理解したうえで、チームビルディングを行うことが重要です。
さらに、ローカルマネージャーを中心とした権限委譲を進めることで、現場の意思決定が迅速になり、現地顧客への対応力も高まります。タイ人社員の信頼を得ながら、グローバル基準の経営体制を構築することが、継続的な成長とブランド浸透につながります。

タイでの会社設立は、法規制や手続きの多さから複雑に感じられますが、正しい流れを理解し、現地の制度や文化に即した戦略を立てることで、安定したビジネス基盤を築くことが可能です。
AXIA Marketingでは、市場調査・法人設立・BOI申請・現地人材採用・営業支援までを一貫してサポート。日本企業が抱えやすい課題を熟知した専門チームが、最適な進出プランを提案します。タイ市場で確実な一歩を踏み出したい企業様は、ぜひAXIA Marketingにご相談ください。
参考文献
Copy Link





