
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.10.18


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
自動車業界は今、かつてない変革期を迎えています。電動化・自動運転・カーボンニュートラルへの対応といった技術革新に加え、各国の環境規制や経済情勢、社会構造の変化など、外部環境の影響を強く受ける業界です。
こうした複雑な環境変化を読み解くために欠かせないのが、PEST分析です。本記事では、自動車業界におけるPEST分析の基本から具体的な分析手法、日産やBMWの事例までをわかりやすく解説します。
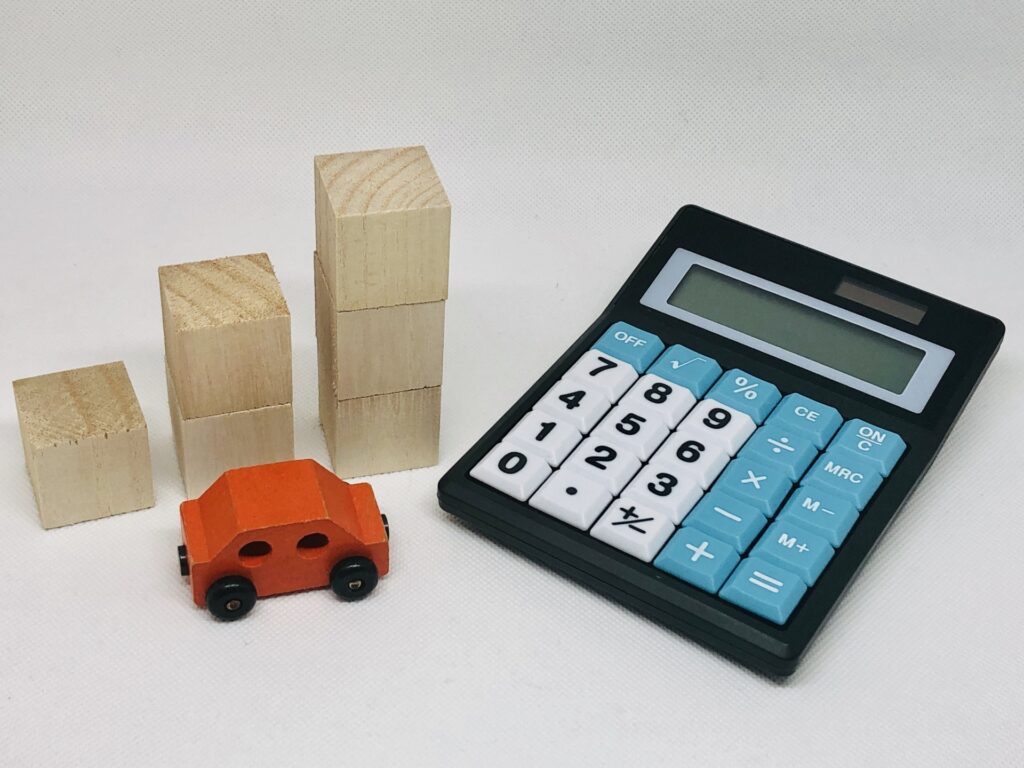
PEST分析とは、企業を取り巻く外部環境を政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの側面から体系的に分析するフレームワークです。
内部要因に焦点を当てるSWOT分析などと異なり、PEST分析はマクロ環境の変化を把握し、将来的なリスクやビジネスチャンスを明確化することを目的としています。自動車業界のように、環境規制や技術革新、社会的価値観の変化といった外的要因が業績や競争力に大きく影響する業界では欠かせない分析手法です。
PEST分析を活用することで、長期的な経営戦略の方向性を定め、新たな市場ニーズや事業機会を的確に捉えることが可能になります。

自動車業界でPEST分析が必要とされる理由は、業界構造が政治・経済・社会・技術といった外部要因の影響を強く受けるためです。特に環境規制や脱炭素政策などの政治的要因は、自動車メーカーの開発方針や生産体制を大きく左右します。
また、経済要因として為替変動や景気動向が販売台数や収益性に直結します。社会面では、人口減少や都市化、若年層の車離れなど、消費者の価値観の変化が需要構造を変えつつあるのです。
さらに、EV(電気自動車)や自動運転などの技術革新は、業界の競争環境を根本から変える要因となっています。PEST分析を行うことで、こうした外部要因を体系的に整理し、今後の市場変化を予測したうえで、柔軟かつ持続的な経営戦略を構築できる点が大きなメリットです。

自動車業界は、環境規制や技術革新、消費者の価値観の変化など、外部環境の影響を強く受ける産業です。ここでは、PEST分析の4つの要因に基づき、業界を取り巻く政治・経済・社会・技術の動向を整理して解説します。
自動車業界における政治的要因は、企業の経営戦略や製品開発方針に直接影響を与える極めて重要な要素です。特に、各国政府による環境規制や脱炭素政策の強化、貿易政策の変動、補助金・税制優遇措置といった施策は、自動車メーカーのグローバル展開や研究開発の方向性を左右します。
政治的な動きに敏感に対応できるかどうかが、今後の競争力を維持する鍵と言えるでしょう。
世界的な脱炭素化の流れにより、自動車業界では厳格な環境規制が相次いでいます。欧州連合(EU)はCO₂排出量削減目標を掲げ、2035年までにガソリン車・ディーゼル車の新車販売を禁止する方針を打ち出しています。日本でも2050年カーボンニュートラル実現に向け、ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)へのシフトが進行中です。
こうした規制強化は、内燃機関の開発縮小や電動化技術への投資拡大を促す一方で、中小部品メーカーには構造転換の圧力となっています。自動車メーカーは、各国の環境基準に対応する柔軟な開発体制とグローバルな生産戦略を整えることが求められています。
自動車業界はサプライチェーンが国際的に広がっているため、関税政策や自由貿易協定(FTA)、地政学的リスクの影響を強く受けます。米中貿易摩擦や英国のEU離脱などは、自動車の輸出入や部品調達コストに直接影響を与えました。
また、ASEAN諸国やメキシコとの経済連携協定(EPA)などは、日本企業に新たな製造拠点や販売市場を提供しています。今後も各国の政策変化に伴い、物流コストや調達ルートの最適化が求められます。政治リスクを見越したサプライチェーンの多様化が、企業の持続的成長のための重要な戦略課題です。
政府による補助金や支援制度は、自動車業界の技術革新と市場拡大を支える重要な原動力です。例えば日本政府は、グリーンイノベーション基金を通じてEV・燃料電池車(FCV)・自動運転関連技術の開発支援を実施しています。
海外でも、アメリカのインフレ抑制法(IRA)により、国内EV生産に対する税控除が拡充されました。これにより、各国メーカーは現地生産やサプライチェーン再編を加速させています。自動車メーカーにとって、こうした政策を活用できるかどうかは、技術開発スピードや国際競争力に直結します。
政策動向を的確に把握し、戦略的に資金調達・投資計画を立てることが不可欠です。
自動車業界は、経済の波に最も敏感に反応する産業のひとつです。景気の好調時には新車販売が伸び、反対に景気後退や物価上昇が起これば販売台数は減少します。
また、為替相場の変動や国際経済の不安定化は、輸出入コストや海外生産の収益性に大きな影響を及ぼします。自動車メーカーは、こうしたマクロ経済の動向を常に注視し、柔軟な価格戦略や調達戦略を取る必要があります。
自動車の販売は、景気動向と強く連動しています。個人消費や企業投資が活発な時期には、自家用車や商用車の需要が増加し、販売台数も上向きます。反対に、景気が低迷すると消費者の買い替え需要が減少し、特に高価格帯の車種は販売が落ち込むのが一般的です。
例えば、リーマンショック後やコロナ禍では、新車販売が世界的に大幅減となりました。現在も金利上昇や不確実な経済情勢が続く中、リース・カーシェアなどの利用が拡大しています。自動車メーカーは、消費支出の動向に合わせた柔軟な販売戦略と、価格以外の付加価値(燃費性能、サブスクリプション型サービスなど)での差別化が求められています。
近年の世界的なインフレは、自動車業界にも深刻な影響を及ぼしています。原材料費(鉄鋼、リチウム、半導体など)の高騰により、車両価格が上昇。消費者の買い控え傾向が強まっています。一方で、物価上昇下でもエネルギー効率の高いEVやハイブリッド車(HV)に注目が集まるなど、購買行動には明確な変化が見られるのです。
燃費性能・維持費の安さを重視する層が増え、長期的なコストパフォーマンスが重視される時代に移行しました。メーカーは、価格戦略だけでなく、ライフサイクル全体の価値訴求を行うことが、今後の購買行動変化に対応する鍵となります。
自動車業界はグローバルに展開しているため、為替変動や国際経済の動向が利益構造に直結します。円安が進行すると、海外での販売利益は増加する一方、輸入部品のコストが上昇するという両面の影響が生じます。
例えば、2024年の急激な円安局面では、輸出型企業が業績を伸ばした一方で、輸入依存度の高いサプライヤーはコスト圧迫に直面しました。また、米中関係の緊張や欧州経済の不安定化など、地政学的要因も生産体制やサプライチェーンに影響を与えています。
自動車メーカーは、複数通貨での取引や現地生産の拡大など、為替リスクを分散させるグローバル戦略の重要性がますます高まっています。
自動車業界における社会的要因は、人々の生活様式・価値観の変化に直結しています。特に人口構造の変化、都市化の進展、ライフスタイルの多様化は、自動車の需要構造を根本から変える要素です。日本をはじめとする先進国では少子高齢化が進み、若年層の「離れや移動手段の多様化が顕著です。
一方、新興国では都市化や所得向上に伴い、初めて車を購入する層が増加しています。社会的要因を的確に捉えることは、将来の市場を見据えた製品戦略・販売戦略の立案に不可欠です。
日本や欧州諸国では、人口減少と高齢化が自動車市場に大きな影響を与えています。高齢者が増えることで、自動車の所有よりも「安全」「利便性」「維持コストの低さ」が重視される傾向が強まっています。
また、運転免許返納者の増加により、MaaS(Mobility as a Service)や自動運転技術への需要が拡大中です。一方、地方では公共交通の衰退により移動の足として自家用車の必要性が依然高く、都市部と地方での需要構造が二極化しています。
メーカーは、高齢者向けの安全支援機能を強化した車種の開発や、シェアリング・自動運転サービスへの転換を進めるなど、多様なモビリティの形を模索しています。
世界的に都市化が進む中で、自動車利用の形態も変化しています。人口が集中する都市部では、交通渋滞や駐車スペースの問題から所有する車よりも必要なときに使う車への需要が拡大。カーシェアやライドシェア、電動スクーターといった新たなモビリティサービスが普及しています。
また、政府による交通インフラ整備やスマートシティ構想の進展により、EV充電ステーションや自動運転対応道路などの新たな整備も進行中です。これにより、自動車業界は単なる車の販売業から移動サービス提供業への転換が求められています。
都市化の進展は、車の在り方そのものを再定義する転換点となっているのです。
現代の消費者は、車を移動手段としてだけでなくライフスタイルの一部として捉えるようになっています。特に若年層では、車のブランド力よりも「環境への配慮」「サブスク利用のしやすさ」「デジタル連携」などが購入動機に直結しています。
また、サステナブル志向やエシカル消費の高まりにより、電気自動車(EV)や再生素材を用いた内装車の人気が上昇。加えて、リモートワークや地方移住の進展によって、必要とされる車種も多様化しています。
メーカーは、消費者のライフスタイルを深く理解し、機能性だけでなく体験価値を提供する車づくりが求められています。社会的要因の変化を先読みできる企業こそ、次世代の自動車市場で優位に立てるでしょう。
自動車業界における技術的要因は、業界構造そのものを変える最重要ファクターです。特に電動化(EV化)、自動運転、再生可能エネルギーの活用などは、メーカー間の競争軸を燃費性能から環境性能・デジタル性能へとシフトさせています。
また、車両データを活用したサービス開発やAIによる生産・物流の効率化も進み、業界全体で“スマートモビリティ”への転換が急加速しています。テクノロジーの進化を正確に把握することは、今後の競争優位性の確立に欠かせません。
電気自動車(EV)の普及は、自動車業界の変革を象徴する最も大きな技術的潮流です。各国政府による脱炭素政策や排ガス規制の強化を背景に、EVシフトが世界規模で加速しています。日本でもトヨタ、日産、ホンダなどがEVラインナップを拡充し、欧州では2035年以降のガソリン車販売禁止を目指す国も登場しました。
これにより、製造・部品サプライチェーンも大きく再編されつつあります。また、EVの航続距離向上や充電インフラ整備が進むことで、ユーザーの心理的ハードルも低下。メーカーは価格競争からエネルギー効率・デザイン・付加価値の競争へと軸足を移し、EVを核とした新しいエコシステムの構築を進めています。
自動運転技術の進展は、自動車の概念を運転するものから移動空間を提供するものへと変えつつあります。AIやセンサー、LiDAR(ライダー)などの技術革新により、レベル3以上の自動運転車が実用化段階に入りました。
日産やホンダ、トヨタをはじめとする国内メーカーに加え、テスラやGoogle系Waymoなどのテック企業も参入し、競争はますます激化しています。自動運転技術は単に利便性を高めるだけでなく、交通事故の削減や物流効率の最適化、移動弱者支援といった社会課題の解決にも直結しています。
今後は法整備やインフラ連携を含めたエコシステム構築が進むことで、完全自動運転社会への移行が現実味を帯びてきているのです。
EV普及を支える要となるのが、バッテリーと再生可能エネルギーの技術革新です。従来のリチウムイオン電池に代わる全固体電池やリサイクル型バッテリーの開発が進み、コスト削減と環境負荷低減が同時に実現しつつあります。
さらに、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを用いた充電ステーションの整備も進行中で、車とエネルギーの融合(V2X技術)が注目されています。自動車メーカーだけでなく、エネルギー企業・IT企業との連携によってグリーンモビリティ市場が拡大。環境にやさしく持続可能な車づくりが、企業のブランド価値を左右する時代になっています。
バッテリー技術の進歩は、単なる駆動力の向上にとどまらず、自動車産業全体の未来を左右する中核技術といえるでしょう。
理論だけでなく、実際の自動車メーカーがどのようにPEST分析を経営に反映しているかを知ることは、理解を深めるうえで非常に有効です。ここでは、日産とBMWという異なる市場戦略を持つ大手自動車企業を題材に、PESTの視点からどんな環境要因に注目し、どんな対策をとっているかを具体的に見ていきます。

日産は、グローバル展開を前提とした自動車メーカーであり、各国の政治・環境規制、技術進化などの外部要因を戦略に組み込んでいます。例えば、環境規制強化に対応するため、電動化を加速させるアリアやノート e-POWERなどのモデル投入を進めています。
また、多くの国で補助金政策が用意されていることを見据え、EV導入を後押しする販売戦略を展開。さらに、為替や国際貿易政策の変動を念頭に、生産・調達拠点の分散化を図ることで、外部リスクの分散を行っています。
こうした実践は、PEST分析を生かした事業戦略の一端と見られます。

BMWは、プレミアム車市場をリードするドイツの自動車ブランドであり、高級感・技術力・ブランド力を軸に事業展開をしています。政治的には、欧州の脱炭素政策や排出規制強化に対応して、EVモデル「i」シリーズやプラグインハイブリッド車を強化。経済的要因を見据え、燃費性能や走行性能によって付加価値を訴求し、富裕層の消費動向を鋭く捉えています。
社会的には、サステナビリティやブランド体験を重視する消費者層の志向に対応し、高品質・環境負荷低減を前提とした商品設計を実践。技術面では自動運転支援システムやコネクテッドカー技術、次世代バッテリー開発に注力し、未来のモビリティ企業への進化を意識した戦略を描いています。

自動車業界では、PEST分析を単なる理論ではなく実践的な戦略設計ツールとして活用することが求められます。政治・経済・社会・技術の各要因が複雑に絡み合う中で、どの要素が事業にチャンスをもたらし、どの要素がリスクとなるのかを整理することが重要です。
以下では、PEST分析を効果的に進めるための4つのステップを紹介します。これらを実践することで、環境変化に強い経営戦略を構築できるでしょう。
最初のステップは、政治(P)、経済(E)、社会(S)、技術(T)の各要因ごとに情報を体系的に集めることです。自動車業界では、環境規制や補助金政策などの政治的要因、景気や為替、原材料価格などの経済的要因、人口動態やライフスタイルの変化といった社会的要因、EV・自動運転・AIなどの技術的要因が重要な焦点となります。
これらの情報は、政府の統計、業界団体のレポート、各国の自動車政策文書、テクノロジー関連のニュースなど、複数の一次情報を組み合わせて収集することが不可欠です。
PEST分析で失敗しやすいのは、情報の“解釈”を“事実”と混同してしまうことです。そのため、集めたデータを「客観的事実」と「主観的な解釈」に分ける工程が欠かせません。
例えば、政府がEV補助金を拡充したというのは事実であり、今後EV市場が拡大するだろうというのは解釈にあたります。この区別を明確にすることで、分析の信頼性が格段に高まります。
自動車業界では、規制変更や国際情勢など不確定要素が多いため、複数のデータソースを突き合わせ、客観的根拠に基づいた判断を行うことが重要です。
分類した事実は、次に機会と脅威に分けます。例えば、政府によるEV購入補助金の拡充は機会といえますが、排出規制の強化や関税引き上げは脅威となります。この段階で重要なのは、事実をポジティブかネガティブかで単純に分けるのではなく、自社の立場やビジネスモデルに照らして評価することです。
自動車業界では、技術革新が速く、昨日の脅威が明日の機会になることも少なくありません。したがって、定量データと市場トレンドを掛け合わせて柔軟に判断する視点が求められます。
最後のステップは、整理した機会と脅威に対して、どんな戦略的アクションを取るかを検討することです。例えば、EV市場の拡大という機会に対しては、新モデルの投入やバッテリーサプライチェーンの強化を行う。一方、為替変動リスクという脅威に対しては、生産拠点の分散化やヘッジ取引によるリスク軽減策を講じるなど、実行可能な施策を明確にすることが大切です。
PEST分析を分析で終わらせず、戦略に結びつけることが、自動車業界の環境変化に対応する最も効果的な方法と言えるでしょう。

PEST分析は、自動車業界の経営戦略を立てる上で非常に有効なフレームワークですが、正しく実施しなければ単なる情報の羅列に終わってしまいます。政治・経済・社会・技術といった外部環境の変化を捉えるには、目的意識を持った分析、信頼できるデータの選定、そして継続的な見直しが欠かせません。
以下では、PEST分析を効果的に機能させるための3つの重要なポイントを解説します。
PEST分析を行う際に最も重要なのは、なぜこの分析を行うのかという目的を明確にすることです。自動車業界においては、新規市場参入、EV(電気自動車)開発、海外工場設立、あるいは法規制への対応など、目的によって分析の焦点が大きく異なります。
目的が曖昧なまま情報を収集すると、膨大なデータの中で本質的な示唆が埋もれてしまうリスクがあります。例えば、国内市場縮小への対応策を検討することを目的に設定すれば、社会的要因(人口減少・価値観変化)や経済要因(購買力低下)を重点的に分析するなど、調査の方向性が明確になります。
PEST分析の精度は、使用するデータの質によって大きく左右されます。自動車業界では、国際的な政策・技術トレンド・経済変動が複雑に絡み合うため、信頼性の高い一次情報を重視することが不可欠です。
政府・各国の環境省や経済産業省の統計、国際エネルギー機関(IEA)、日本自動車工業会(JAMA)、OECDなどの公的データは特に有用です。また、メーカーのIR資料や調査会社の業界レポートも有効な情報源となります。SNSやニュースサイトの情報も参考になりますが、それらは補足的に扱い、客観的なデータに基づいた判断を優先することが成功の鍵です。
PEST分析は一度実施して終わりではなく、継続的にアップデートすることが重要です。自動車業界では、EVシフトや自動運転技術の進展、国際的な環境政策の変化など、外部環境が数か月単位で変化するのです。
例えば、欧州の排ガス規制や中国のEV補助政策などは、短期間で業界構造に影響を与える可能性があります。そのため、半年から1年ごとにPEST分析を見直し、最新の情報を反映させることが望まれます。継続的なモニタリング体制を構築すれば、変化をいち早く察知し、迅速に戦略を修正できる体制が整うでしょう。

自動車業界はEVや自動運転の進展、環境規制の強化、人口動態やライフスタイルの変化など、外部環境の影響を強く受ける産業です。そのため、PEST分析を通じて政治・経済・社会・技術の動向を正しく把握し、将来のリスクと機会を見極めることが欠かせません。
しかし、自社だけで正確かつ継続的に情報を収集・分析するのは容易ではありません。AXIA Marketingでは、最新の海外市場調査と専門的な分析をもとに、企業ごとに最適な戦略立案を支援しています。海外展開や新規事業を検討する際は、ぜひご相談ください。
参考文献
Copy Link





