
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.10.18


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
ビジネス環境が急速に変化する現代において、企業が持続的に成長するためには競合対策が欠かせません。特に日本市場は人口減少や需要の成熟化が進み、同質化した商品やサービスが溢れています。その中で自社の強みを活かし、競合との差別化を図ることは生き残りの必須条件です。
また、デジタル化の加速により、顧客が選べる選択肢は国内外問わず増え続けています。本記事では、競合対策の基本的な考え方から重要視される理由、差別化戦略や分析に役立つフレームワークまで具体的に解説します。

マーケティングにおける競合対策とは、市場で同じ顧客層を狙うライバル企業に対して、自社の価値を明確に打ち出し、優位性を築くための取り組みを指します。単に他社を意識するだけでなく、顧客のニーズや購買行動を深く理解したうえでなぜ自社の商品やサービスを選ぶべきなのかを明確にすることが重要です。
具体的には、競合の価格設定や商品特性、販売チャネル、マーケティング手法を調査し、自社の強みやバリュープロポジションと照らし合わせながら戦略を立案します。競合対策は短期的な販売促進にとどまらず、ブランドの信頼性向上や長期的な顧客ロイヤルティの構築にも直結するため、企業が持続的に成長していくための基盤とも言えるでしょう。

現代のビジネス環境では、従来以上に競合対策の重要性が高まっています。かつては市場の成長余地が大きく、企業が自然に顧客を獲得できる時代もありました。
しかし現在は国内市場の成熟や少子高齢化による需要減少が進む一方、デジタル化の波によって新規参入企業が増加し、競争が激化しています。このような状況で生き残るためには、自社の強みを明確化し、他社との差別化を図ることが欠かせません。以下では競合対策が重要とされる2つの背景について解説します。
日本市場は人口減少や少子高齢化に伴い、多くの産業で需要の伸びが鈍化しています。従来のように市場が拡大しているから売上も伸びるという図式が通用しなくなり、企業は限られたパイの中で競合とシェアを奪い合う状況に直面しているのです。
例えば、自動車や家電、日用品といった成熟市場では、顧客の購買行動は安さや便利さだけでは動かず、ブランド体験やアフターサービスなど付加価値が重要視されます。こうした背景から、企業は競合他社との差別化戦略を明確にしなければ、価格競争に陥り利益率を下げてしまいます。
国内市場の成熟化は、企業にとって自社ならではの強みを磨き続けることの必然性を示しているのです。
近年、ECサイトやSNSの普及により、消費者の購買行動は大きく変化しました。オンライン上では情報が簡単に比較できるため、顧客は価格や機能だけでなく、レビューやブランドの信頼性も基準に商品を選びます。
また、クラウドサービスやデジタル広告の低コスト化によって、小規模企業や海外の新興企業でも容易に市場参入できるようになりました。その結果、従来の競合だけでなく、異業種からの新規参入者も増え、競争環境は一層複雑化しています。
企業がデジタル環境下で競合に打ち勝つには、データ分析に基づくターゲティングや、SNSを活用したブランドストーリーテリングなど、従来型マーケティングとは異なるアプローチが欠かせません。デジタルシフトは競争を激しくする一方で、新しい差別化のチャンスを生み出す契機でもあるのです。

競合対策を成功させるには、単に他社の動きを真似したり、価格を下げてシェアを奪おうとするだけでは不十分です。持続的な成長を実現するためには、自社の存在意義を明確にし、顧客がなぜ自社を選ぶのかという理由を作り出す必要があります。
その際に欠かせないのが、顧客視点・自社視点・競合視点の3つの観点です。顧客の本質的なニーズを理解し、自社ならではの強みを磨き上げ、さらに競合他社との比較で差別化ポイントを明確にすることが、戦略立案の土台となります。
以下では、競合対策において特に重要な3つの視点について詳しく解説します。
競合対策を考える上で最も重要なのは、顧客のニーズを出発点にすることです。顧客は商品やサービスそのものではなく、課題を解決してくれる体験や理想を実現する手段に価値を見出しています。例えば、同じスマートフォン市場でも「高性能カメラを求めるユーザー」「低価格で十分な機能を求めるユーザー」「ブランド力を重視するユーザー」など、ニーズは多様です。
自社がどのニーズに焦点を当てるかを明確にすれば、顧客にとって選ばれる理由が生まれます。単なる商品スペックや価格競争に陥るのではなく、顧客の声を調査・分析し、潜在的な課題や感情に寄り添った差別化を実現することが、持続的な競合優位性につながります。
競合対策では、顧客のニーズに応えるだけでなく、自社が持つ強みを最大限に活かすことも重要です。自社の強みとは、他社には真似できない技術力やブランド力、サービス体制などを指します。これを整理し、顧客にどのような独自価値を提供できるのかを明文化することが、戦略の核となります。
例えば、アフターサポートの充実や地域密着型の対応といった差別化要素は、大手企業が提供する低価格戦略では再現しづらい強みです。バリュープロポジションを明確に提示することで、顧客は「この企業だから選びたい」と納得できます。競合対策を考える際は、自社の強みを見直し、それを顧客ニーズとどう結びつけるかを意識することが不可欠です。
競合対策を考える上で、競合他社の動向を正しく把握することも欠かせません。同じ顧客層を狙う企業がどんな価値を提供しているかを比較することで、自社が埋めるべき差別化の余地が見えてきます。
例えば、競合が価格の安さを武器にしているなら、自社は品質やアフターサービスで勝負するなど、別の軸で戦う必要があります。また、顧客レビューやSNSの声を分析すれば、競合商品への不満や改善要望が見つかり、それを取り込むことで優位性を築けるでしょう。
重要なのは競合を真似るのではなく、競合と異なる価値をどう提供できるかを見極めることです。競合比較を通じて、自社の立ち位置を明確化し、顧客にとって唯一無二の存在になることが、競合対策の本質と言えます。
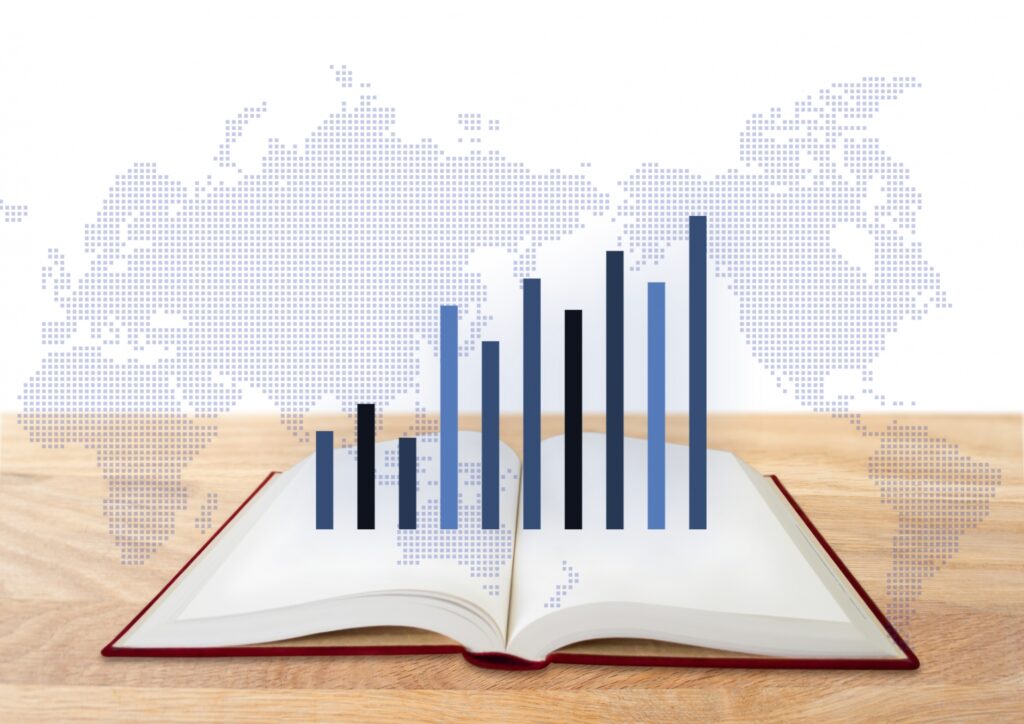
競合の多い市場で勝ち残るには、単に価格を下げたり広告を強化したりするだけでは不十分です。持続的に選ばれるブランドになるためには、顧客に他では得られない価値を提供することが不可欠です。そのための方法が、差別化戦略です。
差別化といっても抽象的な発想ではなく、具体的にどの領域で競合と違いを生み出すのかを明確にしなければ効果は薄れます。ここでは、商品やサービスそのものの独自性、顧客が体験するブランド価値、市場の絞り込み、強みの掛け合わせという4つの具体的なアプローチについて解説します。
差別化戦略の基本は、商品やサービス自体に独自性を持たせることです。顧客は他社にはない機能や独自のデザイン性・使いやすさに価値を感じます。例えば、飲料業界では味だけでなくパッケージデザインや健康成分の付加価値が重要視されるように、同じカテゴリーでもユニークな特徴を示せば強力な差別化要因です。
さらに、技術力に基づく特許や独自レシピなどは模倣困難であり、長期的な競争優位を築けます。重要なのは市場に存在しない新しい価値を提案することです。既存商品の改良であっても、顧客の不満を解消する小さな改善が大きな差別化につながるケースも少なくありません。
差別化は商品そのものだけでなく、顧客がブランドに触れる体験によっても実現できます。例えば、購入前のカスタマーサポートや店舗での接客、購入後のアフターサービスまで、顧客が接するあらゆる場面でポジティブな体験を提供することで、このブランドは安心して選べるという信頼が生まれます。
スターバックスが単なるコーヒーショップを超え、顧客に心地よい第三の場所という体験を提供しているのは代表的な例です。また、SNSやコミュニティ運営を通じて顧客と双方向の関係を築くことも、体験を価値に変える手法です。競合と同じ商品を扱っていても、体験価値の差は大きなブランドロイヤルティを生み出す要素になります。
幅広い市場で多くの顧客を取り込もうとするよりも、特定の市場セグメントに焦点を当てる方が、強い差別化を実現できます。ターゲットを絞り込むことで、その顧客層のニーズに深く応える商品設計やマーケティングが可能になるからです。
例えば、化粧品業界では「敏感肌専用」「男性向け」「ヴィーガン対応」など、ニッチな領域に特化することで競合が少なく、強力なブランドポジションを築けます。また、BtoB分野でも「中小企業専用」「医療業界特化」などの戦略が効果的です。
セグメントを明確にすれば、広告費や販売チャネルの効率も向上し、資源を無駄なく活用できます。
単一の強みだけで、競合優位を保つのは難しくなっています。そのため、複数の強みを掛け合わせて独自の価値を生み出すことが重要です。
例えば、高品質な商品に加え、環境配慮やサステナビリティへの取り組みを前面に出すことで、単なる機能的価値ではなく共感されるブランド価値として差別化できます。あるいは、テクノロジーとデザイン性を融合させることで、競合が真似しにくい独自性を打ち出せます。
上記のように、複数の要素を組み合わせることで生まれる複合的な差別化は、模倣を困難にし、長期的に選ばれ続けるブランドへと成長する原動力となるでしょう。

競合対策は、思いつきや一時的な施策で行うのではなく、体系的なプロセスに基づいて進めることが成功の鍵です。特に競争環境が激化する現代においては、「どの企業を競合と捉えるのか」「どのように情報を整理するのか」「どの段階で戦略に落とし込むのか」を明確にする必要があります。
ここでは、競合対策を実務に落とし込むための5つのステップを解説します。
競合対策の最初のステップは、誰を競合とするのかを明確にすることです。一般的に競合は、直接的に同じ商品・サービスを提供する直接競合と、代替手段を提供する間接競合に分けられます。
例えばタクシー業界では、同業他社だけでなく、ライドシェアサービスや公共交通機関も間接競合に含まれます。すべての企業を対象に調査すると情報量が膨大になり、効果的な分析ができなくなるため、自社のターゲット顧客や市場セグメントに基づき、調査対象を絞り込むことが重要です。
市場規模や地域、価格帯といった軸を設定して競合を分類すれば、後の分析や戦略立案の精度が高まります。
調査対象を絞り込んだら、次に必要なのは競合の情報収集です。情報源は多岐にわたり、競合の公式ウェブサイトやIR資料、プレスリリースはもちろん、SNSでの発信内容や顧客のレビュー、求人情報なども参考になります。
また、業界レポートや政府統計データを活用すれば、客観的な市場環境を把握することも可能です。さらに、営業現場からのフィードバックや展示会・セミナーでの情報収集も有効です。大切なのは定性的な情報と定量的なデータをバランスよく集めることです。
例えば、価格やシェアは定量情報、顧客満足度やブランドイメージは定性的情報にあたります。これらを組み合わせると、競合の実態を多角的に把握できます。
情報を集めただけでは競合対策にはなりません。収集したデータを整理し、洞察に変えるためにはフレームワークを活用することが有効です。代表的なものに、3C分析、SWOT分析、5フォース分析、ポジショニングマップがあります。
フレームワークを使うことで、客観的かつ体系的に競合環境を分析でき、属人的な判断に頼らない戦略策定が可能になります。重要なのは、どのフレームワークを選ぶかよりも、一貫して分析を継続する仕組みを作ることです。
分析結果をもとに、自社の戦略を立案・見直しするフェーズに移ります。ここで大切なのは、競合の動きを模倣するのではなく、自社ならではの強みをどう生かすかを明確にすることです。
例えば、競合が低価格戦略を打ち出している場合に、同じ土俵で戦うのではなく、付加価値を高めることで差別化する選択肢もあります。また、競合の弱みを突く戦略も効果的です。例えば、競合がデジタル対応に遅れているのであれば、自社が積極的にDXを推進して優位性を確立するといった方法です。
定期的な見直しにより、外部環境や顧客ニーズの変化に応じて柔軟に戦略を調整していくことが求められます。
競合対策は一度行えば終わりではなく、継続的なプロセスです。市場や顧客ニーズ、競合環境は日々変化しているため、定期的に分析を繰り返すことで初めて有効な競争優位を維持できます。
例えば四半期ごとに主要競合の動きをレビューし、売上や新サービスの展開状況を確認することで、自社の戦略に反映できます。また、環境変化が激しいデジタル市場では、月単位での見直しが必要な場合もあるでしょう。
さらに、見直しのプロセスには営業やマーケティング部門だけでなく、経営層や開発部門も巻き込むことで、全社的な視点から戦略を強化できます。継続的な改善の積み重ねが、長期的に選ばれる企業への成長につながります。

競合対策は、自社の成長に直結する重要な取り組みですが、進め方を誤ると正しい意思決定ができず、逆効果になるリスクもあります。特に近年は、情報が氾濫する中で信頼性の低いデータに惑わされるケースや、AIの分析結果に過度に依存するケースも増えています。
また、市場環境は短期的なトレンドと長期的な構造変化が混在しており、それらを切り分けて考える視点が不可欠です。ここでは、競合対策を行う際に注意すべき4つのポイントを整理します。
競合分析で最も避けたいのは、一つの情報源に依存してしまうことです。例えば、競合企業の公式発表だけを基にすると、実態よりも良く見せた情報に引きずられてしまう可能性があります。
一方でSNSの評判や口コミは、偏った意見や誤情報が混じるリスクがあります。信頼性を高めるためには、IR資料や業界レポートといった客観的なデータ、顧客インタビューや営業現場からの声といった現場情報を組み合わせることが重要です。
複数の情報源をクロスチェックすることで、偏りを排除し、現実に即した競合環境の把握が可能になります。
近年、競合調査にAIを活用する企業が増えています。AIは膨大なデータを短時間で処理できるため、情報収集や傾向把握に非常に役立ちます。しかし、その分析結果をそのまま鵜呑みにするのは危険です。
AIは公開情報に基づく分析に強みを持ちますが、最新の動きや現場での細かな変化を捉えることは苦手です。また、アルゴリズムに偏りがあると結論が歪められるリスクもあります。AIの結果はあくまで参考値とし、人間が一次情報や現場感覚をもとに検証するプロセスを組み合わせることが重要です。
AIの強みと弱みを理解したうえで活用することで、競合対策の質を高められます。
競合分析を行う際にありがちな失敗は、短期的な動きに振り回されてしまうことです。例えば競合が新商品を投入した直後は、一時的に話題性や売上が急上昇することがあります。しかし、それが市場に定着するのか、それとも一過性のブームで終わるのかを見極める必要があるのです。
一方で、人口動態の変化や技術革新など、長期的な構造変化はすぐには数字に表れないものの、将来的な市場シェアに大きな影響を及ぼします。そのため、短期的なトレンドと長期的な動向を切り分け、両者を組み合わせて分析することが重要です。バランスを意識することで、より持続的な競合優位性を築けます。
競合対策は一度実施すれば完了するものではなく、継続的に取り組むべき活動です。競合環境や市場構造は日々変化し、新しいプレイヤーの登場や消費者の嗜好の変化が常に起こります。
もし分析や対策を一度きりで終わらせてしまうと、競合に後れを取り、気づけばシェアを奪われているという事態にもなりかねません。効果的な方法は、定期的なサイクルで競合分析を組み込み、四半期ごとや半期ごとのレビューの実施です。
また、営業やマーケティング部門だけでなく、開発や経営層も巻き込み、全社的に共有することで対策の実効性が高まります。継続性こそが、競合に打ち勝つ最大の武器となります。

競合対策を効果的に行うためには、感覚や経験に頼るだけでなく、論理的なフレームワークを活用して客観的に状況を整理することが重要です。フレームワークを用いることで、市場全体の構造や自社の立ち位置、競合との強み・弱みの比較を明確化でき、戦略立案の精度が高まります。
ここでは、マーケティングや経営戦略の現場で幅広く使われている代表的な4つの分析手法をご紹介します。
3C分析は、
の3つの視点から状況を整理するフレームワークです。市場規模や顧客ニーズといった外部環境を把握しつつ、競合企業の戦略や強みを分析し、最後に自社の立ち位置を明確化します。
例えば新商品の投入を検討する際、顧客が求める価値を確認し、競合がどんな提供価値を持っているかを把握すると、自社が差別化できる余地を見つけやすくなります。3C分析はシンプルながら実践的であり、新規事業の検討や既存事業の成長戦略を立てるうえで有効な基本ツールです。
SWOT分析は、
の4つに分類して現状を把握するフレームワークです。内部要因である自社の強みと弱みを整理し、外部要因である市場機会や脅威を加えて俯瞰的に検討します。
例えば、自社の技術力の高さが「強み」である一方、人材不足が「弱み」になることもあります。同時に、新しい市場の成長は「機会」、競合の新規参入は「脅威」として把握できます。SWOT分析の利点は、プラス要因とマイナス要因を一枚のシートで整理できる点です。
経営戦略の全体像を描く際や、課題の優先順位を決める際に役立ちます。
5フォース分析は、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱したフレームワークで、業界における競争要因を5つの力(フォース)で整理します。その要素は、
です。この5つを総合的に評価することで、業界の収益性や競争環境の厳しさを把握できます。例えば飲食業界では、競合が多いだけでなく代替品(コンビニ弁当など)の存在も大きな脅威です。5フォース分析を通じて、自社が有利に戦える市場環境かどうかを判断でき、参入戦略や投資判断に活用できます。
ポジショニングマップは、価格・品質、デザイン性・機能性といった2つの軸を設定し、競合他社と自社の位置づけを視覚的に把握できる分析手法です。例えば化粧品市場で価格とブランド力を軸にマッピングすると、高価格・高ブランド力の商品群と、低価格・大衆向けブランドが一目でわかります。
ポジショニングマップを作成することで、自社がどのポジションを取るべきか、競合が参入していない空白地帯を発見できるのが大きなメリットです。特に新商品開発やブランディング戦略を検討する際に有効で、自社の差別化戦略を明確に描くための実践的ツールといえます。

競合対策を効果的に行うためには、的確な調査と分析、そして実行可能な戦略の立案が欠かせません。しかし、自社だけで常に最新の市場動向を把握し続けるのは容易ではありません。
AXIA Marketingでは、海外市場も含めた幅広いマーケティング支援を提供しており、競合分析から戦略立案、実行まで一貫してサポートします。専門的なノウハウと実績をもとに、貴社の成長に直結する戦略を共に構築していきます。
参考文献
Copy Link





