
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.10.18


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
日本の大手ゼネコンは、国内市場の縮小が懸念される中で、積極的に海外進出を加速させています。特にアジアや北米を中心に、都市インフラや大規模建築の需要が拡大しており、各社の成長戦略の柱となりつつあります。実際に海外売上比率が30%を超える企業も登場しており、グローバル競争の中で存在感を高めているのが現状です。
本記事では、最新のIR資料をもとに海外展開に注力するゼネコンをランキング形式で紹介するとともに、市場動向や課題、今後の展望についても分かりやすく解説します。

ゼネコンの海外進出とは、日本国内の建設需要だけに依存せず、成長が期待される海外市場に活躍の場を広げる取り組みを指します。具体的には、オフィスビルや商業施設といった都市開発、空港や道路などのインフラ整備、再生可能エネルギー施設の建設など、多岐にわたるプロジェクトを海外で受注・施工する活動を含みます。
建設業の海外進出は1970年代以降本格化し、海外受注実績は1983年度に初めて1兆円を超えたが、その後は一進一退を繰り返し、2004年度に4年ぶりに1兆円台に回復しました。
背景には、日本国内の少子高齢化や都市部の開発余地の限界により建設市場が縮小傾向にある一方で、アジア諸国を中心に人口増加や都市化が進み、建設需要が急速に拡大しているという現状です。ゼネコン各社は技術力や安全性、品質管理の高さを強みに海外進出を進め、グローバル競争の中で存在感を高めています。
ゼネコン各社は国内市場の縮小を背景に、成長が見込める海外市場への進出を加速させています。ここでは、海外事業に注力している主要ゼネコン5社をランキング形式で紹介します。(明確にIR上に売上高・比率が記載されていない場合があるため、順位付けはできません。)

鹿島建設は国内大手ゼネコンの中でも海外展開に積極的な企業であり、2025年3月期の海外売上高は11,168億円、海外売上高比率は38.4%に達しています。特に北米やアジアを中心に大型プロジェクトを数多く手掛け、インフラ整備から都市開発まで幅広い分野で実績を積んでいます。
海外売上比率が約4割に迫る点は、同業他社と比較しても際立った特徴といえ、国内市場の縮小を見据えた国際戦略の成果が現れている証拠です。加えて、現地法人やパートナー企業との連携を通じ、各国の商習慣や法規制への対応力を高めている点も強みです。鹿島建設は単なる建設請負に留まらず、都市の持続可能な成長に資するソリューションを提供するグローバルプレイヤーとして地位を確立しています。
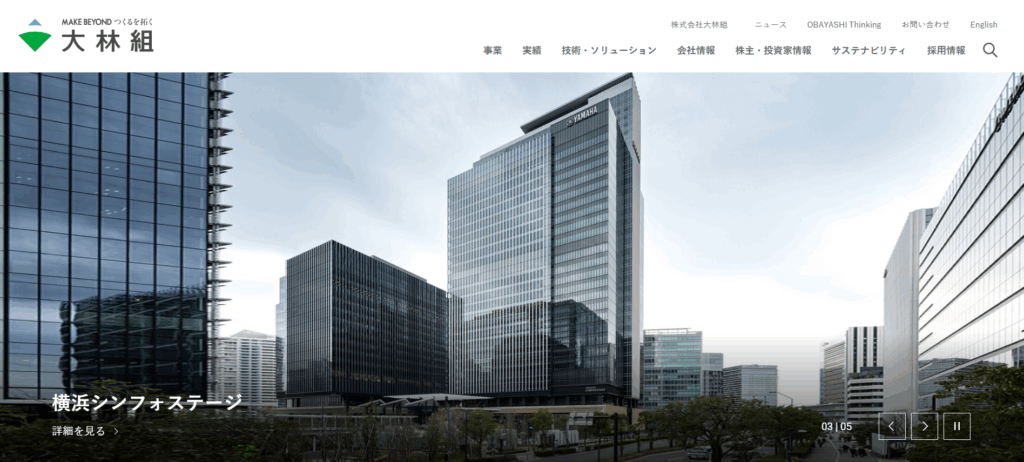
大林組は、ゼネコンの中でも海外展開に一定の実績を持つ企業です。2025年3月期の連結決算によれば、総売上高は約2兆6,201億円、そのうち海外売上比率は約29.2%にあたる7,574億円を占めています。この比率からも、国内市場のみならずグローバル市場への依存度を高めている姿勢がうかがえます。
海外建設事業に対しては、北米、アジアなど複数の地域で事業基盤を築いており、各国現地法人や提携先との協働を強めているのが特徴です。またセグメント別データを参照すると、建築・土木を含む海外事業は大林組の収益構造において補完的な柱として定着していることが読み取れます。
ただし、海外事業の割合が高いわけではなく、国内建設事業も引き続き基盤を支える重要なセグメントです。したがって、大林組の海外進出は拡大だけでなく、国内外のバランスを保つ戦略としても捉えられます。今後は、海外での競争激化や為替変動などのリスクをどう制御するかが、成長の鍵となるでしょう。

竹中工務店は、国内大手ゼネコンのひとつで、伝統と革新を併せ持つ企業として知られています。海外展開も古くから進めており、2022年度の連結実績では海外売上高は2,135億円、海外売上比率15.5%%に達していました。
また地域別の内訳を見ると、アジアで1,207億円、ヨーロッパで524億円、北米で403億円と分散しており、複数エリアに事業基盤を築いているのが分かるでしょう。さらに、竹中工務店は22か国で事業を展開し、約7,000件の海外プロジェクトを手掛けてきた実績も公表しています。
竹中工務店の強みは、国内で培った高い技術力や品質管理ノウハウを生かしながら、海外の法制度や標準へ適応する柔軟性にもあります。多様な地域への進出によりリスク分散を図るとともに、得意分野である建築や都市開発、商業施設のプロジェクトで確固たる実績を残している企業です。
今後は海外売上比率をさらに高めつつ、プロジェクト採算性・現地パートナー網の強化が勝負どころとなるでしょう。

清水建設は、国内スーパーゼネコンの一角として、日本国内事業が主力とはいえ、海外展開にも着実に取り組んでいます。2025年3月期の決算資料によると、清水建設の海外受注高(連結)は1,337億円となっており、全体受注に占める比率も一定水準を示しています。ただし、海外売上そのものを明確に示すデータは限定的ですが、受注ベースで海外案件を積み増していることは確かです。
清水建設は、伝統的な建築・土木工事に加えて、再生可能エネルギーや環境インフラ分野にも注力しており、洋上風力建設プロジェクトで欧州の有力企業とアライアンスを組むなど、技術融合型の展開を進めています。これにより、単なる建設業を越えたソリューション型企業へと進化を図ろうとする姿勢が見て取れるでしょう。
利益面では、国内建築事業の採算改善などにより、2025年3月期は売上高が前年比約3.0%減となったものの、営業利益が改善し黒字転換を果たすなど、収益性を強化する動きもあります。
清水建設の強みは、国内で培われた設計力・施工力をベースに、海外の高度インフラ案件や環境分野での技術提携を通じた差別化戦略を併走させている点です。今後は海外受注拡大とコスト制御、為替変動対応が鍵となるでしょう。

大成建設は、スーパーゼネコンとして国内基盤を維持しつつ、海外展開にも注力している企業です。2025年3月期の連結決算によれば、売上高は2兆1,542億円と前年比22.1%増加し、営業利益は1,201億円と前期を大きく上回る成果を出しました。
ただし、IR資料上では海外売上高や海外比率が明確に開示されておらず、ランキングにおける海外展開の度合いを正確に比較するには限界があります。大成建設の強みは、国内外のプロジェクト受注力・施工力・技術力にあり、特に海外プロジェクトの受注ベースで存在感を発揮しています。
今後は、海外でのインフラ再開発や都市建設案件を取り込むため、為替や現地法規、採算性を管理しつつ、海外売上比率を高めていくことが課題になるでしょう。

近年、日本の大手ゼネコンは積極的に海外市場へ進出し、売上比率を高める戦略を進めています。その背景には、国内需要の伸び悩みと海外市場の成長性の2つの大きな要因です。日本では人口減少や都市開発の一巡により、公共工事や民間投資の需要が縮小する懸念が強まっています。
一方で、アジアを中心とした新興国では都市化やインフラ需要が拡大しており、巨大な建設市場が形成されつつあります。こうした環境変化に対応するため、ゼネコンは収益基盤をグローバルにシフトさせる必要があるのです。ここでは、ゼネコンが海外進出を加速する理由について解説します。
日本国内の建設市場は、高度経済成長期やバブル期に比べて明らかに縮小傾向にあります。人口減少や少子高齢化により住宅需要が頭打ちとなり、さらに大規模都市開発の多くが既に完了していることから、新規の建設案件が減少しています。
加えて、公共事業においても財政制約から大型投資が限定的であり、リニア中央新幹線や一部の都市再開発を除けば、成長ドライバーが限られているのです。そのため、ゼネコン各社は国内需要だけに依存していては将来の成長が見込めない状況に直面しています。
この現実を背景に、持続的な収益を確保するためには海外市場への進出が不可欠となっており、積極的なグローバル展開が進められているのです。
一方で、アジアをはじめとする新興国の建設市場は急速に拡大しています。人口増加と都市化の進展に伴い、住宅供給、インフラ整備、商業施設開発といった幅広い需要が高まり続けているのです。特に東南アジアでは、経済成長を背景に鉄道、空港、高速道路といった基幹インフラの整備が急務となっており、ゼネコンにとっては大規模案件を受注できる絶好の市場環境が整っています。
また、アジア各国の政府は海外投資を積極的に受け入れており、日本のゼネコンが持つ高い技術力や品質管理は大きな強みとなっています。拡大を続けるアジア市場はゼネコンにとって成長のエンジンであり、国内縮小のリスクを補う戦略的なフィールドとして位置づけられているのです。
ゼネコンの海外展開に注目が集まる中、設備工事や空調・電気設備を手がけるサブコンも着実に国際市場へ進出しています。彼らは専門技術力を武器にインフラや建築プロジェクトの裏側を支える役割を担っており、現地の信頼性あるパートナーとして重要性を高めているのです。
ここでは、サブコンの代表例として新菱冷熱工業を取り上げ、その海外展開の戦略と特徴を詳しく見ていきます。

新菱冷熱工業は、空調・衛生・電気設備を中心とする設備系サブコンとして、長年にわたり海外展開を進めてきた企業です。1979年に香港地下鉄の駅舎空調設備を手掛けたことを出発点に、シンガポール、タイ、インドネシアなど東南アジア各国で地下鉄や駅舎空調・換気設備工事を継続的に受注しています。
とりわけシンガポールでは、地下鉄駅舎空調および換気設備を担当する割合が非常に高く、地下鉄駅の約7割に新菱冷熱の技術が導入されているとされています。さらに、新菱冷熱工業はグローバル対応力にも力を入れており、海外拠点数は77拠点以上に拡大しています。また、2024年にはインドのクリーンルームパネル事業を手掛けるGMP Technical Solutionsの買収を発表。これにより、同社の海外事業基盤を強化し、HVACやクリーンルーム市場への拡張を図る戦略が明らかになりました。
こうした動きは、設備技術をコアにしつつ新領域を獲得し、海外競争力を一層高める姿勢といえます。

きんでんは、日本を代表する総合設備エンジニアリング企業で、電気・通信・空調・衛生設備など多岐にわたる技術サービスを提供しています。国内基盤を維持しつつ、長年にわたって海外市場にも進出し、幅広くビジネスを展開している点が特徴です。
具体的には、きんでんは世界90カ国以上で設備工事の実績を持ち、東南アジアを中心に10カ国以上に海外拠点を展開しています。また、海外事業においては、電気・計装・情報通信・空調・衛生設備の企画・設計から施工・メンテナンスまでの一貫体制を海外拠点で展開することで、現地の需要に密着した高品質サービスを提供しています。
さらに、戦略的なM&Aにもより、海外展開を強化しています。例えば、UAE・ドバイに拠点を持つ総合設備工事会社IEMS社に出資し、持分を取得することで現地での技術力と信頼ネットワークの活用を目指しています。
この出資は、きんでんのグローバル戦略を加速させ、中東市場におけるプレゼンス強化を狙うものです。きんでんは単なる国内設備企業にとどまらず、海外市場での技術展開とネットワーク構築を通じて、よりグローバルな企業としての地位を確立しようとしています。

関電工は、電気・空調・衛生設備などを担う総合設備系サブコンとして、国内市場での強みをベースに海外展開を進めています。最新の統合報告書によれば、海外事業は売上ポートフォリオを多様化する戦略の一環と位置づけられており、グリーンイノベーションやPPA(電力販売契約)事業など、新規領域も合わせて拡大を図っています。
具体的な動きとしては、フィリピンの電気・空調・衛生設備工事会社PHPCに対し40%出資し、現地事業基盤を獲得する戦略を採用しています。これにより、施工ノウハウの現地化、人材確保、顧客ネットワーク拡充を一気に進められる体制を構築しているのです。
また、ベトナムでは従来の駐在員事務所を現地法人化し、継続的な設備保守や修繕案件を通じた関係構築を狙っています。さらに、シンガポールなど東南アジアにおいて支社や事業拠点を設置し、現地マネージメント体制を整えて、効率的な現地対応を可能にしています。
これらの取組みによって、関電工は単なる国内設備企業から、地域特性に対応できるグローバル設備企業への変革を目指しているのが特徴です。一方で、出資戦略・現地法人化・技術移転・採算制御などの課題を克服することが、今後の成長の鍵となるでしょう。

高砂熱学工業は、日本の設備エンジニアリングを代表する企業の一つで、空調・換気・環境制御システムを中心に国内外で施工実績を持つ企業です。国内では工場やビル・研究施設の空調設備を手がける一方、海外展開にも意欲的な動きを見せています。実際、海外プロジェクト事例として「MAX Thailand Factory-1,2,3」や「SODA NAMSIANG AROMATIC(タイ)」など、東南アジアでの工場・研究所設備の実績が公開されています。
2025年6月には、タイにおける設備関連会社3社の株式を取得し、海外事業体制の強化を図るM&Aを発表しました。この買収により、現地拠点の運営権確保と技術・ノウハウの展開拡張が期待されています。さらに、同社は1980年に社内に海外事業本部を設けるなど早期から国際戦略に着手しており、香港、マカオ、タイなどにも子会社や支店を設立しています。加えて、マレーシア法人も活動の一環として言及されており、海外技術拠点の拡充が地理的な広がりとして確認できるでしょう。
技術力を活かした環境制御、クリーンルームなど高度制御領域でも展開しており、設備系サブコンの枠を超えたソリューション提供型ビジネスモデルへのシフトが見られます。これらの動きにより、高砂熱学は設備分野における国内外架け橋企業として、今後より一層グローバルな存在感を強めていく可能性があります。

日本のゼネコンは、国内市場の縮小リスクを背景に、成長性の高い海外市場での事業展開を加速しています。進出先は幅広く、北米・東南アジア・欧州といった主要エリアで存在感を示しています。各地域にはそれぞれの市場特性があり、例えば北米では巨大インフラ投資や環境規制、東南アジアでは都市化と人口増加、欧州では脱炭素や持続可能性といった潮流が事業機会を左右するのです。
ゼネコン各社は、こうした地域ごとのニーズに適応しながら、建設技術・マネジメント力を発揮し、グローバル市場で競争力を強化しています。ここでは、ゼネコンが海外進出している主なエリアと特徴について解説します。
北米市場は、世界最大級の建設需要を持つエリアの一つです。特にアメリカでは、老朽化した道路や橋、公共施設の更新に加え、再生可能エネルギーやデータセンターといった新領域への投資が活発です。ゼネコンにとっては高い技術力を発揮できる舞台であり、大規模プロジェクトを通じて収益機会を確保できます。
一方で、厳格な入札制度や労働規制、環境基準の高さなどが参入障壁となります。日本のゼネコンは、現地企業とのパートナーシップやM&Aを活用することで、リスクを抑えつつ事業を拡大しています。特に環境対応建築や地震対策技術など、日本独自の強みを活かした分野で評価を得ており、安定的な成長を見込める市場です。
東南アジア市場は、人口増加と経済成長による都市化の進展が顕著で、建設需要が急拡大しています。インドネシアやベトナム、タイ、フィリピンなどでは、住宅・商業施設から鉄道・空港・港湾といった社会インフラ整備まで、多岐にわたるプロジェクトが進行中です。
加えて、ASEAN各国の政府は外資誘致に積極的で、日本のゼネコンも現地企業と提携しながら事業を展開しています。比較的コスト競争力のある市場であるため、効率的な施工管理と技術力が差別化の鍵となります。また、日本のゼネコンは防災技術や品質管理の面で信頼を獲得しやすく、長期的な関係構築が可能です。経済成長に伴い、今後さらに需要が増えると見込まれる成長市場といえるでしょう。
欧州市場は、持続可能性と環境対応が最重要テーマとなっているのが特徴です。EUの環境規制や脱炭素政策により、省エネ建築や再生可能エネルギー関連施設への投資が拡大しています。特に北欧やドイツなどでは、環境配慮型の建築プロジェクトやゼロエネルギービルの需要が高く、日本のゼネコンも技術提携や現地法人を通じて進出しています。
一方で、欧州は成熟市場であり、既存の大手建設会社との競争が激しいため、差別化戦略が必須です。日本企業は、耐震設計や高品質な施工管理、さらには最先端の建築技術を武器に市場参入を図っています。社会的責任やサステナビリティが重視される欧州市場では、環境と品質の両立を実現できるゼネコンに大きなチャンスがあります。

日本のゼネコンにとって海外進出は大きな成長機会である一方、現地の市場特性や外部環境に左右されやすいという課題も抱えています。特に国際取引に伴う為替の変動、国ごとに異なる法規制や商習慣への対応、地政学的リスクなどは、事業の安定性を揺るがす要因となり得ます。これらのリスクを適切に把握し、事前に備えることが、グローバル市場で持続的に事業を展開するための必須条件です。
ここでは、ゼネコンが海外進出する上での3つの課題とリスクについて解説します。
海外での建設プロジェクトは、多額の契約金額や長期的なスケジュールを伴うため、為替変動の影響を大きく受けるのです。例えば円高が進めば、円換算での売上は減少し、採算性が悪化します。一方で円安になれば輸入資材のコストが上昇する可能性もあり、利益計画に直結します。
そのためゼネコン各社は、為替予約やヘッジ取引を活用してリスクを軽減しているのです。また、契約時に現地通貨建てを採用するなど、契約形態を工夫することで影響を最小化する取り組みも進んでいます。為替リスクへの備えは、海外事業の安定的な収益確保に欠かせない重要な戦略といえるでしょう。
海外進出において大きな壁となるのが、各国ごとに異なる法規制や文化、商習慣です。建設許可の取得手続き、労働基準、環境規制などは国ごとに異なり、遵守しなければ大規模な遅延や罰則につながります。
また、現地の商習慣や文化を軽視すると、パートナー企業や行政との信頼関係を築けず、事業の進展が難しくなるリスクがあります。例えば、契約文化が強い欧州や、関係性重視の東南アジアなど、地域ごとの特徴を理解することが不可欠です。
日本のゼネコンは、現地の法律事務所やコンサルタントと連携しながら、適切な対応策を講じることでリスクを軽減し、スムーズな事業展開を可能にしています。
ゼネコンが海外で活動する際には、政治情勢や安全保障の変化による地政学リスクも避けて通れません。政権交代や紛争、経済制裁などはプロジェクトの中断や資金回収の遅延を招く恐れがあります。
また、カントリーリスクとしては、現地の経済不安定性や治安の悪化、インフラの脆弱性が挙げられます。特に新興国では、プロジェクト開始後に規制変更や政策転換が起きることもあり、リスク管理が重要です。
そのため、多国間開発銀行の保証制度や保険を活用するほか、複数国に分散して進出することでリスクを分散させる戦略も有効です。地政学的要因を的確に見極めることが、安定した海外展開の成否を左右します。

ゼネコン各社の海外展開は、日本国内市場の縮小を背景にますます重要性を増しています。しかし、為替変動や現地法規制、地政学的リスクなど克服すべき課題も少なくありません。こうした状況で確実に成果を上げるためには、現地市場調査や戦略的なパートナー選定、リスク分析を専門的にサポートする存在が必要です。
AXIA Marketingでは、豊富な海外進出支援の実績を活かし、戦略立案から実行支援までを一貫してサポートします。海外市場での成長を目指すなら、ぜひAXIA Marketingにご相談ください。
参考文献
Copy Link





