
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.09.20


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
技術探索は、新規事業や研究開発、オープンイノベーションにおいて欠かせません。社内外の先端技術やアイデアを効率的に集め、評価し、自社の課題解決や新たなビジネス創出につなげるための仕組みを築くことが求められます。
この記事では、技術探索の基礎的な意味から具体的な進め方を、注意点も交えながら具体的に解説します。ぜひ貴社の成長戦略の参考にしてみてください。

技術探索とは、簡単に言うと「技術の使い道を探すこと」です。ただ新しい技術や情報を集めるだけでなく、その技術が自社の課題解決や新しい事業づくりに役立つかどうかを深く考え、実際に役立てるための方法を見出すプロセスです。
例えば、論文や特許、技術ニュース、展示会などから幅広く技術情報を集めるなかで、「これを自社の商品やサービスにどう生かせるか」「自社の課題解決に結びつくか」など、活用のヒントを丹念に探していきます。現代のビジネス環境では、複数の企業や研究機関とも連携し、オープンイノベーションの場を活用することも重要になっています。
そして、集めた情報を単にストックするのではなく、社内関係者と共有しながら評価・分析し、どの技術が本当に市場価値や将来性があるかを見極めていくことが大切です。こうした活動を継続して行う体制が整えば、新しい技術の導入や事業の可能性を広げるための“土台”となります。
つまり技術探索は、「情報集め」だけで終わらせず、自社の未来をつくる“技術の活かし方”を見つけて広げていく、実践的な活動なのです。

技術探索の効率的な進め方は、あらかじめ明確な手順を決めて段階的に進行することが肝要です。
まずは、解決すべき技術テーマや課題を設定し、関連キーワードを用いてネットワーク内外の多様な情報ソースから広く検索を行います。そして大量の検索結果から独自の評価軸に従って分類し、重要な技術群や有望な候補を整理していきます。その絞り込んだ技術を専門文献で調べて科学的知見や事例をまとめることで、経営層への提案やプロジェクト計画策定に説得力を持たせることができるでしょう。
ここで技術探索の進め方を、それぞれのステップに分けて解説していきます。
最初のステップは、自社が直面している課題や今後取り組みたいテーマについて、どんな技術が関わる可能性があるかを洗い出すことです。「解決したい問題」や「目指したい姿」を出発点に、専門家の意見や社内外の議論も参考にしながら、幅広い技術キーワードをリストアップします。
そのうえで、論文データベースや特許情報、業界レポート、学会や展示会情報、さらには技術ニュースサイトやスタートアップの情報など、多様な情報源を活用して徹底的に検索を行います。ここでは「とにかく関連しそうなものは全て拾う」くらいの気持ちで、できるだけ多くの知見や新しい動きを集めるのがポイントです。さらに、最初は検索範囲やテーマをやや広めに取り、情報を集めながら重要なキーワードや焦点分野を徐々に絞り込んでいくと効率的です。
検索ツールの高度な機能も積極的に使いましょう。例えば、キーワードによるフィルタリングや、論文・特許の自動タグ付け、類似技術の抽出機能などを駆使することで、膨大な情報を効率的に整理できます。専門データベースには、関連文献の引用関係や業界動向が俯瞰できるダッシュボード機能を備えたものも多く、検討の抜け漏れを防ぐうえでも役立ちます。
このようにして情報探索を進めると、単なる“手探り”では掴めなかった有望技術や、新しい技術潮流の兆しをより短時間で探し当てることができます。最初の「検索・情報収集」の質と広がりが、以降の技術評価・選定の成果を大きく左右しますので、ここは時間と労力を惜しまずじっくり取り組むことが重要です。
本当に価値のある技術を見つけ出し、自社で活用するためには“分類”のステップがとても大切です。
大量に集まった技術情報は、そのままでは役立てにくい状態です。そこで、自社の経営や技術戦略と照らし合わせて、それぞれの技術が自分たちにとってどれくらい価値があるのかを判断する基準―「評価軸」を決めて整理します。例えば、その技術が自社の課題解決にどれだけ貢献しそうか、どのくらい実用化されているのか、他社とどう差別化できるのか、応用範囲や導入コスト、事業化の現実性など、さまざまな視点で点数をつけて順位付けしていきます。
この分類作業はただデータを並び替えるだけでなく、マトリックスや技術マップなど視覚的にまとめて、関連性や優先度が一目でわかるようにするのが理想的です。こうすれば、どの技術が自社にとって本当に力を入れるべき対象なのかが明確になります。
さらに、分類や評価のプロセスには他部署のメンバーや現場の専門家も加わることで、多角的で現実的な判断ができます。過去の社内プロジェクトや参考になる外部事例と比較しながら、リスクや成功の可能性もあわせてチェックすることも重要です。
このように、本当に期待できる技術を“選び抜く”流れをしっかりと組み込めば、技術探索は「ただ調べる」だけの作業から、自社の強みになる技術に資源を集中させる“戦略的なプロセス”へと深化します。技術探索を成功させるには、この分類・評価・選別の丁寧なステップが欠かせません。
重要な技術群がある程度絞り込まれたら、その次の段階として「文献を把握する」していきます。ここで言う文献には、学術論文や特許、技術白書、開発報告など、信頼性の高い専門資料などが挙げられます。こうした文献をじっくり読み込み、技術の基本的な原理や仕組みはもちろん、最新の研究動向や今まさに注目されている課題、そして競合企業や先行研究者が実際にどこまで進めているのかという開発状況も把握していきます。
文献調査を行う際は、情報の正確性や新しさ、科学的な根拠(エビデンス)がしっかりしているかを特に意識するのが効果的です。同じテーマについて複数の情報源を突き合わせることで思い込みや見落としを防ぎ、より客観的な視点で技術評価ができます。さらに、内容が専門的になるほど、外部の技術者や研究者の知見を活用して理解を深めていくことも役立ちます。
このような文献調査の結果は、そのまま社内向けの報告書や経営層へのプレゼン資料の土台となります。調査で得られた知識やデータをわかりやすくまとめておくことで、関係者全体の納得感やプロジェクト自体の承認を得やすくなり、次の実証や導入ステップへスムーズに進めるのです。
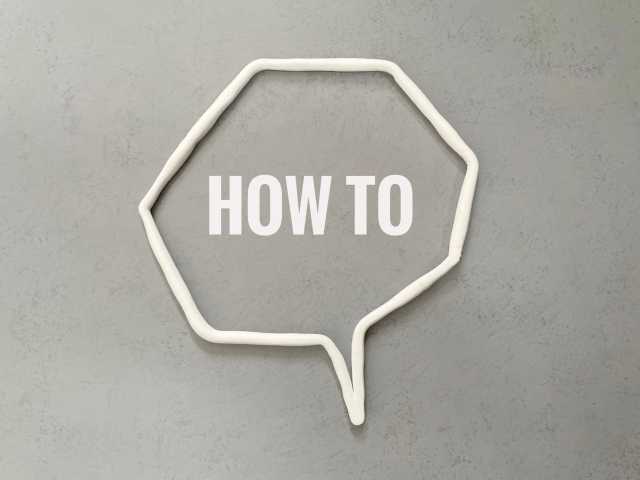
技術探索の真の意義は、未来につながる価値ある技術やアイデアを、社内外の知見や連携を通じて実態に落とし込み、自社の成長や競争力強化に結びつけることです。ツールに頼ったスマートな方法ばかりではなく、時には組織文化や経営戦略に根ざした直感や創造的思考などを大事にすることも必要になるでしょう。
探索活動は、ツールを使いこなすのが偉いのではなく、結果として自社の利益にどう結び付けられるかが重要なのです。ここで、技術探索の意義について、もう少し深く掘り下げていきます。
技術探索の意義は、単に新しい技術を見つけるだけではなく、自社にとって本当に価値のある技術を選び出し、事業の成長や課題解決につなげることにあります。
技術探索には、数多くの専門ツールや膨大なデータベースを利用することが多いですが、ここで注意したいのは、ツールの扱い方を覚えるだけでは十分な成果につながらないということです。高度な検索機能やマッピングツールはあくまでサポートの役割であり、最も重要なのは「どんな技術を探し、なぜそれが必要なのか」という目的意識を持って情報を整理し、実際の業務にどう活かしていくかを考えることです。
また、ツールを使う技術や分析力に加え、企業の組織全体で技術探索に取り組む体制が不可欠です。情報の取捨選択や分析の判断を間違えると、逆に混乱を招きかねません。さらに、ツール自体も日々進歩するため、継続した学習と人材育成が欠かせません。
結局のところ、技術探索の成果は使う人にかかっており、正しい視点と戦略を持ったチームで取り組むことが成功へのカギとなるのです。単にツールを使いこなすだけでなく、目的に沿った分析と組織の連携がなければ、技術探索はうまく機能しません。
技術探索は、固定された方法や枠組みに縛られず、自由で柔軟な発想で進めていくことに意義があります。一般的なフレームワークや標準的な手法は参考になりますが、それに依存しすぎると、新しい発見や独創的なアイデアが生まれにくくなってしまいます。技術探索では、状況に応じて手法をカスタマイズし、時には直感や創造的な考え方も積極的に取り入れることが大切です。多様な情報源やアプローチを組み合わせつつ、社内外の関係者からフィードバックを得て探索方法を柔軟に改善していけば、より良い結果につなげられるでしょう。
また、市場環境や技術の変化に合わせて探索計画を見直すことも欠かせません。これには、短期間で集中的に調査する「スプリント型」の探索を繰り返す方法が効果的です。こうした挑戦と学びを繰り返すことで、組織が持つ探索力が高まり、イノベーションの可能性を広げていけるのです。
技術探索はただの情報収集ではなく、柔軟でクリエイティブな思考と組織的な協力のもとに、最適な方法を模索しながら、価値ある技術を見つけ出すという重要な活動なのです。

技術探索を成功させるためには、何よりもまず「何をどう評価し、どの課題に注力するのか」をはっきりさせることが大切です。ただ漠然と新しい技術を探すのではなく、取り組むべき具体的な課題を明確にし、その課題を解決するための評価基準を設定することが、効率よく有望な技術を見つけ出すコツとなります。
ここでは、技術探索で明らかにしたいポイントや、どのようにして明らかにしていくかを解説します。
技術探索において重要な評価のポイントの一つは、「解決しやすさ」を現実的に見極めることです。課題が極めて難しい場合には、技術的な壁が高く、必要なコストや時間も膨大になりやすいため、短期間で成果を上げるのは厳しくなります。そのため、実現可能性が高い技術やテーマを優先的に選ぶことが、効果的かつ効率的な探索活動の基本となります。
具体的な指標としては、「技術成熟度(Technology Readiness Level:TRL)」がよく用いられます。TRLは技術の開発段階を示す指標で、高い数値ほど実用化に近くなります。例えば、TRLの高い技術は既に実証済みであり、導入後すぐに製品やサービスに反映できる可能性が高いのが特徴です。一方で、新規性や革新性が高い技術は開発・実用化に時間がかかる傾向がありますが、成功すれば大きな競争優位を築ける可能性も秘めています。
また、技術の選定では、既存の技術や社内リソースとの相性も重要です。導入に際してスムーズに運用できるか、コスト面も含めた持続可能性を踏まえた総合的な評価が求められます。こうした多角的な視点で課題を分析・評価しながら、探索テーマを絞り込むことによって、無駄な投資を避け、実践的な成果を目指すことが可能になります。
技術探索において重要なポイントの一つが、自社内の技術力や研究開発能力で課題をどこまで解決できるかを見極めることです。自社の技術テーマに対応できる場合は、外部に頼るよりもノウハウが社内に蓄積されやすく、コスト削減にもつながるため、内製化のメリットが大きくなります。
しかし技術分野によっては、専門知識や特殊な設備・技能が必要な場合も多く、そのような場合は自社だけで開発を進めるのが難しいこともあります。こうした自社だけでの対応が難しい場合は、オープンイノベーションや外部企業、研究機関との共同開発を検討することが重要です。つまり、どこまでを自社で対応し、どの部分をパートナーと協力するかの境界線を明確にして計画を立てることが求められます。
また、自社の技術力だけでなく、マネジメント体制や知的財産の管理体制も技術探索の成否に影響を及ぼします。例えば、プロジェクトの推進力や情報共有の仕組み、知財の保護や活用の体制が整っているかも総合的に評価すべきポイントです。
このように、多方面から自社の対応力を客観的に評価し、「強み」と「外部協力の必要性」を明確化することが、効率的かつ効果的な技術探索を進めるためには必須となります。
技術探索において、「競合が解決できる内容か」を正しく見極めることは極めて重要です。これは、自社が取り組む課題や技術領域の独自性を明確にし、市場で真に競争力を持てるかどうかに直結します。もし競合他社が容易に解決できる技術ばかりを追いかけている場合、差別化ができずに市場での成功は難しくなってしまうでしょう。
そのため、まずは競合他社の研究開発動向や特許申請状況、製品やサービスのラインアップを詳細に調査し、彼らの強みや弱みを把握することが不可欠です。こうした情報収集には、3C分析(自社・競合・顧客の視点で分析)やSWOT分析(強み・弱み・機会・脅威を整理)といったフレームワークを活用し、多角的かつ客観的な視点を持つことが効果的です。
さらに、競合の隙間や市場のニッチを発見できれば、自社が参入可能な独自技術領域や未開拓の特許領域を具体的に抽出できます。これにより、技術探索の焦点が明確になり、リスクを抑えつつ競争優位を築くための戦略的な方向性を立てやすくなります。このように、競合分析を徹底すれば、実際に市場で勝てる技術を見極めることができるのです。
技術探索の成功には、「現状の課題が具体的かつ明確であること」が欠かせません。曖昧な課題設定では、探索範囲が広がりすぎてしまい、無駄な時間やコストがかかるリスクがあります。そのため、現場の実態を調査したり、担当者への丁寧なヒアリングを行ったりして、課題の根本原因や改善すべきポイントを論理的に整理することが重要です。
整理の過程では、どの課題が事業や業務に大きな影響を与えているのかを分析し、それらの優先順位をはっきりさせる必要があります。経営層や研究開発部門といった関連する部署間でこの認識を共有できれば、組織全体で同じ方向を向いて探索活動に取り組めるようになるでしょう。
課題が明確に示されることで、技術探索に割り当てるリソースや時間を効率的に使うことが可能になり、成果が出やすい分野に絞った計画的な活動が進められるようになります。こうした準備が、技術探索の質とスピードを高め、最終的に実用的で価値ある技術の発掘につながっていくのです。

技術探索を成功させるためには、探索対象の市場を的確に設定することが重要です。技術がどの市場に適用可能かを多角的に分析し、市場の成長性や競争環境、自社の強みとの相性などを踏まえて、市場設定を行う必要があります。市場を正しく設定することで、探索の方向性が明確になり、経営資源の効率的な配分と効果的な技術活用を実現できるでしょう。
この章では、自社技術の把握から代替可能な市場の設定、そして市場規模の把握や用途市場の視点について解説します。こうした多面的なアプローチで市場を定義することが、技術探索の成功率を大幅に高めるポイントです。
市場設定の第一歩は、自社が持つ技術の特性や強みをしっかりと把握することです。
具体的には、技術の性能や機能、他にはないユニークな特徴をリストアップし、その技術が顧客にどんな価値やメリットをもたらすのか、利用者の視点で言葉にしていきます。ここで大切なのは、単に技術的に優れていると主張するのではなく、顧客の課題やニーズを解決することに直結した価値に注目することです。そうすることで、その技術の具体的な使い道や市場が明確になってきます。
技術の棚卸しでは、社内の専門家や現場の担当者と何度も話し合い、技術の実用性や適用可能な範囲、現在の開発段階、そして既存の製品やサービスとの差別化ポイントを多角的に評価します。この過程で、市場のニーズとよく合う技術を絞り込むことが重要です。このように、自社の技術の強みを正確に把握することが、市場調査や探索の対象を具体化し、効果的な市場設定の基盤となります。
自社の技術が既存の製品やサービスをどのように置き換えたり改善したりできるかを特定すれば、その対象が現在活用されている市場を知ることができ、どの市場やどの分野にどのような戦略で参入していくかをイメージしやすくなります。
そのためには、まず自社技術が代替可能な既存製品やサービスを洗い出し、これらが展開されている市場をリストアップすることが大事です。このリストアップでは代替対象の商品やサービスの用途、そして顧客層を包括的に把握していきます。例えば、自社の技術が安全性を高める機能を持っていれば、その機能が使われている複数の市場セグメントを調査して、どの市場に参入可能かを検討しましょう。
次に、代替候補の強みや弱みを整理し、自社技術がどの市場で優位に立てるか、または隙間市場を狙えるかを分析していきます。圧倒的な技術優位性がある市場であれば、積極的にその市場を狙う戦略が望ましいです。一方で、競合が多く技術優位性が限定的な場合は、ニッチな領域など競合が薄い市場に参入し、小さくはじめて徐々に拡大していくステップアップ戦略が効果的です。
このように、自社技術の特長や市場特性を掴みながら、代わりとなりうる幅広い市場を設定し細かく分析することが、新たな成長機会を見つけ出すことにつながるのです。
市場設定の精度を高めるためには、まず市場の規模や成長性、競合の状況をしっかり把握する必要があります。それには、市場調査レポート、公的な統計データ、専門の調査機関が提供する情報を利用し、市場ごとに顧客数や売上高、成長率などを具体的に数値化して比較検討するのが有効です。
特に成長率が高い市場は将来性があり魅力的に映りますが、単に大きさや成長だけで判断せず、競争の激しさや参入時のハードルも考慮すべきです。例えば、規制が多い市場や既に多くの競合がひしめく分野では参入が難しい場合もあります。そのため、大規模な市場に加えて、成長が著しい小規模市場や、その技術で特に差別化しやすいニッチ市場の可能性も検討し、リスク分散を図るのが賢明です。
さらに、将来的な技術の進歩や法律・政策の変化など外部環境の動向も織り込んで評価すると、より実効性の高い市場設定が可能になります。こうしてまとめた市場別の分析結果は、探索対象の優先順位決定や戦略立案に役立ちます。このプロセスを通じて、市場の大きさだけではなく「どこにチャンスがあり、どこに課題があるか」を正確に把握し、有望な市場を的確に選び出すことが重要です。
技術の適用可能性は、その使われ方、つまり「用途」によって大きく左右されるため、用途市場を詳細に分析することも重要です。同じ技術でも、用途が異なれば、お客様のニーズや競合の状況、価格帯など市場の性質は大きく変わってきます。
用途市場の分析では、具体的にユーザーがどのように技術を使うのか、どんな目的で導入するのかをしっかり把握することが欠かせません。そのためには現場での調査や顧客へのインタビューなどを通じて、実態に即した情報を集めることが効果的です。こうした現場の声をもとに市場を評価することで、「どの用途なら自社の技術で差別化ができるか」「どの用途から順に参入するのが効果的か」を明確に判断できるようになります。また、用途ごとに最適なパートナーや販売チャネルも異なる場合があるため、それぞれの用途に応じたビジネスモデルの検討も必要です。
このような用途市場視点の分析は、経営層や営業、開発など社内のさまざまな部門との連携を強め、技術探索から事業化へとつなげるための一貫した戦略作りに役立ちます。結果として、より現実的かつ実効性の高い市場展開が可能になるのです。

この記事では、技術探索の方法について、注意点も交えて具体的に解説しました。技術探索は企業の成長や競争力強化に欠かせない重要なプロセスです。幅広い技術情報を戦略的に収集・評価し、自社課題や市場ニーズに合致した技術を見極めることが求められます。
しかし、海外進出や多国籍展開を目指している企業の場合は、現地の市場調査自体が難しいという場合もあるでしょう。そこでご利用いただきたいのが、AXIA Marketingです。AXIA Marketingは世界各地で展開するグローバル企業の市場調査を多数支援しており、アジアから欧米、北中南米まで多地域にわたる詳細なデータ収集と分析を得意としています。現地の生の声を反映し、複雑で多様な国ごとのニーズや競合環境を正確に捉え、クライアントの戦略に合った実行可能な提案を行っています。
弊社サービスや事例について、詳しくは下記公式サイトよりご確認ください。
参考文献
うまく社外の技術を見つける方法(2回目) 2.社外に求める技術の粒度感を調整する(その1)
Copy Link





