
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.09.19


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
ベトナムは近年、急速な経済成長を遂げており、日本をはじめとする各国からの注目を集めています。ASEAN諸国の中でも特に製造拠点としての存在感が高まっており、豊富な労働力や地理的優位性を活かした貿易が盛んに行われています。
その一方で、輸出に関しては規制や関税、必要書類などを正しく理解しておかなければスムーズに取引を進めることができません。
本記事では、ベトナムの基本情報や日本との貿易事情を踏まえたうえで、輸出規制の具体的なポイント、輸出ビジネスのメリット、そして実際に輸出を行う際の流れや関税、必要となる書類について詳しく解説していきます。

ベトナムは東南アジアの中心に位置し、経済成長率が高く、製造業を中心とした産業発展が進んでいます。人口も多く、今後さらなる市場拡大が見込まれている国です。日本にとっても重要な貿易相手国であり、両国の経済関係は年々強化されています。
この章では、まずベトナムの基本的な国情報を確認し、そのうえで日本との貿易事情について詳しく見ていきましょう。
ベトナムは東南アジアに位置し、北に中国、西にラオスとカンボジア、東は南シナ海に面する国です。人口は約1億人に迫っており、その大多数が若年層であることが特徴です。
この豊富な人口は労働力の供給源として強みを持ち、製造業をはじめとする各産業の発展に大きく寄与しています。首都はハノイ、最大の商業都市はホーチミンで、両都市は経済活動の中心地として機能しています。
また、ベトナムは近年、ASEANの中でも特に安定した経済成長を遂げており、2020年代以降のGDPも拡大傾向です。国際的な企業が製造拠点を設けるケースも増えており、輸出における重要なハブとしての存在感が強まっているのです。
農産物や水産物の輸出も盛んで、ベトナム産のコーヒーやエビは世界的に知られています。このような背景から、ベトナムは「製造大国」としてだけでなく「輸出大国」としての地位も築きつつあるのです。
日本とベトナムの貿易関係は非常に良好で、互いに重要な経済パートナーとなっています。日本はベトナムにとって第4位の輸出相手国であり、自動車部品や電気機器、鉄鋼製品などが主な輸出品目です。
一方、ベトナムから日本への輸入は、衣料品や水産物、電子部品などが中心となっていて、特に縫製品や加工食品は日本市場において大きなシェアを占めています。
さらに、両国は経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)を通じて、関税の引き下げや輸入制限の緩和を進めています。これにより、従来よりも低コストかつ効率的に貿易を行える環境が整備されてきました。
特に製造業では、日本企業がベトナムに進出することで現地のサプライチェーンを活用し、コスト削減と供給網の強化を実現しています。このように、両国の経済関係は「相互補完的」であり、今後もさらに拡大していくことが期待されているのです。

ベトナムでビジネスを展開する際には、輸出規制をしっかり理解しておくことが重要です。ベトナム政府は国の安全保障や経済政策の観点から、輸出に一定の規制を設けています。
これらの規制を無視すると、通関でのトラブルや取引停止といったリスクに直結するため、事前に確認しておく必要があります。本章では、代表的な「リスト規制」と「キャッチオール規制」について解説し、企業が取引を円滑に進めるための基本的な知識を整理していきましょう。
リスト規制とは、特定の品目について輸出を制限する制度を指すものです。ベトナムでは、軍事転用が可能な製品や、戦略物資と位置づけられる品目について規制がかけられています。例えば、武器や弾薬、軍事機器はもちろん、化学薬品や特定の電子機器なども対象になる場合があります。
リスト規制の対象品目は定期的に更新されるため、企業は常に最新の情報を確認することが求められるのです。特に日本からベトナムに対して機械や電子部品を輸出する企業は、輸出管理令や関税局の発表をチェックしておくことが必須です。
また、リスト規制は国際的な安全保障の枠組みと連動しているため、ベトナム国内の規制だけでなく国際協定にも影響を受けます。そのため、企業は国内外の制度を総合的に理解して輸出計画を立てる必要があります。
こうした点を踏まえれば、リスト規制は単なる「障壁」ではなく、適切に対応すればリスクを最小化できる重要な仕組みだと言えるでしょう。
キャッチオール規制は、リスト規制に含まれていない品目であっても、用途や取引相手によって輸出が制限される制度を指します。つまり「リストにないから安心」とは言えず、最終的な使用目的や輸出先企業の性質によっては、規制の対象となる可能性があるのです。
この規制の背景には、大量破壊兵器や軍事利用への転用を防ぐという国際的な目的があります。例えば、通常は民生用途で使われる化学物質や電子部品でも、軍事開発や武器製造に利用される恐れがある場合は輸出が制限されるのです。
キャッチオール規制の難しさは、判断基準が「品目」ではなく「用途と相手」にある点です。場合によっては政府への相談や許可申請が必要になることもあり、企業には高いコンプライアンス意識が求められます。
実務的には、輸出管理部門を設けて社内ルールを整備する、または専門コンサルタントや弁護士に相談するなど、体制づくりが推奨されます。軽視すれば思わぬリスクに直面する可能性があるため、リスト規制と合わせて理解し、実務に反映させることが成功の鍵と言えるでしょう。

ベトナムで輸出ビジネスを展開することには、多くの魅力があります。経済成長が続く同国では、製造業や貿易分野が拡大しており、日本企業にとって進出のチャンスが広がっているといえるでしょう。
特に注目されるのは「豊富な労働力」「物流上の有利な立地」「日本との良好な関係」という3つの点です。これらは単なる一時的な利点ではなく、長期的に見てもビジネスの基盤を支える強みとなります。それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
ベトナムの最大の強みの一つは、豊富で若い労働力です。人口は約1億人に迫り、その半数近くが35歳以下という構成になっています。特に製造業や加工業に必要な現場労働者が安定して確保できる点は、海外企業にとって大きな魅力です。
賃金水準も他のアジア諸国と比べてまだ比較的低く、タイや中国の都市部に比べても人件費を抑えられる傾向です。これにより、コスト競争力を高めつつ高品質な製品を生産することが可能になります。
さらに、ベトナム人は勤勉で手先が器用と評価されることが多く、縫製業や電子部品の組み立てといった精密な作業にも最適です。国としても教育水準の向上に力を入れているため、今後は技術者層の拡充も進むと見込まれています。
こうした労働力の安定供給は、生産コストの削減だけでなく、長期的な事業展開における安心材料ともなります。そのため、豊富な労働力はベトナム輸出ビジネスを行う上で最大級のメリットといえるでしょう。
ベトナムは地理的に東南アジアの中心に位置し、物流面で大きな優位性を持っています。北は中国、南はASEAN主要国に接しており、陸路・海路・空路のいずれを使っても近隣諸国との取引がしやすい環境です。
近年はインフラ整備が急速に進み、道路や港湾、空港の拡張が積極的に行われています。これにより輸送のリードタイム短縮やコスト削減が実現し、グローバルサプライチェーンに組み込みやすくなっています。ASEAN自由貿易協定(AFTA)などの枠組みも後押しとなり、関税削減や通関手続きの簡素化が進んでいる点も見逃せません。
実務的には、ベトナムを生産拠点にしつつ、周辺諸国へ輸出する「ハブ戦略」が有効です。例を上げると、中国市場やASEAN市場に向けて効率的に製品を届けることができ、輸出ビジネスの拡大に直結するため、日本企業にとっては調達・生産・販売を一体的に構築できるロケーションとして大きな魅力を持つのです。
物流上の利便性とインフラ改善は、輸出ビジネスを支える重要な基盤となっており、ベトナムの競争力をさらに高めています。
ベトナムと日本は政治的にも経済的にも非常に良好な関係を築いており、これが輸出ビジネスを後押しする大きな要因となっています。両国は長年にわたり友好関係を維持しており、日本はベトナムにとって最大級の投資国の一つです。日本政府もODA(政府開発援助)を通じてインフラ整備や教育支援を行い、両国間の信頼関係を深めているのです。
経済面では、日越経済連携協定やCPTPP(包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定)などの枠組みにより、貿易・投資環境が整備されています。これにより日本企業は輸出入に関するコストを抑えつつ、安定的にビジネスを展開できる環境を手にしました。
ベトナム国内では日本製品に対する信頼度が高く、品質や安全性に優れた製品は現地市場でも歓迎されます。ブランド力の高さは輸出企業にとって大きな武器となりますし、両国間の人材交流も活発で、日本語を学ぶ若者が増えている点もビジネスの円滑化につながっています。

ベトナムへ製品を輸出するには、契約から輸送、そして代金の支払いまでいくつかのステップを踏む必要があります。これらの流れを正しく理解しておけば、スムーズな貿易取引が可能になるのです。
ここでは「売買契約の締結」「輸送の手配」「料金の支払い」の3段階について、実務的な観点から詳しく解説していきます。
輸出ビジネスにおいて最初に行うべき重要なステップが、売買契約の締結です。この契約は単なる取引の約束にとどまらず、輸出入におけるリスクを軽減するための法的根拠となるものです。
売買契約書には、品目・数量・価格・納期・品質基準・クレーム対応・仲裁機関などを明記する必要があります。特に国際取引では「インコタームズ(国際商業会議所が定める貿易条件)」を利用するのが一般的で、輸送費や保険料、通関費用などの負担をどちらが負うのかを明確にしておくことが重要です。
契約には支払い条件を必ず盛り込みましょう。信用状(L/C)決済、前払い、後払いなど、相手先の信用度や取引実績に応じて選択するのが基本です。信用度の低い相手に後払いを認めてしまうと、代金回収が困難になるリスクもあるため慎重な判断が求められます。
加えて、言語の壁や文化の違いから誤解が生じやすい点にも注意が必要です。英語をベースとした契約書を準備する、専門の法律事務所や貿易コンサルタントにチェックを依頼するなど、第三者のサポートを受けることでリスクを大幅に減らすことができます。
売買契約が締結されたら、次は商品の輸送を手配する段階です。ベトナムへの輸送手段は主に海上輸送と航空輸送があり、製品の種類や数量、納期に応じて選択されます。大量の製品を輸送する場合はコスト効率の高い海上輸送が一般的ですが、緊急性が高い製品や高付加価値品は航空輸送が選ばれるケースもあるでしょう。
輸送を行う際には、信頼できるフォワーダー(国際貨物取扱業者)の選定が重要です。フォワーダーは輸送手段の手配だけでなく、通関書類の準備や保険加入、スケジュール管理まで幅広くサポートしてくれる存在です。
輸送では、梱包方法やパッキングリストの内容もポイントになります。湿度が高いベトナムでは、製品が劣化しないように防湿・防錆対策を講じることが欠かせません。積み下ろしの際の破損を防ぐために丈夫な梱包を行い、国際規格に準拠したラベル表示を行うことも必須です。
輸送中のリスクを補償する貨物保険の加入も忘れてはなりません。輸送トラブルによる損失は企業にとって大きな痛手になるため、保険でカバーしておくことが安全な取引につながります。
輸送が完了すると、次は代金の支払い手続きに移ります。国際取引における支払い方法は大きく分けて「信用状(L/C)決済」「送金決済」「前払い・後払い」の3種類があり、それぞれにメリットとリスクがあります。
もっとも一般的で安全性が高いのは信用状決済です。銀行が支払いを保証する仕組みで、輸出者にとっては代金回収のリスクを大幅に軽減できます。ただし、手数料がかかるためコスト面の負担がある点は注意しましょう。
送金決済は相手先企業を信頼できる場合に用いられる方法で、手続きが比較的シンプルです。しかし、代金の未払いリスクが残るため、長年の取引関係や信用調査を前提とするのが一般的です。
少額取引や初回取引では前払いが求められることもあります。逆に、強い交渉力を持つ買い手からは後払い条件を提示されるケースもありますが、リスクが高いため十分な検討が必要と言えます。

ベトナムへ製品を輸出する際には、関税の仕組みを理解しておくことが必要不可欠です。ベトナムはWTO加盟国であり、ASEAN自由貿易協定(AFTA)や日越経済連携協定(EPA)、CPTPPなど複数の国際協定に参加しています。そのため、協定に基づいた優遇関税率が適用されるケースが多く、日本企業にとっては輸出コストを抑えやすい環境です。
ベトナムの関税率は0〜40%の幅で設定されており、品目によって大きく異なります。具体的な例として、工業製品や電子部品などは比較的低率で輸入される一方、農産物や特定の消費財には高い関税がかかることもあります。
さらに、関税以外にも付加価値税(VAT)や特別消費税(SCT)が併せて課される場合があるため、実際の負担額は単純な関税率以上になることがあります。そのため、事前に対象品目の税率を確認し、必要な書類を揃えることが求められます。
ベトナム関税総局や現地のフォワーダー、税務コンサルタントを活用することで、最新情報に基づいて対応できるでしょう。関税制度を正しく理解し、優遇措置を最大限に活用することが、輸出コストの削減と利益確保につながるのです。
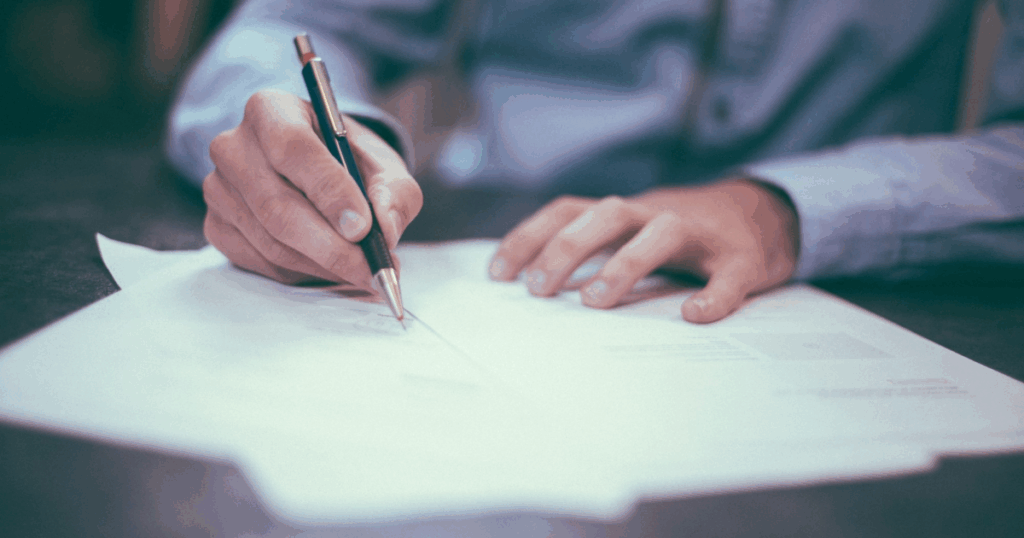
ベトナムへ輸出する際には、複数の書類を準備しなければなりません。通関手続きは書類の正確さに大きく左右されるため、不備があると貨物の遅延や追加コストの発生につながります。
ここでは代表的な「輸出申告書」「インボイス」「委任状」「パッキングリスト」「船積依頼書」について、それぞれの役割と注意点を詳しく解説していきます。
輸出申告書は、輸出貨物の内容を税関に申告するための最も基本的な書類です。ここには輸出者・輸入者の情報、貨物の品目コード(HSコード)、数量、価格、輸送手段などが記載されます。
特に注意すべきはHSコードです。誤ったコードを使用すると税率が変わる可能性があり、最悪の場合は通関遅延や罰金につながりますから、実務上は専門の通関士やフォワーダーと相談し、最新のコード体系を確認することが推奨されます。
また、輸出申告書はベトナムでは電子申告システムを通じて提出されることが多く、オンラインでの処理が主流になっています。日本側で書類を作成する場合も、現地代理人や通関業者と連携して正確な情報を反映させることが欠かせません。
インボイス(Commercial Invoice)は、輸出者が輸入者に対して発行する請求書の役割を持つ書類です。商品名、数量、単価、合計金額、支払い条件などが記載され、輸出入取引の基礎資料として扱われます。税関にとっては取引の正当性や課税額を確認する重要な手がかりとなります。
特に注意したいのは「金額の一致」です。インボイスに記載された金額と、契約書やL/C(信用状)の金額が異なっていると、通関で不審な書類として手続きがストップする恐れがあります。これを防ぐため、契約内容とインボイスを常に照合し、矛盾がないように管理することが求められるというわけです。
インボイスには取引条件(インコタームズ)も記載する必要があります。CIFやFOBなどの条件によって輸送費や保険料の負担者が異なるため、誤記載があると追加コストが発生しかねません。輸入者側が金融機関を通して送金する際にもインボイスが必要となるため、正確で信頼性の高い内容が求められます。
委任状は、輸出者が通関手続きをフォワーダーや通関業者に代行依頼する際に必要となる書類です。輸出者が直接現地で通関手続きを行うことは難しいため、多くの場合は委任状を作成して代理人に業務を任せます。
委任状には、輸出者と代理人の名称・住所・連絡先、委任する業務の範囲、委任期間などを明記します。記載内容に不備があると代理手続きが認められず、通関が遅延してしまうため、正確さが求められるのです。
ベトナムでは通関業務を行えるのは認可を受けた通関業者に限られているため、代理人を選ぶ際にはライセンスの有無を確認することが重要です。信頼できる代理人に業務を委任すれば、通関の効率化やリスク回避につながります。
委任状は一見形式的な書類に思えますが、実際には通関の成否を左右する大切な書類です。輸出者は必ず内容を確認し、代理人と密に連携を取ることで、スムーズな輸出を行えるでしょう。
パッキングリストは、貨物の梱包内容を詳細に記載した書類であり、輸送や通関で不可欠な役割を果たします。具体的には、梱包ごとの品目、数量、重量、サイズなどが記され、貨物の検査や仕分けに活用するものです。
税関はパッキングリストをもとに貨物の実物と書類内容を照合し、不正がないかを確認します。もし記載と実際の貨物に差異があれば、通関がストップしたり追加検査が入ったりするため、正確性が特に重要です。
また、輸送業者にとってもパッキングリストは重要です。貨物の重量や体積を基準に運賃が算出されるため、正確な情報が記されていないと料金トラブルの原因となります。さらに、荷受人が貨物を受け取る際にもパッキングリストは確認資料として機能します。
梱包が複数に分かれる場合は、それぞれの内容を明細化し、合計数量や重量と一致しているかを必ず確認しましょう。パッキングリストは通関の円滑化だけでなく、物流全体をスムーズに進めるための基本書類です。
船積依頼書(Shipping Instruction, SI)は、輸出者がフォワーダーや船会社に対して貨物の輸送を依頼するための書類です。ここには貨物の詳細情報、積み込み港と仕向港、希望するスケジュール、運賃条件などが記載されます。
船積依頼書は、最終的に発行される船荷証券(B/L)や航空運送状(AWB)の基礎となるため、内容の正確さが非常に重要です。記載内容に誤りがあると、輸入側での貨物引き取りができなくなるなど大きなトラブルに直結します。
船積依頼書を提出するタイミングにも注意が必要です。遅れると希望の船便や航空便に積載できず、納期に影響する可能性があります。特にベトナム向けは需要が多いため、早めに予約と依頼を行うことが安全です。
貨物に特殊条件がある場合(危険物や冷蔵品など)は、船積依頼書にその旨を明記しなければなりません。これを怠ると輸送中の事故や保険の不適用につながるリスクがあります。
船積依頼書は「輸送を正式に依頼するための起点」となる書類であり、輸出者の責任を明確化する役割も担っているため、正確かつスピーディーに作成することで安定した輸送を実現できるでしょう。

ベトナムでは、経済発展を支えながらも国民の安全や環境保護を目的として、特定の品目について輸入規制や禁止措置を設けています。輸出ビジネスを検討する際には、これらの規制対象品を把握しておくことが重要です。
具体的に輸出できない品目としては、銃器や爆発物といった武器類、さらには軍事転用可能な特定の機材が挙げられます。また、花火各種や電化製品、中古のIT商品や電気冷蔵機などの中古消費材も規制対象です。
これらの規制に違反した場合、貨物は没収されるだけでなく、輸出者に罰金や取引停止といった厳しい処分が科されるリスクがあります。そのため、輸出を行う前には必ず最新の規制リストを確認し、専門の通関業者や現地代理人と連携して安全に手続きを進めることが大切です。
ベトナム市場は大きな魅力を持つ一方で、輸出禁止品のルールは厳格です。事前の調査と準備を怠らないことが、長期的なビジネスの安定につながります。

ここまでご説明してきた通り、ベトナムは、ASEAN諸国の中でも経済成長率が高く、人口構成が若年層中心であることから、日系企業にとって非常に魅力的な進出先です。加えて、政府の外資誘致政策や自由貿易協定(FTA)による関税優遇など、ビジネス環境も整備されています。
本章では、代表的な3社の事例を紹介し、どのようにして現地市場で成果を上げたのか、その戦略や取り組みを詳しく解説します。

ニトリは、ベトナム市場における家具・インテリア事業で成功を収めました。2025年時点で15店舗以上を展開しており、10年間で70店舗まで拡大することを目標にしています。ホーチミン市やハノイ市の主要ショッピングモールに出店し、日本品質の家具を現地の住環境や消費者のニーズに合わせて提供する戦略が功を奏しています。
特に成功のポイントは、ベトナム消費者のライフスタイルに合わせた商品ラインナップと現地スタッフによる販売戦略です。現地文化や好みを徹底的にリサーチし、家具のサイズやデザイン、機能性を日本本社と連携して調整しているのです。
オンライン販売にも注力しており、ECサイトと店舗を連携させたオムニチャネル戦略を展開しました。これによって、都市部だけでなく郊外や地方に住む消費者にもアクセスでき、ベトナム国内でのブランド認知度を高めています。
このような総合的な戦略により、ニトリは短期間で市場に根付き、安定した売上を確保できる体制を構築しています。

住友電装は、自動車用ワイヤーハーネスの製造拠点として2013年にハノイ近郊に工場を設立しました。同社の成功要因は、単に低コスト生産にとどまらず、現地従業員のスキル向上と品質管理の徹底にあります。
「モノづくりは人づくり」を理念として掲げ、現地の技術者教育プログラムを充実させ、社員が主体的に品質改善や生産効率向上に取り組める環境を整えています。
日本本社と現地工場の情報連携を強化し、工程改善や不良品削減のためのPDCAサイクルを迅速に回しています。これにより、日本品質を維持しながらベトナムの低コストを活用するバランスの取れた生産体制を確立しました。
これに加え、現地の自動車メーカーとのネットワークを活用して安定した受注を確保しており、地場企業とのパートナーシップも成功の鍵となっています。

FPTジャパンホールディングスは、ITサービス・ソリューション提供でベトナム市場に進出しています。同社の特徴は、日本語能力の高いエンジニアを育成し、ブリッジSEとして日本企業との開発案件を円滑に進められる体制を整えている点です。
日本側とベトナム側のコミュニケーションコストを大幅に削減でき、高品質な開発を短期間で提供することが可能になっています。単なる低コストのオフショア開発にとどまらず、AI・DXなど高付加価値領域にも進出しました。
現地での人材育成と高度な技術提供を組み合わせることで、クライアント企業の課題解決に直結するソリューションを提供しています。ベトナム政府や地元教育機関と連携し、IT人材の教育・採用体制を強化している点も、持続的成長につながっているといえるでしょう。

ベトナム市場は、安定した経済成長と若い労働力、地理的優位性など、多くの魅力を持つ進出先です。しかし、成功するためには市場調査が欠かせません。消費者の嗜好や購買力、競合企業の動向、輸出規制や関税などの法規制を正確に把握することが必要です。
事前にしっかりと情報を収集・分析することで、適切な商品戦略や販売戦略を立てることができ、リスクを最小化できます。もちろん、現地パートナーや専門家との連携も成功の重要なポイントです。
市場調査を基盤に進出計画を立てることで、長期的な安定成長と利益確保を実現できるでしょう。

ベトナムには輸出規制はあるものの、海外進出としては大変魅力的な国であることをご説明してきました。
AXIA Marketingは、ベトナム市場に特化したマーケティング調査・コンサルティングサービスを提供しています。現地の消費者動向や競合分析、業界トレンドなどを詳細にリサーチし、日本企業が現地市場で成功するための戦略立案をサポートします。
ベトナム特有の商習慣や規制情報も踏まえた提案を行うため、リスクを最大限抑えながら効率的な進出が実現できます。詳しくは公式サイトよりご確認・ご相談ください。
参考文献
【徹底解説】ベトナムへの輸出ビジネスのメリットと必要な手続きとは?
ベトナムに進出した日系企業の事例から学ぶ|成功の共通点とは?
Copy Link





