
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2024.06.30


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
企業にとって、自社の保持する知的財産を競合他社の侵略から守り、更なる市場拡大を目指すための戦略を構築することは非常に重要です。
この記事では、知的財産戦略(知財戦略)の背景と意義、必要性やメリット、フレームワークの設定とポイントなどについて詳しく解説します。新規参入や事業拡大に成功した企業例も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
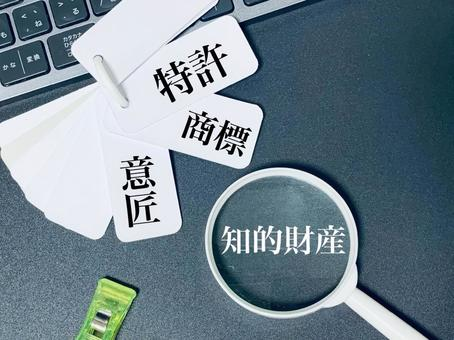
企業や人間が幅広い知的活動を行う際に産み出すアイデアや創作物は無限大です。
このうち、財産的な価値をもつものを「知的財産」と呼び、「知財(ちざい)」と略されます。この知財に法律で独占権を与えたものが「知的財産権」です。
これを細分化すると、様々なビジネスに深く関わるのが特許権(発明)・実用新案権(考案)・意匠権(デザイン)・商標権(ブランド)の4つとなり、総じて「産業財産権」と呼ばれ、特許庁で所管しています。
知的財産戦略とは、企業が既存市場の拡大や新たな市場開拓を目指し、競合他社の知的財産権の状況を把握しながら、自社の戦略を立案することを指します。
具体的には、事業戦略を実行するために必要な開発を検討する段階で、競合他社の知的財産権を把握して、独自の開発戦略を立てる行為となります。
その結果、差別化した自社独自の成果に対して知的財産権を確立・活用し、市場を獲得することになります。
総じていえば、企業が自社の知的財産権を武器として、競合他社の市場介入を阻止し、市場のシェアを獲得・拡大して事業拡大を目指すものです。
先行き不透明な国内外の社会・経済情勢の変化に伴い、わが国における産業の国際競争力強化を図る必要性が増大しています。
こうした状況に鑑(かんが)み、知的財産の創造・保護と活用に関する施策を計画的に推進することを主な目的として、平成15年3月に首相官邸が内閣に知的財産戦略本部を設置しました。
知的財産とは、人や企業がさまざまな創作活動を通じて生み出す、財産価値を有するもので、有形ではない無体物(形を持たないもの)です。
ここ最近、企業価値に占める無形資産の割合が増大しており、こうした知的財産を活用することが企業経営を行う上でますます重要となっています。
調査に特化している弊社では、知的財産に関する支援をさせていただいております。お気軽にお問い合わせください。
知的財産戦略は経営戦略の一部として位置付けることが重要です。経営戦略が企業の方向性や目標を定めるのに対し、知財戦略はそれを具体的に支える手段として機能します。
例えば、新製品の開発や海外市場への進出を目指す場合、特許や商標の活用方法を事前に計画することで、競合他社との差別化を図り、市場参入のリスクを低減できます。
また、知財戦略は単独で成果を上げるものではなく、研究開発や営業、マーケティング、法務部門などとの連携が不可欠です。各部門が協力し、知財の創出から権利化、活用までのプロセスを統合的に管理することで、経営戦略全体の実現可能性を高められます。
経営層が知財戦略を理解し、意思決定に反映させることが、戦略的な知財活用には欠かせません。

知的財産は取得して終わりではなく、企業の成長や事業展開に沿った形で活用することが重要です。そのためには、単なる権利管理ではなく、戦略的に運用するためのポイントを理解しておく必要があります。
知財戦略を効果的に進めるためには、現状の把握から戦略の策定、体制整備、そして情報開示まで、段階ごとに整備していくことが求められるのです。以下では、企業が知的財産を最大限活かすための具体的な5つのポイントについて詳しく解説していきましょう。
知的財産戦略を立てるうえで最初に行うべきは、現状の把握と分析です。自社が保有する特許、商標、意匠、著作権などの知的財産の種類や数、そしてそれらの有効性や競争力を評価することが重要です。
競合他社の知財動向や市場における技術トレンドの分析も欠かせません。自社の強みや弱みを客観的に把握することで、戦略策定の基盤が築かれます。知財ポートフォリオの中で活用されていない権利や、更新・維持管理が不十分なものがあれば、それを整理して将来の活用可能性を見極めることも必要です。
この段階での分析が不十分だと、後の戦略が現実に即さず、無駄なコストやリスクを抱えることにつながります。そのため、現状把握と分析は戦略の土台として最も重要なステップです。
知的財産戦略は単独で考えるのではなく、企業全体の経営戦略と密接に連動させることが重要です。製品開発や市場展開、事業拡大の方向性に合わせて知財をどのように活用するかを検討することで、企業の競争力を高める効果が期待できます。
例として、新規技術を開発する際には、将来的な特許取得や技術保護の観点を事前に計画し、市場投入のタイミングや競合対策を考慮することが求められます。また、海外展開を視野に入れる場合は、各国の知財制度や特許戦略も考慮しなければなりません。
経営戦略との連動がうまくいくと、知財を単なる権利として持つのではなく、売上や事業成長に直結する重要な経営資源として活用できます。そのため、経営層と知財部門の連携が不可欠です。
現状分析と経営戦略との連動ができたら、次は具体的な知財戦略の策定に移ります。戦略策定では、どの知的財産を取得・維持し、どのように活用するかを明確に決めることが重要です。
具体的には、新製品やサービスに関する特許出願の優先順位を決めたり、競合が模倣できない技術の保護を強化したりします。また、知財のライセンス活用や共同開発契約など、権利の活用方法も戦略の一部として検討したり、リスク管理として他社特許の侵害リスクや訴訟リスクを分析して対策を講じることも不可欠でしょう。
戦略策定は単なる書面作成ではなく、実行可能でかつ柔軟性のある計画を立てることがポイントです。こうした対策によって、知財が企業の競争力強化に直結する形で活用できるのです。
知的財産戦略を効果的に実行するには、社内の体制整備が欠かせません。知財担当者だけでなく、研究開発部門、営業部門、経営層が連携できる組織体制を構築することが重要です。
具体的には、知財の出願・管理・活用を一元的に管理する体制や、経営会議に知財戦略を反映させる仕組みが求められます。また、知財教育や社内研修を通じて、社員全体の知財意識を高めることも有効です。
体制が整うことで、権利取得の漏れや管理ミスを防ぎ、戦略の実行力を高めることができます。さらに、情報共有や意思決定のスピードが向上するため、迅速な市場対応や競合対策も可能となります。
知的財産戦略の最後のポイントは、適切な情報開示です。特許や商標の取得状況、ライセンス契約や技術の優位性について、ステークホルダーに対して透明性を持って伝えることは、企業価値の向上につながります。
例えば、投資家や取引先に対して、自社の知財ポートフォリオの強みや戦略的活用方針を説明することで、信頼性を高めることができます。また、公開情報を通じて競合企業に対する抑止力を持たせることも可能です。さらに、知財情報の適切な管理・開示は、訴訟リスクや権利侵害の予防にもつながります。
情報開示は単なる報告ではなく、戦略の一環として企業のブランド力や競争力を強化する重要な手段でもあると言えるでしょう。

知財戦略を実効性のあるものにするためには、企業内の体制づくりが不可欠です。体制づくりとは、知財を管理・活用するための組織構造や運用ルールを整備することを指します。
企業規模や事業内容によって体制は異なりますが、共通して求められるのは、権利の取得や管理、活用方法を明確化し、社内全体で共有できる仕組みを整えることです。体制が整うことで、知財の有効活用だけでなく、権利侵害リスクの回避や新規事業開発の加速にもつながります。
知財戦略の体制構築において最も重要なのは、組織の役割や責任を明確にすることです。
具体的には、知財の取得を担当する部署、活用方法を検討する部署、権利侵害リスクを管理する部署などを明確に分け、それぞれの業務範囲や責任を定めます。また、情報の共有方法や意思決定フローも明確化することで、社内での連携がスムーズになります。
体制は固定的なものではなく、事業環境や市場動向に応じて柔軟に見直すことが求められるでしょう。新たな技術や事業が生まれた場合には、既存の体制が適応できないケースもあるため、定期的なレビューや改善が不可欠です。
適切な体制づくりにより、知財の取得や活用を戦略的に進めることが可能となります。
知財戦略を実行する上では、費用や条件、期間の把握が欠かせません。特許や商標の出願には費用が発生するだけでなく、権利化までには数か月から数年単位の時間が必要です。また、維持費や更新費用も発生するため、計画的な資金配分が求められます。
各国での権利取得条件や審査基準は異なるため、海外展開を考える場合は現地の法制度や手続きを把握することも重要です。条件や期間を正確に管理することで、権利取得の遅延や費用超過のリスクを抑え、知財戦略を効率的に進められます。
こうした対策によって、企業は無駄なコストを削減し、戦略的な知財活用を実現できるというわけです。
知財戦略の実効性を高めるには、社内教育や啓蒙活動も欠かせません。知財の重要性を社員一人ひとりが理解し、日常業務に知財意識を取り入れることで、戦略の成果が大きく変わるのです。
例を出すと、開発部門が新技術を創出する際に特許取得の視点を持つことで、権利化の機会を逃さずに済みますし、営業やマーケティング部門も商標や著作権の活用方法を理解することで、ブランド価値を最大化できます。
加えて、定期的な研修や情報共有の場を設けることで、知財に関する最新情報や成功事例を社内で共有できます。全社員が戦略的に知財を活用する文化を醸成でき、長期的な競争力の向上につながるのです。

知的財産を活用するには、効果的・効率的なフレームワークを策定することが重要です。
知的財産戦略を成功させるには、計画段階から実行までのフレームワークを明確にすることが不可欠です。単に権利を取得するだけではなく、企業の事業戦略と整合性を持たせ、リスク管理や収益最大化を図る必要があります。
フレームワークを体系的に整備することで、知財戦略はより実効性のあるものとなるのです。ここからは、フレームワークの策定とポイントについて解説します。
知的財産を活用するため、次のようなフレームワークを策定します。
自社の事業内容や経営情報などに基づき、まずは自社の現状分析を実施します。
その際には、有名な分析手法として知られるSWOT分析(*)などのフレームワークを活用して自社事業の状況を分析するのも方策です。
こうしたフレームワークを用いることで、自社の強みや弱み、また市場進出のチャンスなどのポイントを明確化できます。
(*)自社のおかれた状況について、強み(Strength)・弱み(Weakness)・機会(Opportunity)・脅威(Threat)の4項目をマトリックス化して分析する方法
その上で、自社が保有するアイデアやコンセプトが商業的に応用可能かどうか確認し、知的財産として登録可能か判断します。
自社が保有している知的財産に関する評価を行います。
自社が提供する製品・サービスやノウハウに関する知的財産が市場でどのような位置付けにあるのか確認するとともに、競合他社の知的財産保有状況を調査します。
こうした調査を通じて競合企業を特定し、業務全般および知的財産戦略を考慮して、該当する製品やサービスの開発を実施します。
自社の知財・無形資産に対する投資の必要性を判断し、自社の知財・無形資産を支えるビジネスモデルを保護するために取るべき具体的な方策について、戦略的な知財マネジメントを実施します。
その上で、自社が保有する知的財産に対する適切な保護戦略を特定します(特許・営業秘密や意匠・商標、オープンソースなどの知的財産)。
自社が直面する経営環境を分析し、経営課題を明確化した上で、投資すべき重点分野を決定した後は、商業化と市場化へと進めていきます。
経営資源は限定されているので、「メリハリ」をはっきりさせた知財活動を行うことが重要です。自社の価値観や価値創造を意識したビジネスモデルを検討し、その中で、知財・無形資産が生み出す機能と役割を明確化します。
そして、自社が所有する商品・サービスについて適切なブランド化を実施し(商標、包装、ウェブサイト、ドメイン名など)、商業化を図ります。

知的財産は単なる権利として保有するだけでなく、事業価値に直結させることが重要となります。現状の把握や経営戦略と連動させ、総合的に運用することで、知財を戦略的に活用し、競争優位性を高めることができます。
知的財産を活用するためのポイントは次のとおりです。
上述のとおり、自社が現在保有する知的財産を定期的に把握し、更には「見える化」に至るまで可視化することで、自社技術の現状を正確に把握することが重要です。
自社が持つ複数の知的財産に関するポートフォリオを作成することで、保有知財の相対価値や、競合他社との差異が可視化され、市場における自社のポジションが明確化されます。
企業の知財戦略と経営戦略とは密接に関連しています。通常、知財戦略は企業における経営戦略の一部として位置付けられていますが、経営戦略の中でそれぞれの機能別戦略に関する方向性を決定する重要な役割を果たしています。
知的財産を権利化するだけではなく、自社の経営戦略や事業戦略との整合性を図り、事業に必要な技術やビジネスモデルを確認し、連動させることがポイントです。
知財戦略の策定にあたっては、特許や商標・意匠、ノウハウやブランドなど、知的財産や無形資産活用の要素を取り込むことが重要となります。
長期間にわたって自社の商品・サービスの価値を維持するためには、戦略を策定した上で、競合他社との差別化と競争優位性を確保することがポイントとなります。
知財情報を組み込んだ経営・事業情報を分析することで、自社の強みをより客観的・相対的に認識できます。
知的財産を活用し、事業運営を万全とするためには、適切な任務遂行が可能な組織体制の構築がポイントとなります。
自社の知財部門が持つ機能を整備し、それぞれの役割を明確化した上で、業務遂行が可能な体制を築くことが重要です。
知的財産戦略を実行すると同時に、自社の強みを開示することが重要です。
また、自社の強みをアピールすることにより、ステークホルダーや関係者を包含した企業価値の向上を図ることがポイントです。
全ての企業における経営戦略に共通する目標として、投資からより多くの収益を得ること、つまり利益を最大化することが最大の使命です。
特に技術系の企業では、研究開発に関する投資から生じた知識をいかに収益に結びつけるかが成功のポイントです。
知的財産権は、自社が生み出した知識を権利として確保し、事業を保護・拡大するための重要なツールとなります。
利益の源泉であるコア技術を独占しながら、周辺領域の技術を広くライセンス化して普及促進を図ることがポイントです。
知的財産権の中でも主要な権利である産業財産権ですが、権利に必要な費用はさまざまです。
自社が開発した新製品や技術に関する費用について、しっかりと把握することが重要です。
特許出願に際しての具体的な費用項目と費用の目安は下表のとおりです。
知財戦略の調査を依頼する際には、各機関・各会社により費用感には幅がありますので、実際の調査にあたっては個別・具体的に確認が必要です。

近年、開放特許(オープン特許)を活用した知的財産戦略が注目されています。開放特許とは、自社の特許を一定条件で他社が利用できるよう公開する仕組みであり、技術の標準化や市場拡大に寄与する要素の1つです。
開放特許の利点は、単に自社の技術が広まるだけでなく、ライセンス料収入や他社との共同開発による新規事業創出も期待できることや、企業全体の競争力を高めるとともに、技術力やブランド価値の向上にもつながるといった点が挙げられます。
ここからは、開放特許の活用と知的戦略の活用について解説します。
知的財産権には一定の「独占権」が与えられています。
その一方、国内の特許の利用率は約5割程度であり、半数の特許が使われていない現状があります。
こうした状況下、特許権の有効利用を進める方法として「開放特許」が挙げられます。
開放特許とは、「特許権のライセンス付与や権利譲渡を希望する特許権者が一般に開放している特許」を指します。
具体例を1つ挙げます。
ある金属加工企業は、抗菌めっき技術に関する研究開発を進めていました。
中小企業のため経営資源が不足しており、大手製鉄メーカーの開放特許のライセンス供与を受けました。現在、同社では当該特許を利用し、医療機器メーカーなどに新製品の提案を進めています。
このように、開放特許を活用することで研究開発の時間が短縮され、開発費用も低減できるメリットがあります。
また、自社が使用してない特許を開放特許として公開することで、ライセンス料収入などが期待できます。
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営する「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」では、特許庁が所管する産業財産権の検索が可能となっています。
詳しくは下記サイトをご参照ください。
参照:特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) 公式サイト
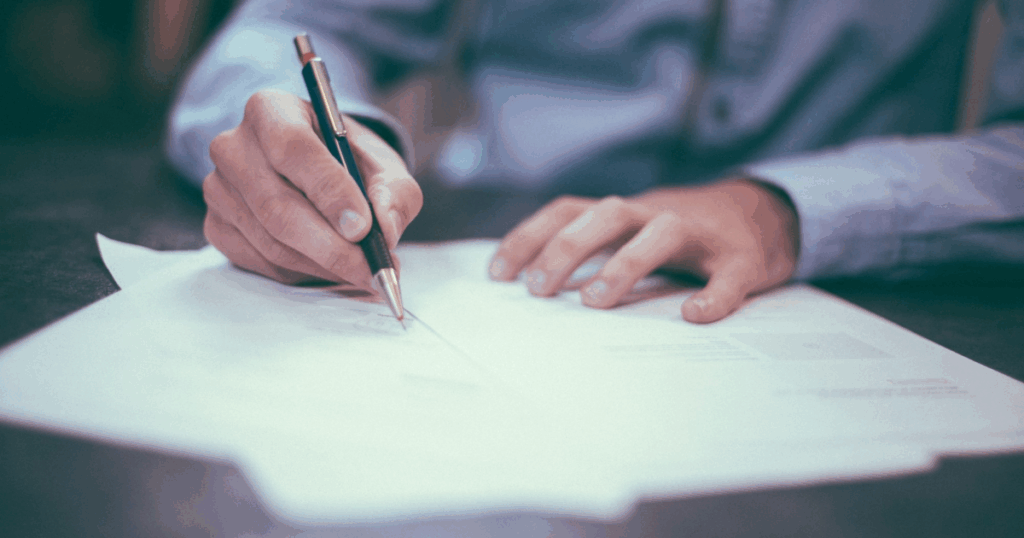
知財戦略は自力で策定できるのでしょうか?
結論から言えば、可能です。
知的財産権情報は公報で公開されていますので、自社が取り組むべき分野での状況を確認します。
参照:特許庁
その後、特許分類を抽出し、自社で情報分類・収集・分析を実施します。
さまざまな分析手法がありますが、自社に最適な手法を取り入れて実践すれば、対応は可能です。
その一方、知的財産戦略を自力で策定する場合には、想定外の事態に直面したり、結果として取り組み自体がマイナスの方向へと向かうこともあります。こうした状況を避けるためには、専門の事業者に依頼することをお勧めします。

知的財産戦略を実際にどのように企業活動に活かしているかを理解するためには、具体的な取り組み事例を見ることが非常に有効です。理論だけではイメージしにくい知財の活用方法や戦略の実際の運用方法を実例を通して確認することで、自社での応用のヒントを得られるでしょう。
企業規模や業種によってアプローチは異なりますが、特許や商標の取得・管理だけでなく、ライセンス契約やオープン特許の活用、技術連携など多様な手法があります。
これから知的財産権知的財産戦略の代表的な活用事例についていくつか取り上げ、解説します。
1950年代にカメラメーカーとして発足したキヤノンは、先行する競合企業の特許網を突破する新技術を特許化し、後発からの参入に成功しています。
その後、1970年以降も新たなコア技術の開発による特許取得と周辺技術の開発による特許取得を積み重ね、複写機の分野で現在に至るまで確固たる地位を構築しています。
同社hpから引用:
“キヤノンの知的財産活動は、ドイツのライカ社が保有する特許を避けてカメラを開発するための実用新案の取得から始まりました。その後、1960年代にはキヤノンは複写機分野へ参入し、米国のゼロックス社が保有していた完璧といわれた特許網をかいくぐり、ゼロックス社の特許に触れない、新しい電子写真技術「NP方式」を開発することに成功しました。これらの経験がキヤノンの知的財産戦略の基礎となり、今日まで受け継がれています。”
同社で継続的に実施している「発明先取り会議」は、まだ他の誰もが取り組んでいないテーマについて、5年後~10年後を考えたらこの領域で「こういうことが始まるのではないか」を考え、新たな発明を考えるものです。
同社の特許出願している主な分野について共通特許分類(CPC分類)のランキングで確認すると、その7割近くがG06F(電気的デジタルデータ処理)に関する出願となっています。
未来の事業戦略を描き、必要な特許を先に確保することで、戦略を達成することが可能となります。
同社は1985年に国策会社として発足(国際電信電話株式会社)後、通信自由化に伴う合併などを経て2000年に発足しました。
その後、現在に至るまで多種多様なスタートアップ企業との協業による新規事業を創出し、知的財産部門を中心に事業の共創を推進しています。
同社hpから引用
“新規事業の創出と事業競争力の強化には、共創相手であるグループ会社やスタートアップの成長が不可欠との考えから、グループ会社や出資先スタートアップの知的財産活動(発明発掘、特許侵害調査、IPランドスケープなど)の支援を推進しています。
こうした支援の取り組みが認められ、2019年度に知財活用企業(オープンイノベーション推進企業としては初)として「知財功労賞」(経済産業大臣表彰)を受賞しました。
今後も新規事業の創出と事業競争力の強化のために、KDDIグループの知的財産活動の強化を図っていきます。”
同社は、知的財産を幅広い事業分野に活用できる無形資産として考慮し、知的財産のベストミックスを戦略的に活用することが持続的な競争優位の実現に重要であるとして、さまざまな対応を行っています。
同社hpから引用
“VISION2030の全社基本戦略である、(1)社会課題視点に基づく事業ポートフォリオ変革、(2)事業デザイン力の強化とソリューション型ビジネスモデルの構築、(3)環境基盤技術の開発・獲得とサーキュラーエコノミー型ビジネスモデルの構築、(4)デジタル・トランスフォーメーションの全社・全領域への展開に基づき、事業部門/研究開発部門/生産技術部門、さらにグループ内外の関係部署とも緊密に連携して、競合に対して優位となる知的財産の取得・活用の方針を逐次見直し、事業に資する知財ポートフォリオを構築していくことにより、知的財産を活用した事業機会の最大化と知的財産に起因する事業リスクの最小化に取り組んでいます。”

知的財産戦略の背景と意義、必要性とメリット、フレームワークの設定とポイントなどについて解説しました。知的財産戦略を自力で策定するには時間と労力、専門知識が必須となります。
AXIA Marketingでは、知財戦略にお悩みの企業様に向けて、経験豊富なスタッフが適切な支援を行います。詳しいサービスの詳細やお問い合わせについては、公式サイトをご覧ください。
参考文献
・知的財産戦略本部
・知的財産権活用事例 | 経済産業省 特許庁
・中小企業経営者のための知的財産戦略マニュアル
・知的財産戦略 | 研究開発 | 帝人株式会社
・知的財産戦略|イノベーション|明治ホールディングス株式会社
・知的財産の保護・活用 | 研究・技術開発 | レゾナック
・知的財産戦略 | 三菱ケミカルグルー
・知的財産戦略 | 研究・開発 | 旭化成株式会社
・知財活用に向けたフレームワーク – KPMGジャパン
・知財戦略とは? ~考え方と成功企業の事例を簡単に解説~|TechnoProducer株式会社|
・事例から学ぶ!「知財戦略」 | 経済産業省
・知財経営とは | 支援情報 | INPIT岡山県知財総合支援窓口
・一歩ずつ進める中小企業向け知財戦略チェックリスト
・スタートアップ・ベンチャー・中小企業のための特許出願|弁理士法人みなとみらい特許事務所
・特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) 公式サイト
・特許庁
・キヤノン「テクノロジー」公式サイト
・KDDI「知的財産マネジメント」 公式サイト
・三井化学「知的財産」 公式サイト
Copy Link





