
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.10.18


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
近年、東南アジアの化粧品市場は高い成長率を維持しており、日本や韓国をはじめとする海外ブランドからの注目もますます高まっています。特に若年層を中心とした消費者の購買力向上や、SNSを活用した情報収集の浸透が市場拡大を後押ししています。
また、インドネシアやマレーシアではハラル認証コスメ、タイやベトナムではK-Beautyの人気、シンガポールではサステナブル製品など、国ごとに異なる需要が見られるのも特徴です。本記事では、東南アジア化粧品市場の最新トレンドと国別の特徴を整理し、日本企業が参入する際に押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。

東南アジア(ASEAN域内を中心とした国々)の化粧品市場は近年急拡大しており、2024年には約USD14.5B(約145億米ドル)の規模に達したと推定されています。これは、市場の拡大、所得水準の向上、デジタル化の進展などが相まっての結果とされます。IMARC Groupの予測によれば、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)は約4.04%を維持し、2033年には USD21.5B(約215億米ドル)水準に達すると見られているのです。
この成長を支える背景には、若年層人口の増加と中間層の拡大、都市化の進行、インターネット利用率とモバイル決済の普及があります。特にEC化粧品チャネルは年率20~30%規模で拡大しており、消費者はオンラインでの購入をますます選好する傾向が強まっているのです。ジェトロの調査によれば、インドネシアでは化粧品・パーソナルケア製品のEコマースチャネルが前年比約30%成長しており、オンライン化の波が明確に表れています。
また、市場セグメントでは「機能性化粧品(スキンケアや医療的な効果を持つ成分を含む製品)」の成長率も注目されており、2024年時点で約USD113M規模、年率約7.26%の成長が予測されています。このようなトレンドは、消費者が単なる美容用途だけでなく、成分や効能にもこだわる風潮を反映しているのです。
国別に見ると、インドネシアやタイ、ベトナムが成長の主力となっており、人口規模や購買力、ローカルブランドの台頭などで他国を牽引しています。マレーシアでは多民族ゆえの美意識の多様性を背景に、差異化された商品が支持を受けつつあります。
シンガポールも都市国家ながら、クリーンビューティーや高価格帯ブランドの需要が根強く、成長基盤を持ち続けているのです。
将来的には、デジタルマーケティング・SNS連携・ライブコマースの活用、ハラル認証化粧品やサステナブル素材の導入が、成長戦略の鍵を握るでしょう。東南アジア市場は、単なる“追随市場”から“競争の舞台”へと変化しつつあり、日本企業が適切なローカライズ戦略をもって挑む余地は大きいと言えます。

東南アジアの化粧品市場は、人口増加や中間層の拡大を背景に今後も大きな成長が期待されています。しかし、単に市場規模が拡大しているだけでなく、消費者の価値観や購買行動の変化を反映した新たなトレンドが次々と登場しています。
東南アジアの化粧品市場において注目すべきトレンドとして、以下の4つが挙げられます。
【東南アジア化粧品市場で注目すべき4つのトレンド】
東南アジアの化粧品市場において、特に成長が著しい分野の一つがハラル認証コスメです。インドネシアやマレーシアといったイスラム教徒人口が多数を占める国では、化粧品にもハラル対応が求められるケースが増えています。
ハラルとは、イスラム法に則り許可された成分や製造方法を指し、動物由来成分の使用や製造過程における規定が厳格に定められています。これにより、消費者は安心して日常的に使用できる製品を選ぶことができ、信頼性の高いブランドが市場で優位に立つ傾向があるのです。
さらに近年では、ハラル認証は宗教的理由だけでなく、「安全・高品質・倫理的」といった付加価値の象徴として、非イスラム教徒の消費者層にも広がっています。特に自然由来成分や動物実験を避けた商品が求められるサステナビリティ志向と重なる部分があり、グローバルブランドも東南アジア市場に合わせてハラルラインを展開する動きが加速しています。日本企業が参入を検討する際も、現地の認証制度や流通の仕組みに対応できるかが成功の鍵となるでしょう。
ハラル食品・商品一覧はこちらをご覧ください。
東南アジアの消費者は、かつては価格や効果を重視する傾向が強かったものの、近年ではサステナビリティへの関心が急速に高まっています。特にプラスチックごみ削減や動物実験を行わないクルエルティフリー製品、オーガニック原料を使用した自然派コスメが注目されています。
こうした背景には、地球温暖化や海洋汚染といった社会的課題がメディアやSNSを通じて広く共有され、若い世代を中心に「環境に優しい選択」がライフスタイルに根付いてきたことがあります。サステナブルなパッケージや再利用可能な容器を採用するブランドは、特にシンガポールやマレーシアで好意的に受け入れられ、ブランド価値を高める重要な要素となっています。
韓国コスメは、東南アジア市場において今なお強い存在感を放っています。その理由は、手頃な価格帯と高い品質、さらにSNS映えするパッケージやトレンドを先取りした商品展開にあります。特にスキンケア分野では、美白・保湿・エイジングケアに対応する多様なアイテムが揃い、幅広い層のニーズを満たしています。韓流ドラマやK-POPの影響も大きく、韓国文化全体への憧れが消費行動に直結しているのも特徴です。
その他、韓国ブランドはマーケティングにおいても柔軟で、現地のインフルエンサーとのコラボやポップアップストアの展開などを積極的に行っています。そのためK-Beautyは単なる流行ではなく、東南アジア市場で継続的な定番として位置づけられています。
東南アジアはスマートフォン普及率が高く、オンラインでの情報収集や購買行動が急速に拡大しています。特に化粧品分野では、ECサイトやSNSを通じた販売・プロモーションが重要なチャネルとなっています。インドネシアやベトナムではShopeeやLazada、シンガポールではQoo10などのECプラットフォームが市場をリードしており、各ブランドはこれらのモールに公式ショップを開設することで信頼性を確保しています。
また、InstagramやTikTokを活用した短尺動画によるレビューやライブコマースが若い世代に強く支持されており、購買決定の大きな要因となっています。今後もデジタルマーケティングを活用できるかどうかが、東南アジアでの化粧品事業の成否を左右するでしょう。

東南アジアは、多様な文化や宗教背景を持つ国々が集まり、それぞれの市場特性が化粧品の需要や嗜好に大きく影響しています。例えば、世界最大のイスラム人口を抱えるインドネシアではハラル認証が購買の前提条件となる一方、シンガポールでは高級志向が強く、ハイテク美容機器やラグジュアリーブランドが人気を集めています。
また、タイでは美白需要、ベトナムではEコマースを中心とした消費拡大、フィリピンでは韓国コスメ人気、マレーシアではアンチエイジング需要が目立ちます。ここでは、主要6カ国の市場特徴を具体的に解説します。
インドネシアは世界最大のイスラム人口を抱える国であり、化粧品市場においてもハラル認証が最も重要なキーワードとなります。消費者の購買行動において宗教的背景が大きく影響しているため、化粧品メーカーはハラル認証の取得を前提とした商品展開を行う必要があります。
実際に、インドネシアの化粧品市場は堅調に成長を続けています。
ユーロモニター・インターナショナルのデータによると、2023年の市場規模(小売総額)は101兆9,656億ルピア(日本円で9,278億円、1ルピア=0.0091円で算出)と前年比は5%の増加です。
インドネシアの若い世代から現在人気の韓国カルチャー流入を機に、美容への関心の高まり、または経済成長によって購買率が上がったことが要因だと言われています。
タイ市場の最大の特徴は、美白ニーズの強さです。日焼けした肌よりも白く明るい肌が美の基準とされ、美白化粧水やクリーム、日焼け止めが高い人気を誇ります。
タイの化粧品市場規模は2013年の740億1,000万バーツから、2018年の1,078億5,900万バーツへ45.7%拡大しています。
また、タイは化粧品の製造・輸出拠点としてのポジションも確立しつつあり、ASEAN域内への輸出も盛んです。国内ブランドに加え、日本や韓国ブランドも高いシェアを持ち、特に品質と安全性が重視される傾向があります。
観光立国であるタイではインバウンド需要も見逃せません。旅行者が現地で購入する化粧品や土産用の美容製品は、販売チャネル拡大に寄与しています。美白需要と輸出拠点という二重の強みを持つタイは、今後もASEAN美容市場の中核として成長が見込まれます。
ベトナムは経済成長率の高さと中間層の拡大により、化粧品市場も急速に発展しています。特にオンライン販売の伸びは著しく、2013年から2018年にかけてEコマースの化粧品売上は約379%増加しました。
さらに、消費者は高価格帯のプレミアム製品にも積極的に投資する傾向があり、欧米や日本ブランドの進出にとって大きなチャンスとなっています。都市部の若年層はSNSを通じて最新の美容情報にアクセスしており、トレンドの変化が早いのも特徴です。韓国コスメや日本のスキンケア製品が人気を集める一方で、地場ブランドも台頭しており、ローカルと外資が共存するダイナミックな市場が形成されています。
マレーシアの化粧品市場は、若々しい外見を維持・向上させることに重点を置いた製品が人気を集めています。特にアンチエイジングやスキンケア関連商品は高い需要があり、30〜40代の女性を中心に市場を牽引しています。
マレーシアは車社会で、エアコンを使う時間が長いため、肌の乾燥が起こりやすい環境です。そのため、従来から人気のある美白ケアに加え、近年は保湿へのニーズも高まっています。現地で日本商品の販売やマーケティングを手掛ける「ふぁん・じゃぱん」の五木田貴浩氏も、こうした傾向を指摘しています。
さらに、日差しが強い気候の影響で、シミ予防が期待できるビタミンC誘導体入りの保湿クリームや、UVケア商品は民族を問わず幅広い層から支持されているのです。また、スキンケアにおいては「つけ心地の良さ」も重視されており、べたつくタイプよりも、さらっとした使用感の商品が好まれる傾向があります。
シンガポールはASEANの中でも一人当たりGDPが最も高く、高級志向が強い市場として知られています。化粧品市場においても、ハイブランドのスキンケアやメイクアップ製品、最新テクノロジーを搭載した美容デバイスが人気を集めています。
一人当たりの化粧品消費額は約177.8米ドルとASEAN諸国で最も高く、購買力の高さが際立つでしょう。また、多民族国家という特性上、幅広い肌質や美容ニーズに対応する製品が求められています。Eコマースの利用率も高く、オンライン限定商品やデジタルキャンペーンが効果的です。
技術革新が高かったり、リーズナブルな皮膚科医推奨ブランド等、付加価値が高い製品が人気です。富裕層をターゲットとしたマーケティングだけでなく、駐在員や外国人労働者向けの商品展開も市場拡大の一因となっています。
フィリピンでは韓国コスメの人気が非常に高く、市場の約3分の1を占めています。特に手頃な価格とトレンド感のある商品が若者層に強く支持されており、K-Beautyブランドが現地の小売市場を席巻しています。フィリピンは人口が多く平均年齢も若いため、美容関連消費の潜在力が大きいのも特徴です。
ユーロモニター2019によると、美容用品の2018年のフィリピンでの小売販売額は1,993億ペソ(約4,185億円、1ペソ=約2.1円)で、2004年と比較して約2倍となり、2023年までに2,500億ペソ以上に達することが予測されています。
日本の化粧品メーカーは、高い技術力と品質への信頼を武器に、東南アジア市場で着実に存在感を高めています。中間層の拡大や美容意識の向上に伴い、スキンケアやメイクアップ製品の需要は年々増加しており、現地の文化や生活習慣に合わせた商品展開が不可欠となっています。
ここでは、東南アジア市場に参入する代表的な日本の化粧品企業を3社紹介します。

引用:株式会社資生堂公式サイト
資生堂はアジア最大級の化粧品メーカーとして、東南アジアでも強力なプレゼンスを発揮しています。シンガポールを拠点にアジア太平洋地域の統括機能を持ち、現地消費者の嗜好や文化に合わせた製品開発を進めています。
特にスキンケア領域でのブランド力は圧倒的で、敏感肌や高機能スキンケアに対応した商品は現地でも高く評価されている企業です。また、資生堂は現地での研究開発にも力を入れており、サステナビリティを重視した製品や、デジタルマーケティングを駆使した販売戦略を展開しています。シンガポールでは現在、150周年を記念したプロジェクトが進行中で、誰もが心身ともに健やかで美しく、前向きに日々を過ごせる社会の実現を目指しています。
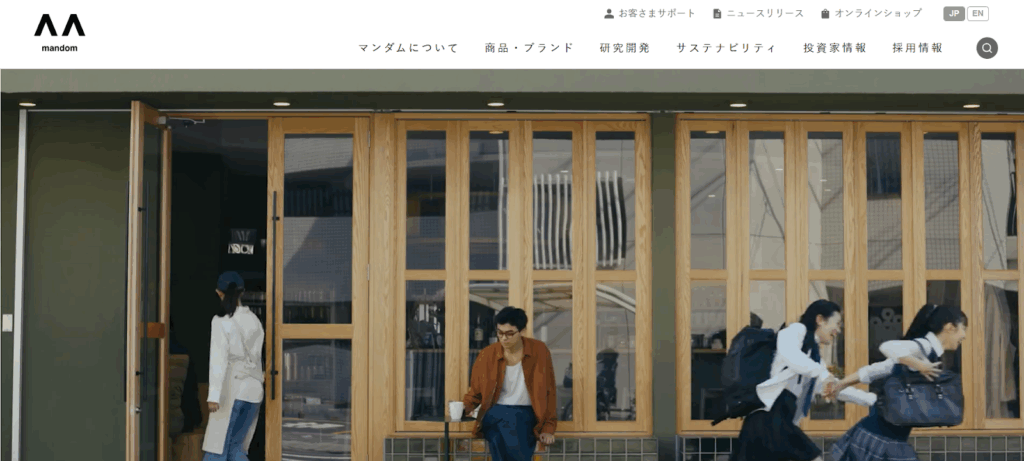
引用:株式会社マンダム公式サイト
マンダムは「ギャツビー(GATSBY)」ブランドで知られ、特に男性向け化粧品市場で高い支持を得ています。東南アジアではインドネシアを中心に強いブランド力を持ち、整髪料やスキンケア製品は若年層を中心に広く浸透しています。
マンダムは早くから現地法人を設立し、消費者のライフスタイルや宗教的背景に適応した商品開発を行ってきました。例えば、イスラム圏向けにハラル認証を取得した製品を展開するなど、現地ニーズを的確に捉えた戦略が成功につながっています。さらに、SNSやインフルエンサーを活用したマーケティングにも積極的で、東南アジアの若年層市場での存在感を一層強めています。
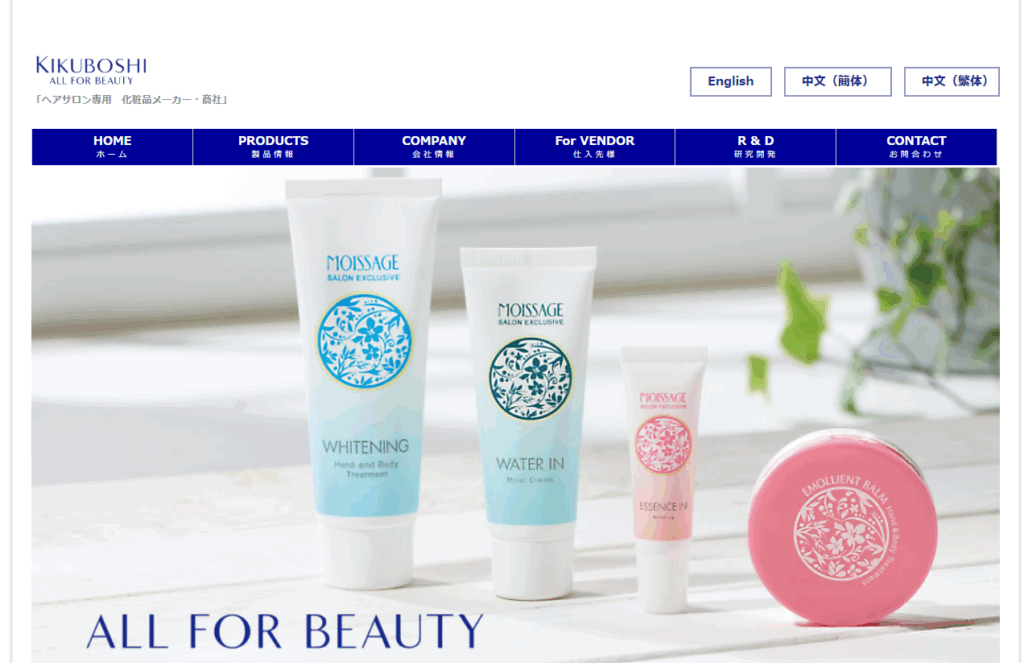
引用:株式会社菊星公式サイト
株式会社菊星は、日本国内での美容室向けプロフェッショナル化粧品事業を基盤に、東南アジア市場にも進出しています。特にベトナムでは現地企業との提携を通じて美容サロン向け製品の展開を進めており、プロフェッショナル市場でのシェア拡大を狙っています。
菊星の強みは、美容師やサロンオーナーのニーズに寄り添った製品開発と教育支援です。単に製品を販売するだけでなく、美容技術の指導や現地スタッフの育成を含めた包括的な支援を行うことで、ブランドの信頼性を高めています。品質を第一に考えて生み出した商品には、モンド・セレクションやiTQi、グッドデザイン賞などの受賞実績もあり、国内外に多数の特許も有しています。
今後も東南アジアでのパートナーシップ強化を通じ、プロ市場を中心に独自のポジションを確立していくことが期待されます。

東南アジアの化粧品市場は急速に成長しており、日本企業にとって大きなビジネスチャンスが広がっています。しかし、単に日本国内と同じ製品や販売手法を持ち込むだけでは成功は難しく、各国の宗教や文化、規制、流通環境を正しく理解し、それに適応することが求められます。
ここでは、日本企業が東南アジア化粧品市場へ進出時に押さえておくべき4つの重要ポイントを解説します。
東南アジアは多民族・多宗教社会であり、国ごとに文化的背景や生活習慣が大きく異なります。そのため、化粧品市場に進出する際には宗教・文化的要素を踏まえた商品設計とプロモーションが不可欠です。
例えば、インドネシアやマレーシアではイスラム教徒が多数を占めるため、ハラル認証を取得した化粧品の需要が非常に高く、製品成分や製造プロセスにおいても厳格な基準への対応が求められます。
また、タイやベトナムでは美白志向が強く、ホワイトニング製品が人気ですが、フィリピンやシンガポールでは自然派・オーガニック商品が注目されています。このように、宗教や文化を理解し現地の価値観に合致した商品やマーケティングを展開することが、顧客から信頼を得てブランドを定着させる大きな鍵となります。
東南アジア諸国では、化粧品の輸入や販売に関する規制が厳格に定められており、日本企業は進出前に必ず現地の制度を把握しておく必要があります。例えば、シンガポールでは「Health Sciences Authority(HSA)」が輸入化粧品の安全性や成分表示を厳しく管理しており、輸出時には成分リストや製造工程の詳細を提出する必要があります。
また、ベトナムでは「化粧品の輸入規則および留意点」として、製造国の承認書や自由販売証明書(CFS)の提出が義務付けられています。
こうした規制は国ごとに異なるため、参入前にジェトロ(日本貿易振興機構)などの公的機関が提供する情報を活用することが重要です。輸出規制や認証への的確な対応は、参入スピードを高めるとともに、現地での信頼構築にも直結します。
東南アジアの化粧品市場では、ShopeeやLazadaといった大手ECプラットフォームが急成長しており、特に若年層や都市部の消費者にとって欠かせない購入チャネルとなっています。これらのプラットフォームは越境ECにも対応しており、日本からの直接販売を可能にするため、中小企業にとっても参入障壁が低いのが魅力です。
また、プラットフォーム内で展開されるフラッシュセールやライブコマース機能を活用することで、ブランドの認知拡大や短期的な売上向上が期待できます。さらに、レビュー機能やランキング制度は消費者の購買判断に大きな影響を与えるため、積極的な顧客対応やキャンペーン戦略を組み合わせることが欠かせません。
例えば、Shopeeの日本法人であるショッピージャパン株式会社は、ベトナム市場での越境EC事業を実施しています。【2025年版】ベトナムでの越境ECに関する定点調査によると、95.4%がベトナム市場への新規参入増加を予測し、2024年を5.9ポイントも上回る結果となりました。
東南アジアではSNSの利用率が世界的にも高く、Instagram、TikTok、Facebookを中心としたデジタルマーケティングが化粧品市場で大きな力を発揮しています。特にインフルエンサーを活用したプロモーションは、若い世代を中心に絶大な影響力を持ち、ブランド認知の拡大や購買行動の促進につながります。
また、現地の消費者は口コミやレビューを重視する傾向が強いため、オンライン上での評判管理も欠かせません。さらに、国や地域によっては消費者が好むコンテンツの形式や表現が異なるため、現地の文化や言語に合わせた広告クリエイティブの最適化が必要です。デジタルマーケティングを効果的に活用することで、日本企業は短期間で幅広い消費者層にリーチでき、競争力を高められます。

東南アジアの化粧品市場は、経済成長とともに中間層が拡大し、今後も高い成長が見込まれる注目の分野です。国ごとに美容トレンドや購買チャネルが異なるため、現地の消費者嗜好や文化を理解した上で戦略を立てることが成功の鍵となります。
AXIA Marketingでは、市場調査から進出戦略の策定、現地パートナーの選定支援までワンストップでサポート可能です。東南アジア市場への参入を検討している企業は、ぜひAXIA Marketingにご相談ください。
参考文献
Copy Link





