
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.10.18


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
製造業は、政治・経済・社会・技術といった外部環境の影響を最も受けやすい業界の一つです。原材料価格の高騰や為替の変動、環境規制の強化、AI・IoTによる生産技術の進化など、変化のスピードは年々加速しています。
こうした複雑な環境下で企業が持続的な成長を遂げるためには、外部要因を体系的に把握し、経営戦略に反映することが不可欠です。
本記事では、製造業におけるPEST分析の基本的な考え方から、具体的な実施手順、国内外企業の事例までをわかりやすく解説します。

PEST分析とは、企業を取り巻く外部環境を「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の4つの視点から体系的に分析する手法です。市場の変化や外的要因は、企業の意思決定や事業戦略に大きな影響を与えます。
特に製造業のようにグローバルなサプライチェーンを持ち、政策や経済動向に左右されやすい業界では、PEST分析が経営判断の重要な基盤です。この分析を通じて、企業は外部要因を機会と脅威として整理し、自社の強みをどのように活かすか、またリスクをどう最小化するかを見極められます。
市場調査や経営企画の初期段階でPEST分析を行うことで、将来の環境変化を見据えた中長期的な戦略立案が可能になります。

製造業でPEST分析が必要とされる理由は、外部環境の変化が事業に直結する業界構造にあります。原材料の価格変動、為替レートの上下、環境規制や貿易政策の改定といった外部要因は、製造コストや供給網、販売戦略に直接的な影響を与えます。
特にグローバル展開を行う企業にとって、各国の政治・経済情勢を把握し、リスクマネジメントを徹底することは不可欠です。さらに、脱炭素化やDXなどの社会的潮流も製造業の競争力を左右する要素となっています。
例えば、環境対応製品への需要増加やAI・IoT技術の導入は、ビジネスチャンスである一方で投資負担や技術対応の課題も伴います。PEST分析を行うことで、こうした外部要因を整理・把握し、自社の経営戦略に反映させることが可能です。
結果として、変化の激しい市場環境でも柔軟かつ持続的な成長を実現できるのです。

製造業は、国際情勢や原材料価格、技術革新など外部環境の変化に大きく左右される業界です。ここでは、PEST分析の4つの観点から製造業に影響を与える主要な外部要因を整理し、今後の戦略立案に役立つ視点を解説します。
政治的要因は、製造業の経営環境を大きく左右する重要な外部要素です。政府による規制や法改正、貿易政策、補助金制度などは、企業のコスト構造や事業戦略に直接的な影響を及ぼします。
製造業では、環境政策や労働関連法の変更、国際関係に基づく貿易摩擦などが、サプライチェーンの安定性や海外拠点の運営に関わるため、継続的なモニタリングが欠かせません。各国政府の動向を把握することは、事業のリスクヘッジと機会創出の両面で極めて重要です。
製造業では、各国の環境規制や労働関連法が事業活動に直接的な制約を与えます。近年では、カーボンニュートラル実現に向けた排出削減目標の強化が進み、再生可能エネルギーの導入や省エネ設備投資が求められています。これに伴い、製造コストの上昇や生産体制の見直しを余儀なくされるケースも少なくありません。
一方、労働法改正により、労働時間の短縮や安全基準の厳格化、最低賃金の引き上げといった対応も必要です。これらの変化は一見負担に見えますが、長期的には企業の社会的信頼やブランド価値の向上につながる側面もあります。
そのため、環境と労働の両面で持続可能な経営を実現するための戦略的対応が求められています。
グローバル化が進む製造業では、貿易政策の変化がサプライチェーン全体に大きな影響を与えます。近年では、米中貿易摩擦やロシア・ウクライナ情勢などの地政学的リスクが顕在化し、原材料や部品の調達先を多角化する動きが加速しています。
加えて、自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)の締結により、関税削減や輸出入手続きの簡素化といったメリットも。一方で、政治的緊張や輸出規制の強化は、調達コストの上昇や物流の混乱を招くリスクがあります。
そのため、企業はリスク分散を前提としたグローバルサプライチェーンの再構築を進めることが重要です。現地生産の比率を高める、サプライヤーを複数化するなど、柔軟な体制構築が競争力維持の鍵となります。
経済的要因は、製造業の売上・利益・投資判断に直結する極めて重要な外部環境です。原材料価格の変動、為替レートの変化、景気動向などは、生産コストや収益性を大きく左右します。
製造業は景気に敏感な業種であり、国内外の経済情勢を的確に読み解くことが競争力の維持に不可欠です。加えて、インフレ・金利・雇用情勢といったマクロ経済指標を踏まえ、中長期的な事業戦略を柔軟に見直す姿勢が求められています。
製造業における最大の経済リスクのひとつが、原材料価格の高騰と為替変動です。鉄鋼、樹脂、半導体、エネルギーといった主要資材の価格は、世界的な需給バランスや地政学的リスクによって大きく変動します。例えば、原油価格の上昇は製品コストや物流費を押し上げ、利益率の低下を招くのです。
また、為替の変動も輸出入企業にとって重要な要素で、円安は輸出企業の利益を押し上げる一方、輸入コストを増加させるという二面性があります。そのため製造業では、為替予約やコスト転嫁の仕組みを整えるほか、現地生産比率を高めるなどして為替リスクを分散する戦略が有効です。
安定的な調達網と価格変動への耐性を持つサプライチェーン構築が、企業の持続的成長を支える鍵となります。
製造業は景気変動の影響を最も受けやすい業界のひとつです。景気拡大期には設備投資や消費が活発化し、需要が急増しますが、景気後退期には企業・個人の支出が抑制され、生産縮小や在庫調整を余儀なくされます。
特に耐久消費財やBtoB製品を扱う企業では、世界経済の動向や主要取引先の投資マインドが業績に直結します。さらに、近年はグローバルサプライチェーンの分断やインフレの長期化などにより、景気の先行きが不透明な状況が続いています。
そのため、製造業では短期的な景気変動に左右されないよう、複数市場への展開やサービス事業への転換など、収益源の多角化を進める企業が増加中です。需要変動を見越した柔軟な生産・販売体制を整えることが、長期的な競争優位の確立につながります。
社会的要因は、製造業の労働力確保や消費者行動の変化に直結する重要な外部環境です。特に日本では人口減少と高齢化が進行し、労働力不足が構造的な課題となっています。
一方で、消費者の価値観や購買意識も多様化しており、環境に配慮した製品やサステナブルな生産体制への期待が高まっています。製造業が成長を維持するためには、これら社会的な変化を踏まえた人材戦略・製品戦略・企業ブランディングが不可欠です。
日本をはじめとする先進国では、人口減少と労働力不足が深刻化しています。製造現場では若年層の就業希望者が減少し、熟練工の高齢化が進むことで技術継承や生産性維持が課題となっています。その結果、人手不足を補うための自動化・ロボット導入や外国人労働者の受け入れが加速しているのです。
また、人材確保だけでなく、従業員のエンゲージメント向上や柔軟な働き方の導入など、労働環境の改善も求められています。一方で、労働人口の減少は国内市場の縮小にもつながるため、製造業各社は海外市場への展開や高付加価値製品の開発を進めるなど、需要の多様化に対応した戦略が必要です。
人材不足を単なる制約ではなく、生産性革新を進める機会と捉える企業が、将来的な競争優位を築けるでしょう。
近年、消費者の購買行動は価格重視から価値重視へと大きく変化しています。特に若年層を中心に、環境配慮・社会的責任・サステナビリティを重視する傾向が強まっており、製造業にもエシカルな視点が求められています。
再生素材の活用、リサイクル可能な製品設計、省エネ生産への転換など、ESG経営やカーボンニュートラル対応が企業の信頼性を左右する時代です。さらに、SNSや口コミを通じて企業の取り組みが可視化される中で、「どのように作られているか」がブランド価値に直結しています。
そのため製造業では、環境負荷の低いサプライチェーン構築や透明性の高い情報発信が不可欠です。こうした社会的要請に応える企業は、消費者からの支持を得やすく、長期的な企業価値向上にもつながります。
技術的要因は、製造業の競争力を左右する最も重要な外部環境のひとつです。近年では、自動化・ロボット化、AI・IoT・DXといった先端技術の導入が進み、生産効率の向上・品質管理の高度化・人材不足の解消に寄与しています。
これらの技術革新は、単なる生産ラインの効率化にとどまらず、ビジネスモデル全体の変革を促進しており、製造業の在り方そのものを再定義しつつあります。
製造業では、深刻な人手不足への対応や品質の均一化を目的に、自動化・ロボット技術の導入が急速に進んでいます。組立・検査・搬送といった反復作業では、産業用ロボットの導入による24時間稼働の無人化ラインが実現しつつあるのが現状です。
また、協働ロボットの普及により、人と機械が安全に共働できる環境も整備されています。この結果、作業効率の向上だけでなく、人件費の削減やヒューマンエラーの防止にもつながっているのです。
さらに、自動化技術は単なる省人化の手段ではなく、熟練工の技術をAI・ロボットに学習させる技能継承の手段としても注目されています。今後は、ロボットが生産現場のデータを取得・分析し、リアルタイムで最適化を行う自己進化型工場の構築が進むでしょう。
AIやIoT、DXの進展は、製造業の構造を大きく変革しています。IoT技術によって生産設備・製品・物流がネットワークでつながり、AIが取得したデータを解析することで、設備の異常予知・在庫最適化・品質管理の自動化が可能になりました。
また、製造現場だけでなく、設計・調達・販売・アフターサービスなど、サプライチェーン全体でデータ連携が進みつつあります。これにより、顧客の利用データをもとに製品を改善するサービタイゼーション(製造+サービスモデル)の動きも加速。さらに、クラウドや生成AIの活用により、開発スピードの短縮や柔軟な意思決定が実現しています。
製造業におけるAI・IoT・DXの導入は、効率化から価値創造へと進化しており、今後のグローバル競争で優位に立つための必須要素となっています。
PEST分析は、製造業における外部環境の変化を的確に捉え、将来のリスクと機会を見極めるための重要な手法です。近年は、脱炭素化・デジタル化・地政学リスク・人材不足といったマクロ要因が、企業経営に直接的な影響を与えています。
ここでは、日本を代表するデンソーと、グローバル製造業のリーダーであるSiemensの取り組みをもとに、PEST分析の具体的な実践事例を紹介します。両社の分析を通じて、製造業がどのように環境変化に対応し、持続的成長を実現しているかを見ていきましょう。

デンソーは、自動車部品の世界的リーディングカンパニーとして、環境変化への対応を経営戦略の中心に据えています。政治的要因としては、カーボンニュートラル政策や電動車普及政策への対応が求められており、デンソーはCO₂排出ゼロを目指す「DENSO Green Challenge 2050」を推進中です。
経済面では、原材料費の高騰やサプライチェーンの混乱に対応するため、グローバル生産体制の分散化・調達先の多様化を進めています。社会的要因では、人口減少に伴う人材確保と技術継承の課題に対し、AIや自動化技術を活用した生産効率化を推進。また、技術要因としては、CASEへの対応を強化し、半導体やセンシング技術など次世代領域への投資を拡大しています。
これらの施策により、デンソーは環境規制や市場変化を機会と捉え、サステナブルかつ競争力の高い製造体制を構築しています。
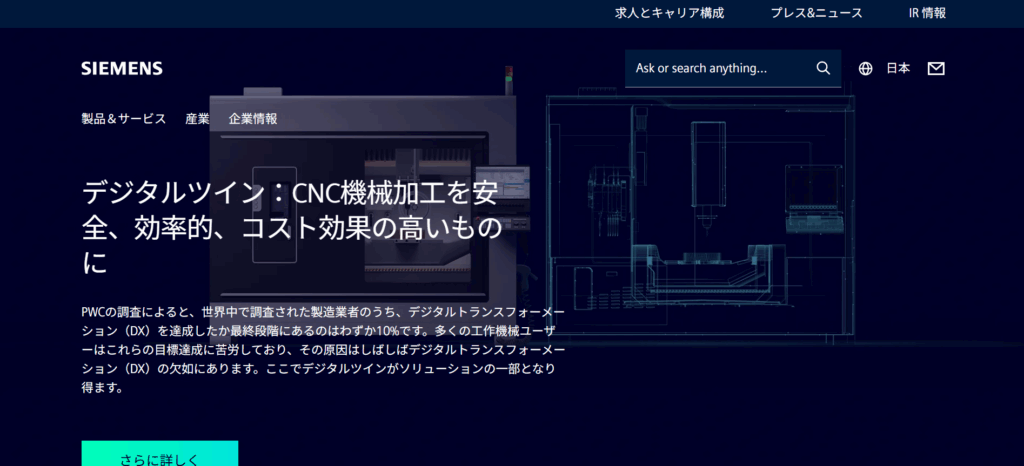
ドイツのSiemensは、産業・エネルギー・医療機器など多角的な事業を展開し、世界的なPEST変化に柔軟に対応している代表的な製造業企業です。政治的要因としては、欧州連合(EU)のグリーンディール政策やカーボンニュートラル義務化に沿い、再生可能エネルギーやスマートグリッド事業を拡大。経済面では、グローバル景気変動やエネルギー価格高騰を見据えたコスト構造の最適化とサプライチェーン再構築に取り組んでいます。
社会的要因では、多様性とサステナビリティを重視し、従業員の教育・リスキリングや、社会的価値創出を目的としたイノベーション文化を推進。技術的要因では、「Siemens Xcelerator」というデジタルプラットフォームを中心に、AI・IoT・クラウド技術を活用したスマートファクトリー化を牽引しています。
これらのPEST要因を統合的に捉え、経営戦略へ反映している点が、Siemensの強みです。Siemensのアプローチは、グローバル製造業が外部変化を競争優位へ転換する成功例と言えるでしょう。

PEST分析を効果的に行うためには、単に外部環境の情報を集めるだけでなく、情報の整理・評価・戦略への落とし込みまでを体系的に進めることが重要です。製造業は政治・経済・社会・技術といった要因の変化が生産体制や供給網、製品開発に直接的な影響を及ぼします。
以下では、PEST分析を実務レベルで活用するための4つのステップを紹介します。
まず最初のステップは、「政治」「経済」「社会」「技術」の4つの要因ごとに、関連する外部情報を網羅的に収集することです。製造業では、環境規制、労働関連法、貿易政策、為替動向、消費動向、技術革新などが事業に直結するため、マクロ環境全体を俯瞰することが重要です。
具体的には、政府の公式発表、経済白書、業界団体のレポート、シンクタンクの分析、ニュースなど複数の情報源を活用します。特に、環境・エネルギー関連政策や国際物流の規制動向など、中長期での影響が予想される要素を優先的にチェックしましょう。
これにより、変化の兆しを早期に察知し、柔軟に経営戦略を見直すための基礎データが整います。
次のステップは、集めた情報を事実と解釈に分けることです。例えば、「政府が炭素税を導入する方針を発表した」というのは事実であり、「製造コストの上昇リスクがある」というのはその事実に対する解釈です。
製造業では、事実と意見が混在すると意思決定の誤りにつながるため、両者を明確に切り分けることが重要です。この段階では、データの信頼性・出典の明確化も欠かせません。複数のソースを照合し、数字や時期に矛盾がないかを確認します。その上で、経営陣や各部門でディスカッションを行い、どの情報を戦略検討の基礎にするかを決定。これにより、分析の精度が高まり、判断の客観性が担保されます。
3つ目のステップでは、整理した事実を機会と脅威の2つに分類します。例えば、「政府の脱炭素政策によりEV市場が拡大する」は機会ですが、「炭素排出規制により生産コストが上昇する」は脅威にあたります。
製造業においては、同じ事象が事業領域によって機会にも脅威にもなり得る点に注意が必要です。この分類によって、どの外部要因が自社の成長を後押しし、どの要因がリスクとなるのかが可視化されます。
ここでの目的は、悲観的・楽観的な見方に偏らず、現実的なリスクマップを作成することです。機会と脅威を定量的に評価すれば、次の戦略立案フェーズでの優先順位づけが明確になります。
最後のステップは、抽出した機会と脅威に対して、具体的な対応策を設計し、事業戦略に反映することです。例えば、新興国の需要拡大という機会に対しては、現地生産拠点の設置やパートナー企業との提携が有効です。
一方、サプライチェーンの不安定化という脅威には、調達先の多様化や在庫リスク分散といった施策で備えます。また、PEST分析を単発で終わらせず、経営計画やR&D戦略、人材育成方針などへ定常的に組み込むことが成功の鍵です。
変化の早い製造業では、分析と戦略立案を継続的に繰り返すことで、外部環境に柔軟に対応できる組織体制を構築できます。

PEST分析を効果的に活用するためには、単に外部環境を整理するだけでなく、経営戦略や事業判断に直結させる運用体制が欠かせません。製造業は、政治・経済・技術といった外部要因の変化が生産・調達・販売に直結するため、分析の精度と継続性が企業の競争力を左右します。
ここでは、PEST分析を実践するうえで特に意識すべき3つのポイントを解説します。
PEST分析の最大の落とし穴は、分析のための分析に陥ることです。まず明確にすべきは、何のためにPEST分析を行うのかという目的設定です。例えば、新規事業の立ち上げ、市場参入、海外展開、サプライチェーン再構築など、目的によって注視すべき外部要因は異なります。
製造業の場合、環境規制への対応やエネルギーコストの変動など、事業リスクを可視化するための分析が中心となることが多いでしょう。目的が曖昧だと、収集すべきデータや検討すべき論点が分散してしまい、経営判断に活かせない分析に終わります。
したがって、分析に着手する前にどの意思決定に役立てるのかを明文化し、チーム全体で共有することが重要です。
PEST分析の精度を高めるには、主観や憶測を排除し、客観的な一次情報・公的データを活用することが不可欠です。製造業では、経済産業省やJETRO、IMF、OECDなどの信頼できるデータソースを基盤にすることで、根拠ある分析が可能になります。
また、経済や技術動向に関しては業界レポートや国際機関の発表に加え、サプライヤーや顧客からの現場情報も重要です。これにより、マクロとミクロ両面から環境変化を捉えられます。
さらに、情報の偏りを防ぐために複数ソースを比較検証し、更新日や出典の信頼性を確認するプロセスを設けることが望ましいです。正確なデータに基づいた分析は、経営層の意思決定に説得力を持たせる基礎となります。
PEST分析は一度実施して終わりではなく、継続的な更新と見直しが前提です。製造業を取り巻く環境は、政治情勢の変化、為替レートの変動、新技術の登場などによって常に動いています。1年前の分析が、今日の状況では全く通用しないケースも珍しくありません。
そのため、少なくとも年1回は分析を再実施し、特に大きな政策転換や技術トレンドが発生した際には臨時で見直すことが求められます。また、定期的に社内共有の場を設け、PEST分析の結果を経営戦略やR&D計画に反映させる体制を整えることも重要です。
継続的な分析によって、変化を先取りし、柔軟に事業戦略を調整できる外部環境に強い企業体質を形成できます。

製造業は、政治・経済・社会・技術といった外部環境の影響を強く受ける業界です。PEST分析を効果的に活用することで、市場変化を先取りし、持続的な競争優位を築けます。
AXIA Marketingでは、各国の規制動向や経済トレンド、技術革新までを網羅した海外市場調査・戦略立案支援を提供しています。現地のリアルなデータに基づき、企業の成長を後押しする最適な市場戦略を構築。グローバル展開を見据える製造業企業にとって、頼れるパートナーです。まずはお気軽にご相談ください。
参考文献
Copy Link





