
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.10.09


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
企業が成長戦略を描くうえで業務提携は、近年ますます重要な選択肢となっています。自社だけでは補いきれない生産力や技術力、販路を補完し合うことで、新たな市場を切り拓く可能性が広がるからです。
一方で、提携解消時のトラブルや経営の自由度低下といったリスクもあり、成功には戦略的な準備が欠かせません。本記事では業務提携の基本や種類、メリット・デメリットを整理するとともに、国内外の成功事例9選を取り上げ、どのように成果へつなげているのかを具体的に解説します。

業務提携とは、複数の企業が互いの強みを活かし、協力して事業を進める取り組みのことを指します。提携内容は生産や技術、販売など幅広く、契約の形態も柔軟に設定できるのが特徴です。
企業はそれぞれ独立性を保ちながらも、協業によってリソースを補完し合うことで、単独では実現できない規模の成果や新たな価値を創出することが可能になります。特に競争の激しい市場環境においては、効率的に成長スピードを高める手段として注目される戦略です。
業務提携とよく比較されるのがM&Aですが、両者には明確な違いがあります。M&Aは企業そのものを合併したり、株式を取得して支配権を持つことで経営を統合する手法です。これに対し、業務提携はあくまで契約による協力関係であり、企業は独立性を維持したまま必要な領域でのみ協力します。
そのため、提携解消も比較的容易であり、柔軟な戦略を取りやすいという特徴があります。一方で、M&Aは意思決定や経営権を統合する分、強固なシナジーが期待できますが、統合コストや文化的摩擦が大きなリスクとなるでしょう。
業務提携は低リスクで迅速に成果を狙える方法であるのに対し、M&Aは長期的な統合と大規模な資本投入を伴う点で異なるのです。

業務提携と一口に言っても、その形態は多岐にわたります。企業が置かれている状況や抱える課題、目指す成長戦略によっても最適な提携スタイルは異なります。代表的なものは、「生産提携」「技術提携」「販売提携」の3つです。
以下にて、それぞれ詳しく解説していきます。
生産提携は、複数の企業が製造工程や生産設備を共有・協力することで、生産能力を高める取り組みです。需要が急増するタイミングや、大規模な投資を単独で行うリスクを避けたい場合に選ばれることが多いです。
例えば、自動車や半導体といった設備投資額が大きい業界では、生産ラインの共同利用やOEMが一般的に行われています。これにより、生産効率が上がるだけでなく、コスト削減や納期短縮にもつながります。
また、原材料の共同調達によって仕入コストを引き下げられる点も魅力です。一方で、品質管理の基準を統一する必要があり、連携の仕組みづくりが成否を分けるといえます。
技術提携は、企業同士が研究開発や知見を共有することで、革新的な製品やサービスを生み出すための協力関係を築く形態です。特に、AIやバイオテクノロジー、次世代エネルギーといった高度な専門分野では、自社だけで十分な研究資源を確保することが難しい場合が多いため、技術提携が有効に機能します。
例えば、異なる分野の企業が技術を持ち寄ることで、新しい市場を創出したり、従来にない付加価値を提供できる可能性があります。さらに、開発スピードの向上や研究コストの分散というメリットも。一方で、知的財産権の取り扱いには注意が必要で、提携契約において共有範囲や使用条件を明確にしておかないと、後のトラブルにつながるリスクもあります。
販売提携は、企業がそれぞれ保有する販売チャネルや顧客基盤を相互に活用し、販売力を強化する提携形態です。例えば、全国的な流通網を持つ大手企業と、独自の商品力を持つ中小企業が提携することで、商品をより広範囲に届けられるようになります。
また、異業種間で販売チャネルを共有するケースも増えており、スーパーと通信キャリア、コンビニと金融サービスといった異なる業界同士の協力は、クロスセル(相互販売)の機会を生み出します。販売提携の最大のメリットは、短期間で新規顧客や販路を獲得できる点です。
しかし、販売戦略やブランドポジションの違いが摩擦を生む可能性もあるため、提携時には明確な販売方針のすり合わせが欠かせません。

業務提携は、単独では難しい課題を解決したり、新しいビジネスチャンスを獲得したりするための有効な戦略です。特に近年は、大手企業同士の連携だけでなく、中小企業やスタートアップが大企業と提携する事例も増えており、提携の形態は多様化しているのです。
ただし、業務提携には成長を加速させる大きなメリットがある一方で、リスクやデメリットも存在します。ここではまず、企業が業務提携を検討するうえで理解しておきたい主なメリットとデメリットを詳しく解説します。
業務提携の主なメリットとしては、以下の4つが挙げられます。
業務提携の最大の魅力は、事業成長のスピードを一気に高められる点です。自社だけで新市場へ進出する場合、販路開拓・設備投資・人材確保に時間とコストがかかりますが、提携先の経営資源を活用することで、その過程を大幅に短縮できます。
例えば、製造業であれば相手先の生産設備を利用して迅速に供給体制を整えたり、小売業では既存の店舗網を利用して新商品を短期間で全国展開できたりします。スピード感のある市場対応は、競争優位性の確立に直結する大きなメリットです。
販売提携や異業種連携を通じて、これまで接点のなかった顧客層へ効率的にリーチできるのも大きなメリットです。例えば、IT企業と小売企業が提携すればオンラインとオフライン双方の顧客基盤を相互に活用でき、新規市場を切り開くことが可能になります。
また、相手企業が海外市場に強みを持っている場合は、輸出や現地展開の足掛かりとなり、グローバル進出の加速にもつながります。提携により顧客接点が多角化することで、ブランド認知度の向上や販売機会の拡大を期待できるでしょう。
業務提携はコスト削減にも直結します。例えば、生産提携で製造ラインを共有することで設備投資を抑えられたり、共同で原材料を調達することで仕入コストを引き下げられたりします。
また、研究開発を共同で行う場合には、研究費を分担できるため、自社単独では実現が難しい規模の開発にも挑戦可能です。さらに、物流やマーケティング活動を共同で行えば、広告宣伝費や配送コストの最適化も可能です。限られた資源を効率的に活用するうえで、提携は非常に有効な手段といえます。
技術提携を通じて、相手企業の強みを取り入れられる点も大きなメリットです。例えば、製造業では新しい生産技術の導入により製品品質を高められたり、IT分野ではAIやIoTといった最新技術を自社サービスに組み込めたりします。
さらに、互いの研究リソースを掛け合わせることで、単独では難しかった新製品・新サービスの開発スピードを加速できます。結果的に市場での競争力を高められるだけでなく、技術的な優位性を確立することで長期的な成長基盤を築くことが可能になります。
業務提携の主なデメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
業務提携を行う際には、技術やノウハウ、顧客情報など自社の重要な機密情報を共有する場面が必ず発生します。そのため、相手企業の管理体制が不十分であったり、従業員教育が徹底されていなかったりすると、情報漏洩のリスクが高まります。
特に競合関係に近い企業との提携では、自社の強みや差別化要素が外部に流出してしまい、かえって競争優位を失う恐れもあります。秘密保持契約(NDA)の締結や情報管理ルールの策定を徹底し、リスクを最小限に抑えることが重要です。
業務提携は永続的なものではなく、戦略の変化や市場環境の変動によって解消されることもあります。その際に発生しやすいのが、資産や知的財産権の帰属、顧客対応、共同で開発した技術の扱いなどを巡るトラブルです。
契約内容が曖昧なまま提携を進めてしまうと、解消時に双方が大きな損害を被る可能性があります。提携開始時から出口戦略を見据え、契約書に解消時の条件や手続きを明確に盛り込んでおくことが、リスクを減らすポイントです。
業務提携は相手企業と共同で事業を進めるため、戦略や意思決定において自社の自由度が制限される場合があります。例えば、販売戦略や商品開発方針について、自社の考えだけでなく相手の意向を考慮しなければならず、迅速な意思決定が難しくなることがあります。
さらに、相手企業の経営状況や市場での評判が自社に影響を与えるケースも少なくありません。自社の独自性を維持しつつ、提携によるシナジーを最大化できるバランスを見極めることが大切です。
近年、企業間の業務提携は新規事業開発や市場拡大の重要な戦略として注目を集めています。特に国内企業においては、同業種での効率化やシェア拡大を目的とした提携、異業種での新しい価値創出、大企業とスタートアップの協業によるイノベーション推進など、多彩な形態が見られます。
ここでは、国内企業の業務提携事例を整理して解説しますので、参考にしてください。
同業種の企業同士が提携するケースは、競争力の強化やコスト削減を目的とすることが多いです。例えば物流業界では共同配送や倉庫シェアリングを通じて効率化を実現する事例が増えています。
また、製造業においては共同研究開発や原材料の共同調達を行うことで、規模の経済を活かしながら市場シェアを拡大しています。同業種連携は競合でありながら共存を模索する形でもあり、業界全体の成長に貢献する取り組みとして重要性が高まっているのです。
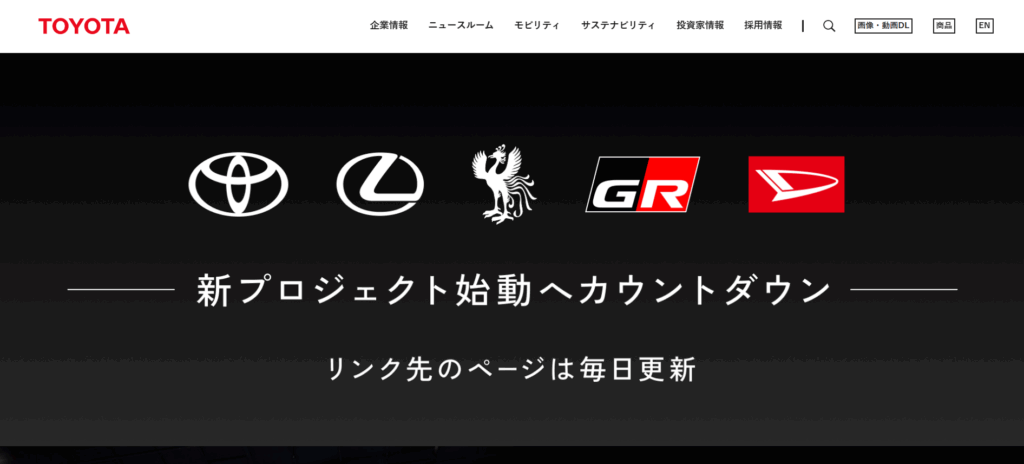
トヨタとスズキは、自動車産業の競争力強化を目的に包括的な業務提携を進めています。両社は互いの得意分野を活かし、トヨタは電動化や自動運転などの先端技術を、スズキは新興国市場での強力な販売網を提供。スズキが開発するSUVタイプのバッテリーEV(BEV)を、トヨタにOEM供給することを決定しました。
協業車両の導入地域は、日本、インド、欧州、アフリカ、中東に拡大しています。さらに環境対応車の普及や次世代技術開発においても協力を強め、グローバル市場での持続的な成長を目指しています。

ANAとJALは国内航空業界における競争関係にありながらも、安全性と効率性を高めるために業務提携を実施しました。具体的には、空港でのグランドハンドリング業務に関して、両社の作業資格を相互承認する仕組みを導入。これにより、作業人員の柔軟な運用が可能となり、空港業務の効率化や人材不足への対応を実現しました。
ライバル同士が協力する姿勢は、利用者の利便性と業界全体の安定性を高める好例として注目されています。
業務提携の中でも特に注目されるのが、業種の異なる企業同士が持つ強みを融合させる異業種連携です。例えば、通信事業者と小売事業者、製造業とIT企業など、通常は交わらない領域で協力することで新しい価値を創出できます。
異業種連携は単なる補完関係ではなく、互いの技術・チャネル・データを掛け合わせてシナジーを発揮できる可能性を秘めているのです。以下では、国内で実際に発表された代表的な異業種連携事例を2つ紹介します。

KDDIとローソンは、三菱商事を巻き込んだ資本業務提携を締結し、「リアル×デジタル×グリーン」の融合による新しい生活者価値創出を目指しています。この提携では、ローソンの約14,600店舗という強力なリアルチャネルと、KDDIの通信基盤や情報技術力・顧客データ基盤を連携。
例えば、KDDIのサービス(通信・保険・金融など)をローソン店舗で提供したり、ローソンの商品や決済サービスをKDDIのチャネルでも扱ったりする構想が検討されています。さらに店舗データと顧客属性データを統合することで、顧客体験の高度化や販促最適化、店舗オペレーション効率化といったシナジー創出が期待されているのです。
グリーン分野でも、ローソンの環境ビジョン「Lawson Blue Challenge 2050!」に向けた施策を三社で協調推進すると発表しており、環境価値を含めた中長期的な連携を志向している点が注目されます。
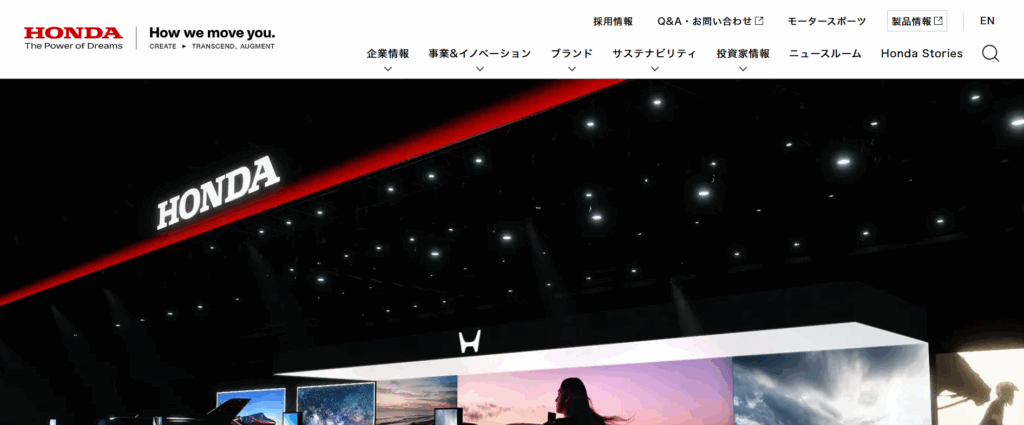
ソニーとHondaは、2022年にモビリティ領域での戦略的提携として合弁会社ソニー・ホンダモビリティ株式会社の設立に合意しました。この提携では、Hondaの環境技術・車体製造ノウハウ・アフターサービス運営能力と、ソニーが持つイメージング・センシング、通信・ネットワーク、エンタテインメント技術を融合させ、新たな電動車(EV)とモビリティサービスを共同展開する計画です。
提携によって、単なる車両開発にとどまらず、移動中の体験、車内空間のエンタメ、コネクテッドサービスなどの付加価値を統合的に提供するビジョンを描いています。両社の技術資産を持ち寄ることで、既存の自動車市場における差異化を図ると同時に、未来のモビリティ市場をリードする狙いがあります。
大企業とスタートアップの業務提携は、近年ますます注目を集めています。大企業が持つ資金力や社会的信頼と、スタートアップのスピード感や革新的な技術を組み合わせることで、従来の枠を超えたサービスを創出できるからです。
社会課題の解決や都市の利便性向上といったテーマにおいても、両者の強みを活かした取り組みが数多く進められています。ここでは、大企業×スタートアップの連携事例を紹介します。

西武鉄道・東急電鉄と電動マイクロモビリティのシェアリング事業を展開する株式会社Luup は、株式会社ブルーインキュベーションや東急株式会社と業務提携を発表しました。本提携では、西武・東急の駅や商業施設とLuupのシェアサイクル拠点を連携させることで、地域の回遊性を高め、沿線価値の向上を目指しています。
特に「鉄道×モビリティ」という組み合わせにより、駅から目的地までのラストワンマイル移動を快適にし、観光や日常利用の利便性を向上させる狙いがあります。また、電動キックボードや自転車といった次世代モビリティを活用することで、環境負荷低減や交通混雑緩和といった社会課題の解決にも寄与。都市開発や交通網の進化に、スタートアップの柔軟なサービスが大企業のインフラと結びついた好例といえます。

大手警備会社のセコムは、AIを活用した防犯・監視システムを提供するセーフィー株式会社と提携しました。この連携の目的は、映像データを活用した次世代のセキュリティサービスを共同開発することにあります。
セーフィの強みはクラウド録画やAI解析による効率的な映像管理であり、これをセコムの警備ネットワークや現場対応力と組み合わせることで、リアルタイムかつ高度な防犯体制を構築可能にしました。
例えば、商業施設やマンションにおいて不審者の行動を自動検知し、即座に警備員や関係者に通知できる仕組みの実現が期待されています。この提携は、従来の人による警備中心のモデルを進化させ、テクノロジーと人の力を融合した新しいセキュリティの形を示しています。
大企業がスタートアップの先端技術を取り入れることで、防犯領域でも大きな変革が進んでいる好例です。
グローバル化が進む中で、日本企業と海外企業の業務提携はますます重要性を増しています。海外市場に参入する際、現地に強力なネットワークを持つ企業と連携することで、文化や規制の壁を乗り越え、スピーディに事業を拡大可能です。
ここでは、中国、東南アジア、タイといった多様な地域における代表的な提携事例を紹介します。

フリマアプリ大手のメルカリは、中国の巨大EC企業アリババグループと提携し、中国市場への進出を図りました。アリババが運営する越境ECプラットフォーム「タオバオ(淘宝)」とフリマアプリ「シェンユー(閑魚)」を活用することで、日本の個人出品者が中国の消費者に向けて商品を販売できる仕組みを構築。
この連携により、中国国内で高まる日本製品への需要を取り込み、販売チャネルを一気に拡大しました。特に化粧品や日用品など、日本品質への信頼が厚い分野で高い成果が期待されています。アリババにとっても、日本の人気ブランドやユニークな中古商品がプラットフォームを充実させるメリットがあり、双方にとって市場拡大につながる提携事例です。

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、東南アジア最大級のスーパーアプリを提供するGrabに出資し、戦略的提携を進めています。Grabは配車サービスからスタートし、今ではフードデリバリーやデジタル決済など幅広い領域をカバー。MUFGはGrabの持つ顧客基盤やデジタル金融サービスの知見を活用することで、東南アジアにおける金融サービスの拡充を加速させています。
具体的には、キャッシュレス決済やマイクロファイナンスといった新しい金融インフラの構築が進められており、銀行サービスにアクセスできなかった層への金融包摂も狙いの一つです。伝統的金融とデジタルプラットフォームの融合により、新たな価値提供を実現するモデルケースといえます。

大手消費財メーカーの花王は、タイ最大級のコングロマリットであるCPグループと提携し、タイ市場におけるサステナビリティ経営を推進しています。この提携では、花王の持つ環境技術・製品開発力と、CPグループの広範な流通網を掛け合わせ、環境負荷を低減した製品やリサイクルシステムの普及を目指しています。
特にプラスチック容器の回収・再利用や、低炭素社会に資する製品開発など、循環型経済の実現に向けた取り組みが進行中です。タイはASEANの中でも人口が多く消費市場が拡大している国であり、現地大手と連携することで持続的な成長と環境課題解決を両立する姿勢を示しています。
日本企業の環境技術が、現地の社会インフラと結びついた好例といえるでしょう。

業務提携は企業の成長を加速させる大きなチャンスですが、安易に進めると期待外れの結果やトラブルを招くリスクもあります。成功の鍵は、提携を目的ありきで戦略的に設計することです。そのためには、自社の課題を明確化し、最適なパートナー選定から契約締結まで段階的にプロセスを踏むことが不可欠です。
以下では、業務提携を成功に導くための4つのステップを具体的に解説します。
業務提携を検討する際、まず重要なのはなぜ提携するのかを明確にすることです。例えば、「新市場へ参入したい」「研究開発力を補強したい」「販路を拡大したい」など目的は企業によって異なります。
目的を曖昧にしたまま提携を進めると、双方の期待値にズレが生じ、早期解消や不信感につながる恐れがあります。あわせて、自社が抱える課題を客観的に把握することも欠かせません。例えば「資金力不足で成長が鈍化している」「デジタル化に遅れている」といった弱みを整理することで、提携によって補うべきポイントが浮き彫りになります。
目的と課題を明確にすることが、最適なパートナーとの信頼関係を築く出発点になります。
次のステップは、明確化した目的と課題に基づき、最適なパートナーを探すことです。候補企業を探す際は、単なる規模や知名度だけでなく、自社との補完性や長期的なビジョンの一致度を重視することが重要です。
例えば、技術提携なら研究開発体制や知的財産の保有状況、販売提携なら流通網やブランド力などが評価基準になります。さらに、企業文化や意思決定のスピード感も実務上の相性に直結します。表面的な条件だけで選ぶと、後々摩擦が生じやすくなるため注意が必要です。
実際の選定プロセスでは、候補企業へのヒアリングや市場での評価調査を行い、複数候補の中から最もシナジーを発揮できる相手を選ぶことが成功への近道です。
パートナー候補が絞り込めたら、情報交換を行う前に必ず秘密保持契約(NDA)を締結する必要があります。業務提携では、事業戦略や顧客情報、技術ノウハウなど高度な機密情報をやり取りするケースが多く、情報漏洩のリスクを軽視すると大きな損害につながりかねません。
NDAを結ぶことで、相手方が情報を第三者に開示することを防ぎ、安心して交渉を進められる環境を整えられます。また、契約の内容には「秘密情報の範囲」「利用目的」「有効期間」などを具体的に定めることが重要です。双方が適切にルールを共有することで、初期段階から信頼関係を築きやすくなり、その後の契約交渉も円滑に進めやすくなります。
最後のステップは、具体的な条件を交渉し、正式な契約書を作成・締結することです。業務提携契約書には、提携の目的や範囲、役割分担、利益配分、契約期間、解消条件などを詳細に盛り込む必要があります。
特に、提携解消時の取り扱いや知的財産の権利関係はトラブルになりやすいため、事前に明確化しておくことが不可欠です。交渉段階では、法務部門や外部の専門家を交え、リスクを最小化する観点で条項を精査することが望まれます。
また、一度で全てを決定するのではなく、試験的な小規模提携から始め、成果を見ながら範囲を拡大する方法も有効です。慎重かつ段階的に進めることで、長期的に持続可能な提携関係を築けます。

業務提携は、自社の成長を加速させる有効な手段ですが、相手選びから契約条件の調整、リスク管理まで、専門的な知識と経験が不可欠です。特に海外企業との提携では、各国の規制や文化の違いに対応するため、現地事情に精通したパートナーのサポートが成功を左右します。
AXIA Marketingでは、市場調査から現地戦略の立案、提携先選定までワンストップで支援し、貴社の海外進出を力強く後押しします。海外展開や業務提携を検討している企業様は、ぜひご相談ください。
参考文献
Copy Link





