
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Contact
無料
見積もり・相談

Column
2025.10.09


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
企業のマーケティング戦略や商品開発においてよく耳にするインサイトという言葉ですが、単なる顧客ニーズとは意味が異なります。インサイトとは、消費者本人さえ気づいていない潜在的な欲求や行動の背景にある心理を指し、購買行動を引き出すための重要な手がかりとなるのです。
例えば、便利だから買うという表面的な理由の裏に、忙しい生活の中で少しでも自分の時間を確保したいという深層心理が隠れているケースもあります。本記事では、インサイトの定義やニーズとの違いを整理したうえで、実際にどのように見つけ出せばよいのか、具体例を交えてわかりやすく解説していきます。

インサイトとは、消費者の購買行動や選択の背後にある隠れた心理や動機を指します。一般的なニーズが表面的に認識できる欲求であるのに対し、インサイトは本人も自覚していない深層的な理由に基づいているのが特徴です。
例えば、安いから買うというニーズの裏には、「経済的に安心したい」「失敗して損をしたくない」等の心理が隠れています。このようにインサイトは消費者の行動の根拠をより本質的に捉えるものであり、マーケティングにおいては購買を促す強い動機づけになります。企業がインサイトを正しく把握できれば、単なる機能や価格の訴求だけではなく、感情や価値観に響く提案が可能になります。
その結果、競合との差別化やブランドロイヤリティの向上にもつながるのです。

ニーズとインサイトは似ているようで大きく異なる概念です。ニーズとは、消費者が自覚している欲求や必要性を指します。例えば、「もっと安い商品が欲しい」「移動手段が必要」といった具体的で表面的な要望がニーズにあたります。
一方、インサイトはそのニーズの奥に潜む本当の理由や隠れた心理を意味します。例えば、安い商品が欲しいというニーズの背景には、「経済的に余裕がない」「できるだけ損を避けたい」という深層心理が隠れているのです。また、移動手段が欲しいの裏には「時間を無駄にしたくない」「快適に移動したい」という価値観が存在します。
このように、ニーズは表面的な声であるのに対し、インサイトはその行動を生み出す根本的な動機を明らかにするものです。マーケティング戦略では、表面的なニーズに応えるだけでは競合と差別化が難しいため、インサイトを捉えることでより心に響く価値提案が可能となります。
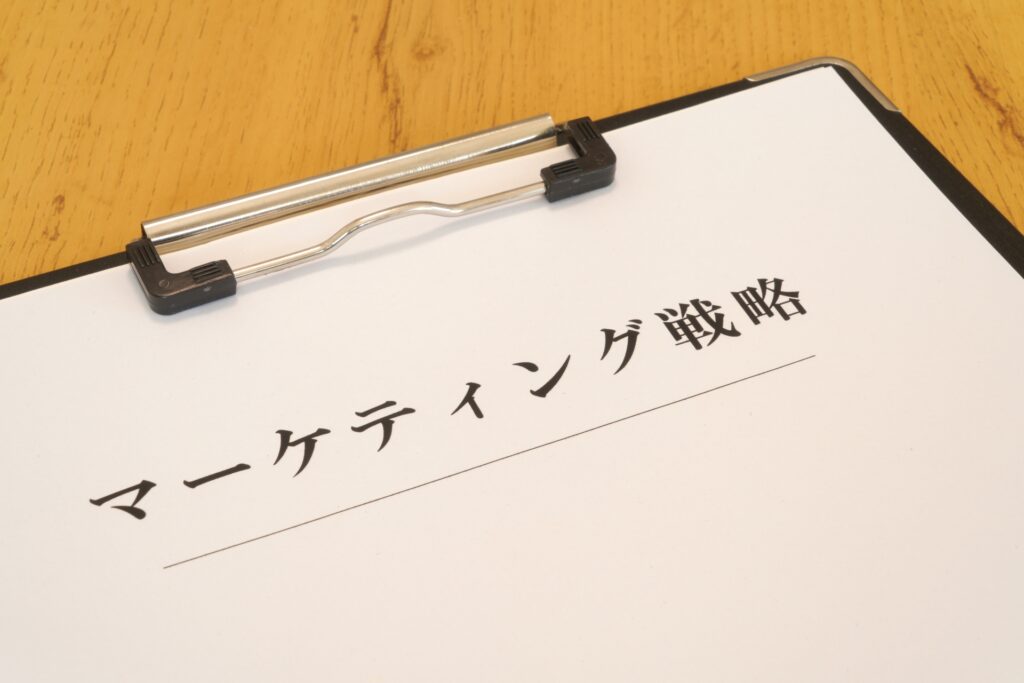
現代のマーケティングにおいて、単に消費者のニーズを把握するだけでは不十分です。競争が激化し、製品やサービスが似通う中で、企業が選ばれるためには顧客の心の奥にある本音を掴むことが不可欠になっています。
その核心を示すのがインサイトです。インサイトを理解することで、顧客との関係性を強化し、新しい市場の創出や競合との差別化にもつながります。
ここでは、インサイトが重視される3つの理由を具体的に解説します。
インサイトを捉えることは、単なる購買行動の理解にとどまらず、顧客の価値観やライフスタイル、心理的背景を把握することに直結します。顧客が「なぜその商品を選ぶのか」「なぜそのブランドに共感するのか」を深く理解できれば、表面的な広告メッセージではなく、顧客の心に響くコミュニケーションが可能になるでしょう。
例えば、健康志向だから低カロリー商品を選ぶというニーズの背後には家族のために長生きしたい等のインサイトが潜んでいることがあります。これを把握することで、企業は単なる商品提案にとどまらず、顧客の人生観や価値観に寄り添った提案を行えるのです。
その結果、単発的な購買ではなく、長期的なブランドロイヤルティや信頼関係の構築につながります。
インサイトは、潜在的なニーズを発見する重要な手掛かりとなります。顧客が自覚していない課題や欲求を掘り下げることで、新しい市場や製品のアイデアを生み出すきっかけになるのです。
例えば、時短家電が広がった背景にはもっと自分の時間を大切にしたいというインサイトがありました。顧客自身は掃除を楽にしたいとしか表現できないかもしれませんが、その奥にある時間価値への意識を捉えたことで、ロボット掃除機や全自動家電といった新市場が生まれました。
このようにインサイトは、顧客が気づいていない本当の欲求を形にする起点となり、商品開発やサービス設計において革新的な突破口を提供します。
どの業界においても競争は激化しており、機能や価格だけで差をつけることは難しくなっています。そこで重要となるのが、顧客インサイトを軸にした差別化戦略です。
同じニーズを満たす商品でも、「どんな心理を満たすか」「どんな価値観に寄り添うか」が異なれば、顧客に選ばれる理由が生まれます。化粧品業界を例にすると、美白効果や保湿効果といった機能性は当たり前になっていますが、「自分らしく輝きたい」「環境にも優しい製品を選びたい」というインサイトに対応することで、エシカルコスメやパーソナライズ化粧品が人気を集めています。
インサイトを理解し、競合がまだ気づいていない顧客の心を捉えることが、長期的なブランドの差別化につながるのです。
インサイトを見つけるには、表面的なアンケート結果や購買履歴を見るだけでは不十分です。顧客の本音や潜在的な動機は、時に言語化されておらず、データや数字だけでは捉えきれません。
そのため、複数の調査・分析手法を組み合わせ、定量的な視点と定性的な視点の両方から顧客を理解することが重要です。ここでは、企業がインサイトを発見する際に役立つ3つの代表的な調査・分析手法を解説します。
最初のステップは、既に手元にあるデータを活用することです。例えば、購買履歴やアクセス解析、SNSでの言及内容など、顧客との接点から得られる情報を体系的に分析すれば、消費者の傾向や隠れたニーズが見えてきます。
例えば、購入は少ないが頻繁にサイトを訪れている層がいれば、その背景には興味はあるが価格に不安があるといったインサイトが潜んでいるかもしれません。また、カスタマーサポートへの問い合わせデータや口コミも重要な手がかりです。
既存データを多角的に読み解くことで、顧客自身が気づいていない課題や欲求を掘り起こすことが可能となります。
定性的な調査の代表例が、顧客との直接的な対話です。インタビューや座談会、アンケート調査などを通じて「なぜその商品を選んだのか」「どんなシーンで使っているのか」を深掘りすると、表面的な理由の奥にあるインサイトが浮かび上がります。
特に一対一のインタビューでは、顧客が普段は口にしない不安や願望が語られることも多く、ブランドに対する率直な感情を知る貴重な機会となります。さらに、既存顧客だけでなく、競合の商品を使っている人や購入を迷っている層にも話を聞くことで、市場全体における潜在的なインサイトを把握可能です。
直接対話は時間と労力がかかりますが、他の調査手法では得られない生の声を引き出せる点が大きな強みです。
インサイトは、言葉ではなく行動の中に隠れている場合も少なくありません。例えば店舗での購買行動を観察すると、「商品棚の前で長く迷ったが結局買わなかった」「比較対象の商品を何度も手に取った」といった行動が見えてきます。
これらは、顧客が抱える潜在的な不満や欲求を示している可能性があります。デジタルの世界でも、ECサイトでの離脱ポイントやSNSでのリアクション分析など、行動観察を通じたインサイト発見は有効です。
顧客は必ずしも自分の感情やニーズを正確に言語化できるとは限らないため、行動という事実を観察することで、本人さえ気づいていない深層心理を読み解くことが可能になります。特にユーザビリティテストや購買体験のモニタリングは、実際の行動と心理を結びつけるうえで有効な手法です。
顧客の表面的な要望やデータだけではなく、「なぜそう感じるのか」「どんな状況でその行動をとるのか」といった深層心理=インサイトを捉えることは、商品開発やサービス改善において極めて重要です。
インサイトを正しく読み解いた企業は、競合との差別化や新しい市場の開拓に成功してきました。ここでは、日本国内で実際にインサイトを活用して成果を挙げた5つの事例を取り上げ、それぞれがどのように消費者心理を捉え、施策へと結びつけたのかを具体的に紹介します。
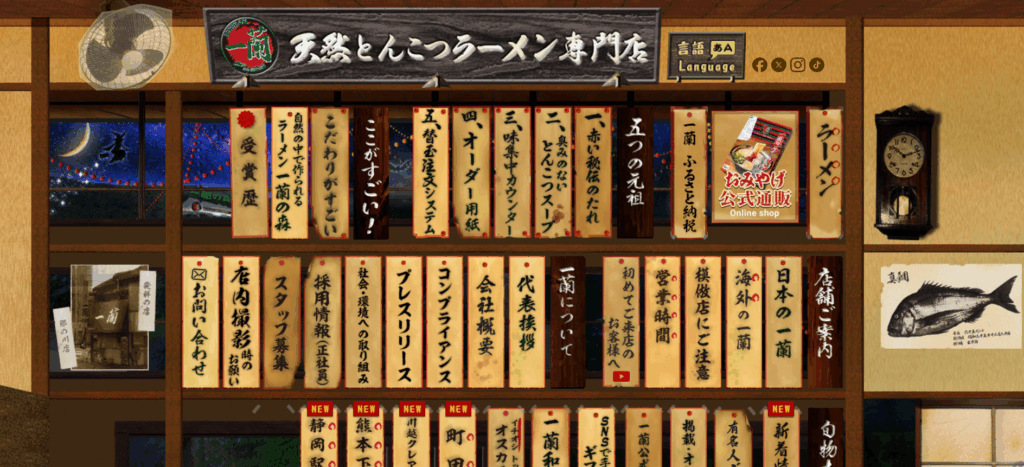
ラーメンチェーンの一蘭は、女性や一人客が「ラーメン店に一人で入ることを恥ずかしい」「周囲の視線が気になる」と感じているインサイトに着目しました。この心理的な障壁を取り除くために導入されたのが味集中カウンターです。隣席との間に仕切りを設け、さらに店員とのやり取りもすだれ越しに行えるようにすることで、完全に一人の空間でラーメンを楽しめる設計を実現しました。
結果として、一人客でも気兼ねなく来店できる環境が整い、女性客や出張中のビジネスマンなど幅広い層を取り込むことに成功しました。この施策は食事を誰かと共有するものという固定観念を打破し、一人でも自由に楽しめる空間という新たな価値を創出した好例といえます。
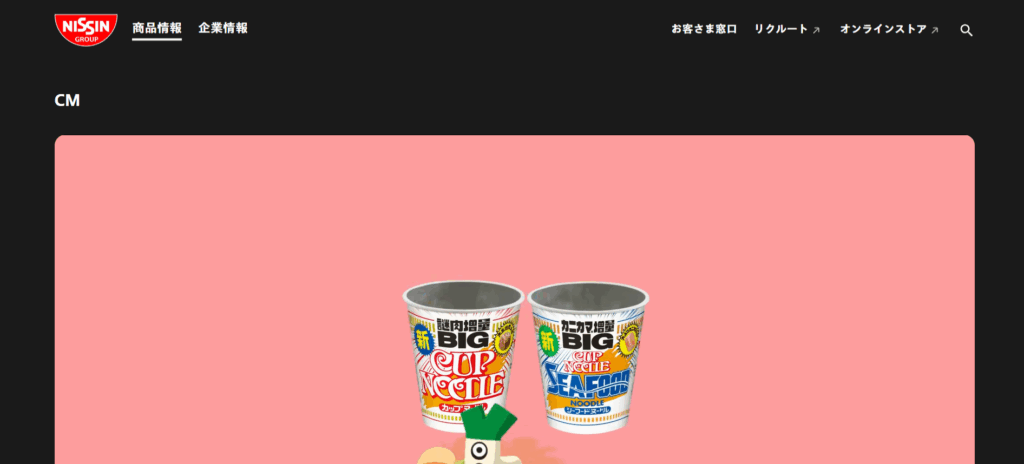
日清食品は、シニア市場におけるインサイトに注目しました。従来、シニア向け商品の多くは「減塩」「低カロリー」といった健康訴求が中心でしたが、実際には揚げ物やお酒を楽しみたいというアクティブシニアも多いことが分かってきました。
そこで日清は、フカヒレスープやスッポンスープなど贅沢な味わいを前面に打ち出したカップヌードルリッチを開発しました。これは健康一辺倒ではなく、時には贅沢を楽しみたいという潜在欲求に応える商品です。
結果として、シニア層を中心に特別感のあるご褒美食品として受け入れられ、新しい市場を切り開くことに成功しました。インサイトを見極めることで、既存の健康訴求とは異なる切り口を生み出した好例です。

味の素冷凍食品の人気商品ギョーザは、働く女性や主婦が抱える冷凍食品を使うと手抜きだと思われるのではという罪悪感に注目しました。そこで油も水も不要で、誰でもパリッと焼けるという調理法を強化し、これを永久改良として打ち出しました。
単なる利便性の訴求ではなく、「手間を省く=手抜きではなく、むしろ家族に美味しい食事を提供する工夫」という価値を前面に出したのです。このメッセージは共働き世帯や忙しい家庭に広く響き、「冷凍食品=時短と豊かさを両立する選択肢」というポジションを確立しました。
結果として、ギョーザは長年にわたり冷凍食品市場のトップブランドとして支持され続けています。

温湯温泉 佐藤旅館は、旅館は複数人で行くものという固定観念に対して、一人旅を望む層のインサイトを捉えました。特に現代では「自分の時間を大切にしたい」「一人で気兼ねなく旅を楽しみたい」というニーズが高まっており、それに応える形で「一人旅歓迎」「1名1室OK」を打ち出したのです。
さらにSNSや口コミを活用し、宿泊者自身が体験を発信するUGCキャンペーンを展開しました。これにより、一人でも安心して泊まれる宿というブランドイメージを確立し、新しい顧客層を獲得。従来の団体や家族客中心だった温泉旅館の利用形態に、多様性を取り入れることに成功しました。
これは、時代の価値観変化に柔軟に対応した好事例といえます。
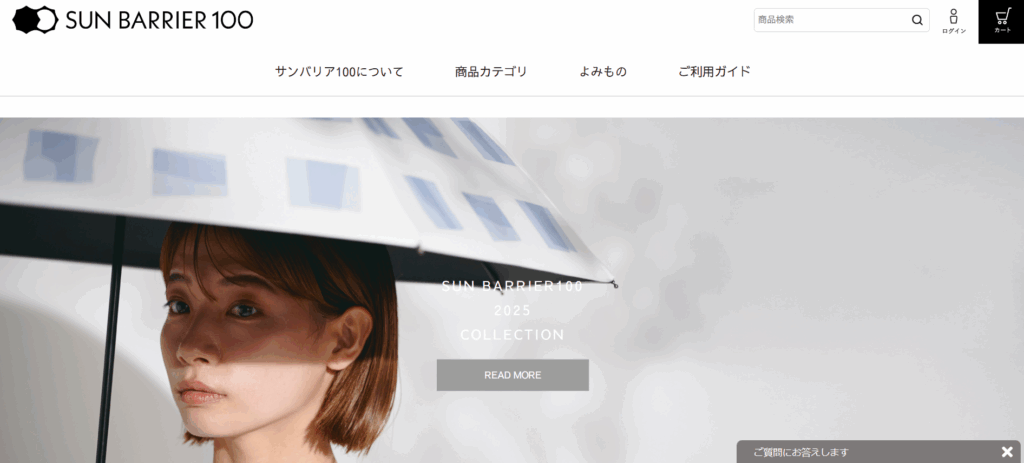
日傘ブランド「サンバリア100」は、日傘が消耗品と見なされてきた固定観念に挑戦しました。インサイトとして「環境配慮型の商品を選びたい」「長く使える品質を重視したい」というニーズが高まっている点に着目。そこで10年使える完全遮光日傘というメッセージを動画で可視化し、さらに全商品が100%遮光であることをECサイト上で明確にしました。
従来の日差しを避ける道具から、環境に配慮しながら美しく健康を守る製品へと価値を転換し、持続可能性を意識する層に強く訴求することに成功しました。この戦略は単なる機能訴求を超え、ブランドとしての信頼性や社会的評価の向上にもつながっています。
インサイトを正しく捉えるためには、単にデータを集めたり顧客の声を表面的に聞き取るだけでは不十分です。顧客が言葉にしていない本音や潜在的な欲求を見極めるには、分析の姿勢や思考プロセスに工夫が必要です。
特に、自分自身の先入観にとらわれず、事実と解釈を切り分けてさらに多様な視点を交えて考えることが重要になります。ここでは、良いインサイトを発見するために欠かせない3つのポイントを解説します。
良いインサイトを発見するためにまず大切なのは、自分自身の思い込みや先入観を捨てることです。顧客行動を観察するときに「若者はこうに違いない」「主婦ならこう考えるはず」といった決めつけをしてしまうと、真のニーズを見誤る可能性が高まります。
例えば、冷凍食品に対して手抜きというイメージが強かった時代に、実際の消費者は忙しい中でも家族に美味しい料理を提供したいという思いを抱いていた事例があります。つまり、既存の固定観念では見えなかったインサイトが隠れていたのです。
調査の際は自分の予想は間違っているかもしれないという前提に立ち、フラットな姿勢でデータや消費者の声を受け止めることが、深い洞察につながります。
インサイトを導き出すうえで重要なのが、事実と解釈を分けて考える姿勢です。例えば、売上データである商品の購買層に30代女性が多いというのは事実ですが、女性は見た目を気にしているから買っているというのはあくまで解釈にすぎません。
事実に基づかない解釈は、的外れなマーケティング施策につながりかねません。調査や分析を行う際には、まずは「誰が・いつ・どこで・何をしたのか」という事実を明確にし、それに対してなぜそうしたのかと仮説を立てる流れが必要です。
その後、追加の調査や顧客インタビューで仮説を検証していくことで、正しいインサイトに近づけます。事実と解釈を混同しないことが、分析の精度を大きく左右するのです。
一人の分析者や一部のチームだけでインサイトを見つけようとすると、視点が偏り、見落としが発生しやすくなります。そこで重要なのが、多様な視点を取り入れることです。
例えば、マーケティング部門だけでなく、営業担当者やカスタマーサポートの意見を取り入れると、顧客のリアルな声や現場での気づきを加味できます。また、消費者自身の発言に加え、SNSの投稿やレビューなど生活者が自然に発信しているデータも参考になります。異なる立場やバックグラウンドを持つ人々の視点を集約することで、バイアスのない多角的な分析が可能になり、より信頼性の高いインサイトにたどり着けます。
組織的に意見交換や、ブレーンストーミングを行う仕組みを整えることも効果的です。

インサイトは、単なる顧客ニーズの把握ではなく、購買や行動の背景にある本音を捉える重要なプロセスです。しかし、自社だけで正しく見極めるのは難しく、思い込みやデータの解釈ミスにつながることも少なくありません。
AXIA Marketingなら、専門的なリサーチ力と多様な分析手法を駆使し、企業が見落としがちな潜在的な顧客心理を明確化します。新商品開発やマーケティング戦略を成功に導くために、インサイトの調査・分析はぜひ専門家にご相談ください。
参考文献
Copy Link





