
About
Service
Knowledge

About
Service
Knowledge
Column
2025.09.19


記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
インドネシアは2億7000万人を超える人口を抱え、東南アジア最大の市場規模を誇る国です。経済成長も著しく、中間層の拡大により日本製品への需要は今後さらに高まると見込まれており、日本企業にとって非常に魅力的な輸出先と言えるでしょう。
しかし一方で、インドネシアでは食品・医薬品・化学製品などを中心に輸入規制が設けられており、事前の申請や認可が必要となる場合があります。また、関税制度も複雑で、品目ごとに細かく税率が設定されているため、十分な確認と準備が不可欠です。
本記事では、インドネシアの輸出規制品目や関税制度の基本、さらに日本企業が輸出ビジネスを行う際のメリットと注意点について具体的に解説します。インドネシア市場への進出を検討している企業の皆様に、実務に役立つ実践的な情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。

インドネシア市場への輸出を検討する前に、まず基本的な国情と日本との貿易関係を把握することが重要です。人口約2億7,000万人を擁するインドネシアは、東南アジア地域の経済大国として着実な成長を続けています。日本とインドネシアの経済関係は長年にわたって築かれており、両国にとって重要な貿易パートナーです。
本章では、インドネシアの基本情報と日本との貿易情報について詳しく解説していきます。
インドネシアの正式名称はインドネシア共和国で、首都はジャカルタに位置しています。国土面積は約192万平方キロメートルで、世界第4位の人口を有する国家です。主要産業には石油・天然ガス、パーム油、石炭、繊維製品などがあります。経済成長率は年平均5%前後を維持しており、中間所得層の拡大が続いているのが特徴です。
公用語はインドネシア語で、宗教はイスラム教が約90%を占めています。通貨はルピア(IDR)で、為替レートは変動制を採用しています。政治体制は大統領制を採っており、政治的安定性も保たれています。地理的にはASEANの中心に位置し、東南アジア地域のハブとしての機能を果たしていることも特徴です。
さらに、経済発展に伴い、インフラ整備も積極的に進められているのが現状です。特に道路、港湾、空港などの物流インフラの改善により、ビジネス環境が向上しています。また、デジタル化の推進により、電子商取引市場も急速に拡大しており、新たなビジネスチャンスが生まれています。
日本とインドネシアの貿易関係は、長年にわたって発展してきました。日本は、インドネシアから天然ガスや石炭、石油などの天然資源を中心に輸入しています。反対に、日本からインドネシアへの主要輸出品目として挙げられるのは、自動車、機械類、鉄鋼製品、化学製品などです。
日本企業のインドネシアへの投資も活発で、製造業を中心に多くの日系企業が進出しています。特に自動車産業では、トヨタ、ホンダ、スズキなどの日系自動車メーカーが現地生産を行っており、インドネシア国内市場だけでなく、周辺国への輸出拠点としても機能しています。
貿易総額は年々増加傾向にあり、日本にとってインドネシアは重要な貿易パートナーの一つです。インドネシア側でも日本の技術力や品質の高さが評価されており、特に精密機械や電子部品などの分野で日本製品への需要が高まっています。また、両国政府間での経済対話も定期的に開催され、貿易・投資環境の改善に向けた取り組みが続けられています。

インドネシアへの輸出(インドネシアの輸入)には、厳格な規制が設けられています。これらの規制を理解することは、スムーズな輸出ビジネスを展開するために必要不可欠です。規制は主に禁止品目と制限品目に分かれており、それぞれ異なる対応が求められます。
インドネシアで輸入できるのは未使用の新品であるという基本原則があります。
具体的に輸入が禁止されている品目としては、砂糖やイタリアからのモッツァレラチーズなどの食品分野があります。農業分野では農具・農園用具が禁止されており、工業分野では特定の冷蔵システムや水銀を含有する医療機器が該当します。
その他の禁止品目としては、あらゆる中古品、オゾン層破壊物質、有毒危険物質、有毒危険廃棄物と特定の非有毒危険廃棄物があります。これらの品目は一切の輸入が認められていません。
制限品目については、特別な許可や条件を満たすことで輸入が可能となります。食品・飲料・医薬品分野では米、トウモロコシ、砂糖、にんにくなどの基本食材から、アルコール飲料、牛肉類、医薬品まで幅広く制限されています。工業製品では携帯電話、タブレット端末、電気製品、計測機器なども制限対象です。
さらに、宗教的な理由によるハラル認証が必要な品目もあります。これらの規制に対応するため、輸出前の十分な調査と準備が重要となるのです。

インドネシアの関税制度は財務省が管轄しており、担当は関税総局です。関税率は輸出入される品目や相手国、適用される協定によって大きく異なります。日本企業がインドネシアに輸出する際は、これらの関税制度を正しく理解することが重要です。
インドネシアの関税率は複数の制度によって決定されます。種類は一般税率のほか、ASEAN共通効果特恵関税(CEPT)、自由貿易協定(FTA)の適用税率、一般特恵関税制度(GSP)、世界的貿易特恵関税制度(GSTP)などです。日本からの輸出品については、日本インドネシア経済連携協定(JIEPA)による特恵税率の適用が可能な場合もあります。
輸入関税の基本税率は以下のように定められており、国内産業を保護するために輸入品には高い税率が適用される傾向があります。最必需品は0~10%、必需品は10~40%、一般品は50~70%、贅沢品は最大200%という税率設定です。この分類は明確な基準がなく、当局との交渉が必要になるケースが多いのが実情です。

インドネシアへの輸出ビジネスには、多くの企業が注目する魅力的なメリットがあります。東南アジア地域における戦略的な重要性と、将来性の高い市場特性により、日本企業にとって大きなビジネスチャンスが期待できます。
ここでは主要な3つのメリットについて詳しく解説していきます。
インドネシアの経済成長率は安定しており、今後も継続的な拡大が見込まれていることは魅力的なポイントです。人口ボーナス効果により、労働力人口の増加と中間所得層の拡大が同時に進行しています。これにより、消費市場の規模が年々拡大しており、日本製品への需要も増加傾向にあるのです。
政府主導のインフラ開発プロジェクトも活発に展開されており、経済成長を支える基盤が整備されています。特に新首都ヌサンタラの建設計画や、高速道路網の拡張など大規模なインフラ投資が予定されています。これらのプロジェクトにより、建設機械や産業機器などの日本製品への需要が高まることが予想されているのです。
さらに、デジタル経済の発展により新たな市場機会も創出されているのもポイントです。電子商取引市場の急成長に伴い、物流システムや決済システム関連の需要も増加しており、日本企業の技術力を活かせる分野が拡大しています。このような多面的な成長要因により、長期的な事業展開が可能な魅力的な市場環境が形成されています。
人口約2億7,000万人を有するインドネシアは、東南アジア地域で最大の消費市場を形成しています。この人口規模は日本の約2倍に相当し、巨大な消費ポテンシャルを秘めていると考えられるでしょう。特に若年層の比率が高く、新しい商品やサービスに対する受容性が高いことが特徴です。
地域別に見ると、ジャワ島を中心とした都市部では購買力の高い消費者層が形成されています。ジャカルタ首都圏だけでも約3,000万人の人口を擁しており、一つの都市圏だけで多くの国の人口を上回る規模です。このような大規模市場では、商品の大量販売が可能であり、スケールメリットを活かしたビジネス展開ができます。
また、島嶼国家という地理的特性により、地域ごとに異なる消費パターンや需要が存在します。これにより、多様な商品展開や地域特性に応じたマーケティング戦略が可能になります。市場規模の大きさと多様性により、リスク分散を図りながら安定的な売上基盤を構築できる環境が整っているのです。
インドネシアは東南アジア地域の地理的中心に位置し、周辺国へのハブ機能を果たしています。ASEAN最大の経済規模を背景に、地域内貿易の重要な拠点としての役割を担っています。インドネシアを拠点とすることで、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピンなど周辺国への展開も効率的に行うことが可能です。
港湾インフラの整備も進んでおり、特にタンジュンプリオク港やタンジュンペラック港などの主要港湾では、大型コンテナ船の寄港ができます。これにより、日本からの直接輸送コストを抑制しながら、効率的な物流体制を構築できるのです。また、空港インフラも充実しており、スカルノ・ハッタ国際空港は東南アジア地域のハブ空港として機能しています。
他にも、ASEAN自由貿易協定(AFTA)により、域内貿易では関税優遇措置が適用されます。インドネシアで現地生産や組み立てを行うことで、ASEAN域内への輸出時に低い関税率を適用できる場合があります。このような地理的優位性と制度的メリットを活用することで、東南アジア地域全体を視野に入れた事業展開が可能となるのです。

インドネシアでのビジネスには多くの魅力がある一方で、日本企業が注意すべき重要な課題も存在します。これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることが成功の鍵となります。
本章では文化的違いから法制度の複雑さまで、多面的な注意点について詳しく見ていきましょう。
インドネシアのビジネス環境は、複雑な法制度と多層的な規制によって特徴づけられています。投資法、会社法、労働法、環境法など、事業運営に関わる法律が多数存在し、それぞれが頻繁に改正されているのです。特に外国投資に関する規制は厳格で、業種によっては外資出資比率の制限や特定の許認可が必要です。
輸入業務においても、輸入業者認証番号(API)の取得が必要であり、品目によっては追加の許可や認証が求められます。これらの規制は省庁ごとに管轄が分かれており、手続きの複雑さが事業開始までの期間を延ばす要因となっています。また、中央政府と地方政府の規制が異なる場合もあり、事業展開する地域ごとに個別の確認をしなければなりません。
法令の解釈についても、担当官によって見解が異なることがあります。このため、現地の法務専門家や経験豊富なコンサルタントとの連携が不可欠です。法的リスクを最小化するためには、事業計画段階から法的適合性の検証を行い、継続的な法令遵守体制を構築することが重要になります。
インドネシアは多様な文化と宗教が共存する国家であり、日本企業はこれらの文化的差異を理解し、尊重しなければなりません。人口の約90%がイスラム教徒であることから、ハラル対応は食品業界に限らず重要な要素となります。また、ラマダン期間中の働き方や、定期的な祈りの時間への配慮も求められることにも注意しなければなりません。
ビジネス慣行においても大きな違いがあります。インドネシアでは人間関係を重視する文化があり、信頼関係の構築に時間をかける傾向があります。意思決定プロセスも日本とは異なり、合意形成に時間がかかる場合が多いです。
また、上下関係を重視する階層社会の側面もあり、組織運営においては適切な敬意を示すことが重要です。コミュニケーションスタイルも日本とは大きく異なり、直接的な批判や否定を避ける傾向があることから「はい」という返事が必ずしも同意を意味しない場合もあります。このような文化的特性を理解し、現地スタッフとの効果的なコミュニケーション方法を確立することが、事業成功の重要な要素となるでしょう。
インドネシアでは政府主導でインフラ整備が進められていますが、広大な国土と分散した島嶼構造により、地域格差が大きな課題となっています。ジャカルタなどの大都市圏では比較的整備が進んでいますが、地方部では道路、港湾、電力供給などの基本インフラが不十分な地域も存在します。
物流インフラの課題は特に深刻で、道路渋滞による配送遅延や、港湾での荷役効率の悪さが事業コストを押し上げる要因となっているのです。また、電力供給の不安定さにより、製造業では自家発電設備の導入が必要になる場合があります。通信インフラについても、地方部では高速インターネット接続が困難な地域が残っています。
これらのインフラ制約は、事業計画の策定時から考慮することが大切です。物流ルートの複数確保、予備電源の準備、通信手段の多様化など、インフラリスクに対する備えをしておきましょう。また、政府のインフラ開発計画を注視し、将来のインフラ改善を事業戦略に組み込むことで、長期的な競争優位性を確保することができるでしょう。

インドネシアへ輸出する際には、基本的な通関書類を整えておくことが不可欠です。輸出国と輸入国双方の規制に適合した書類を提出することで、スムーズな通関が可能になります。ここでは、インドネシアで特に求められる主要な書類について解説します。
インボイスは輸出取引の基本となる書類で、取引内容を明確に示す役割を果たします。品目名、数量、単価、合計金額、取引条件などを正しく記載する必要があります。インドネシア税関では、輸入申告に基づく関税や付加価値税の算定にインボイスを参照します。そのため、誤りや記載漏れがあると、通関遅延や追加確認が行われるリスクがあります。輸出企業は、相手先企業と事前に記載内容を確認しておくことが望ましいです。電子データの形式で提出を求められる場合もあるため、最新の通関要件を確認することも重要です。
パッキングリストは輸送貨物の内訳を示す書類で、貨物検査や通関審査に用いられます。梱包ごとの重量や容積、数量、内容物の詳細を記載するのが基本です。インドネシアの港湾や空港では、検査官がパッキングリストをもとに実貨物との照合を行います。記載が不正確だと、貨物検査の強化や通関の遅延につながる可能性があります。インボイスとの記載内容に齟齬がないか、事前に確認しておくことが不可欠です。輸送業者と連携し、正確な情報を反映させることが円滑な通関につながります。
船荷証券は貨物の受領と輸送契約を証明する重要な書類です。インドネシアの輸入手続きにおいて、B/Lは輸入者が貨物を受け取る権利を示すために利用されます。発行元は船会社またはフォワーダーであり、貨物の詳細や積み地、仕向け地などが記載されます。輸入者は、このB/Lを提示することで現地で貨物を引き取れる仕組みです。近年は電子B/L(eB/L)の利用も広がっており、インドネシアでも徐々に導入が進んでいます。輸出者は取引相手や物流業者とB/Lの発行方法を事前に確認しておく必要があります。
一部の品目については、インドネシア当局が発行する輸出許可証(Export License)が必要です。特に農産品や鉱物資源、戦略物資などの輸出では規制が厳格に設けられています。さらに、自由貿易協定(FTA)やEPAを活用するためには、原産地証明書(Certificate of Origin, CO)が不可欠です。この書類があることで、インドネシア側での関税減免措置が適用される場合があります。発行機関は日本商工会議所などで、申請にあたっては輸出貨物の原産性を証明する必要があります。COの記載不備や遅延は、関税優遇の適用漏れにつながるため注意が必要です。輸出前に必ず取得しておくことが望まれます。

インドネシアには多くの日本企業が進出し、現地市場で成功を収めています。これらの企業の事例を通じて、インドネシア市場での事業展開のポイントや成功要因を理解することが可能です。
業界をリードする代表的な日系企業の取り組みについて詳しく見ていきましょう。
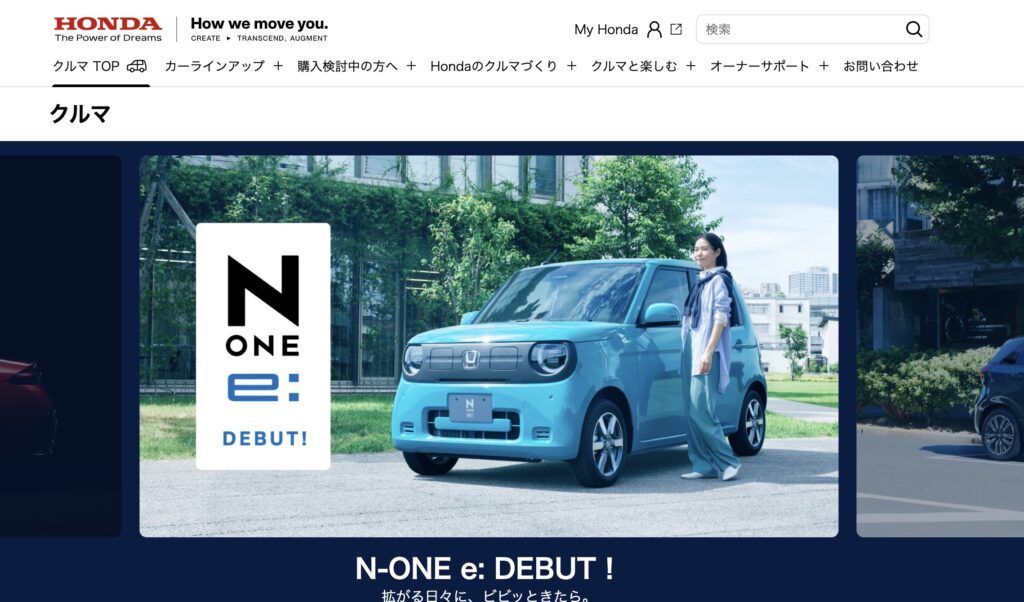
ホンダはインドネシアの二輪車市場で圧倒的なシェアを持つ代表的な日系企業です。1970年代から現地生産を行い、燃費効率に優れた小型バイクを中心に、インドネシアの交通事情や経済環境に合った製品を展開してきました。その結果、幅広い層の消費者から強い支持を獲得しています。
さらに現地化戦略の一環として、インドネシア人エンジニアの育成やサプライヤーとの協力体制を積極的に推進し、製品の品質向上と安定供給を実現しています。販売後のアフターサービス網の整備も進め、顧客満足度を高める取り組みを継続してきました。
四輪車分野ではまだシェアは限定的ながら、コンパクトカーや環境対応車を中心に商品展開を強化し、市場での存在感を高めつつあります。ホンダの歩みは、長期的な視点に基づいた市場理解と現地適応が企業成功の鍵であることを示す好例と言えるでしょう。

ユニクロは2013年にジャカルタで第1号店をオープンして以来、インドネシア国内で着実に店舗数を増やし、現在では主要都市を中心に幅広く展開しています。日本発のファストファッションブランドとして、高品質かつベーシックな衣料を比較的手頃な価格で提供し、独自の市場ポジションを確立しました。
特に機能性素材を活用した商品は、年間を通して温暖な気候を持つインドネシアに適しており、多くの消費者から支持を集めています。インドネシアは若年層が多くファッションへの関心も高いため、ユニクロのブランドコンセプトとの親和性が強いことも成長を後押ししています。
さらに中間層の拡大により、価格と品質のバランスを求める消費者が増えており、そのニーズに応える形でユニクロは存在感を高めていることも特徴です。店舗展開に加えオンライン販売の強化や現地スタッフ教育にも注力し、日本品質のサービスを提供している点も競争優位性の一因です。

ヤクルトは1970年代にインドネシア市場へ参入した先駆的な日系企業であり、日本独自の乳酸菌飲料を現地に根付かせてきました。特に「ヤクルトレディ」による訪問販売は、地域社会に密着した独自の流通網として機能し、スーパーやモールでの実演販売とあわせて重要な販売チャネルとなっているのです。
現地生産体制を整備し、品質管理を徹底することで、日本と同等の品質を維持しつつ新鮮な商品を供給しており、消費者から厚い信頼を獲得しています。健康志向の高まりを背景に機能性食品市場が拡大する中、ヤクルトは研究開発や商品改良にも注力し、新たな価値提案を通じて市場での存在感をさらに強めています。長期的な視点でブランドを育成してきた同社の取り組みは、継続的投資の重要性を示す良い例です。

インドネシアへの輸出は、書類準備から輸送、通関までの一連のプロセスを正しく踏むことが重要です。各段階で必要な手続きや提出書類を把握していないと、遅延やトラブルにつながる可能性があります。ここでは一般的な輸出の流れを順を追って解説します。
まず輸出者とインドネシア側の輸入者との間で、売買契約を締結します。契約内容には品目、数量、価格、支払条件、輸送条件(インコタームズ)などを明確に記載する必要があります。曖昧な契約は後のトラブルを招きやすいため、事前に両者で十分に確認することが大切です。契約内容はインボイスや船荷証券にも反映されるため、整合性を取ることが求められます。輸出契約は全ての通関手続きの基盤となるため、慎重に進めましょう。
契約が締結されたら、輸出に必要な各種書類を準備します。主な書類はインボイス、パッキングリスト、船荷証券、輸出許可証や原産地証明書などです。インドネシアでは輸入規制品目に関して追加書類が必要となる場合もあるため、事前の確認が欠かせません。書類の不備や遅れは通関遅延や追加検査につながります。輸出者は物流業者や通関士と連携し、最新の規制に沿った正確な書類を整備する必要があります。電子申請が導入されている場合は、システム利用にも慣れておくと安心です。
必要書類が揃ったら、貨物の輸送を手配します。輸送手段には海上輸送や航空輸送があり、輸出品目や納期に応じて選択します。輸送契約はフォワーダーや船会社を通じて行い、B/LやAWBの発行を受ける流れです。貨物の梱包や表示はインドネシアの規制に適合している必要があります。誤った表示や梱包は現地で問題となりやすいため、国際基準に沿った準備が求められます。積み込み後は、輸出申告に必要な情報が正しく反映されているか確認しましょう。
輸送と並行して、輸出国側の税関へ輸出申告を行います。日本からの輸出であればNACCSシステムを利用して電子申告を行うのが一般的です。申告内容はインボイスやパッキングリストと一致していることが前提で、食い違いがあると審査に時間がかかります。税関では輸出規制の対象品目かどうかもチェックされます。不正確な申告は罰則やペナルティの対象となるため注意が必要です。必要に応じて税関検査が行われ、クリアすれば輸出許可が下りる流れです。
貨物がインドネシアに到着すると、輸入者が現地税関で輸入申告を行います。ここで提出されるのはインボイス、パッキングリスト、B/L、輸入許可証などです。インドネシアではHSコードの適用や関税計算が厳格に行われ、書類内容との一致が重視されます。規制品目の場合は追加の許可証や証明書が必要となる場合があります。税金や関税を納付した後、貨物の引き取りが可能となります。ここまで完了して初めて輸出取引が成立します。
輸出が完了した後も、輸入者とのアフターフォローを行うことが大切です。貨物の破損や数量不足などが発生した場合は、迅速な対応が信頼関係の維持につながります。特にインドネシアでは通関後に追加確認が行われるケースもあるため、書類やデータを一定期間保管しておくと安心です。さらに、輸出の実績を社内で共有し、次回の取引に生かすことも重要です。アフターフォローまでを一連の輸出プロセスとして捉えることが、長期的な取引関係の構築につながります。

インドネシア市場で成功するには、文化的多様性や地域格差を踏まえた綿密な市場調査が不可欠です。統計データや市場規模などの定量情報に加え、消費者インタビューや現地視察による定性的な洞察を組み合わせることで、都市と地方、世代や所得層ごとの消費行動の違いを把握できます。
競合分析では日系のみならず欧米系や現地企業の戦略を幅広く調べ、成功・失敗の両事例から学ぶことが必須です。さらに輸入規制や投資規制、労働法など頻繁に変化する法制度の最新情報を継続的に収集する体制を整えることで、リスクを抑えながら市場進出を進めることができるでしょう。

AXIA Marketingは、独自のネットワークと豊富な経験を活かし、日本企業のインドネシア市場進出を力強く支援する調査サービスを提供しています。AXIA Marketingでは、単なるデータ収集にとどまらず、事業戦略に即した調査設計により実践的で価値ある情報を届けられるのが強みです。
また質の高いインタビュー調査を重視することで、現地の声やインサイトを丁寧に把握し、数字だけでは見えない市場の実態を把握できます。インドネシア特有の文化や商習慣を深く理解した調査は、輸出や投資を検討する企業にとって信頼できる指針となるでしょう。
海外展開の可能性評価からリスク把握まで、専門チームが多角的にサポートし、戦略的な意思決定を後押しします。詳しくは公式サイトをご覧ください。
参考文献
インドネシアでの通関・税関(輸出入)手続きのやり方について|手順や必要書類一覧、関税やトラブル事例も解説
インドネシアとの貿易(輸出・輸入)における基礎知識を徹底解説
Copy Link





